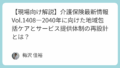令和7年4月、介護保険制度における実務改正が施行され、特に居宅ケアマネジャーの業務に直結するいくつかの重要な変更が始まりました。
「記録様式が変わるらしい」「TAISコードの記載が必要と聞いたが、どう対応すればよいのか?」
そんな不安を抱えるケアマネの皆さんに向けて、今回の制度改正の背景とポイントを、実務目線でわかりやすく整理します。
制度改正の時系列:令和6年と令和7年の違い
まず整理しておきたいのが、「いつ・どんな改正があったのか」という時系列です。
- 2024年(令和6年度)には、介護報酬改定(+1.59%)が行われ、処遇改善加算の一本化やLIFE加算の見直しなどが主な変更点でした。
- 一方、2025年(令和7年)4月から施行されたのが、実務様式やシステム整備に関わる制度改正です。
つまり、居宅ケアマネジャーの「日々の書類作成や記録」「事業所間の情報共有」に直接影響するのは、令和7年施行の内容になります。
1.ケアプランデータ連携システムとは?
ケアプランデータ連携システムとは、居宅介護支援事業所と各サービス事業所間で、ケアプラン・サービス提供票・実績票などを電子的に標準フォーマットでやり取りできる国主導の仕組みです。
これまでは、FAXや手渡し、郵送でやり取りするケースが多く、記録漏れ・連絡ミス・二重記録といった問題が生じやすい状況でした。
そこで厚生労働省は、ケアマネジメントの質向上と業務効率化を目的に、2025年度から段階的な全国展開を開始し、2028年(令和10年)4月からの全面運用を目指しています(介護保険最新情報Vol.1405より)。
データ連携システムの導入には、「標準仕様に対応した介護ソフト」や「事業所内の通信環境整備」が必要になります。
国保中央会や一部自治体では、導入支援・補助金制度も用意されており、今後の義務化を見据えて早期の準備が求められます。
2.ケアプラン様式の変更とTAISコードの記載義務化
令和7年4月のもう一つの重要な変更が、ケアプラン第6表(サービス利用票)および第7表(サービス別表)への「TAISコード」または「届出コード」の記載欄追加です(介護保険最新情報Vol.1286より)。
これまで、福祉用具貸与の欄には「車いす」「ベッド」といった一般名を記入するだけで済んでいました。しかし、同じ名称の用具でも、メーカーや機種によって性能や価格、適合基準は異なります。
そこで導入されたのが、「TAISコード(Technical Aids Identification System)」です。
これは公益財団法人テクノエイド協会が管理する製品識別番号で、各種福祉用具に個別の番号が割り当てられています。
▼ TAISコード記載の狙い
- 用具の機種特定を通じて、給付内容の正確性と透明性を担保
- 記録ミスや不正請求の予防
- 情報共有時における言葉のずれや解釈違いの防止
ケアプランデータ連携システムを導入している事業所では、このTAISコードまたは届出コードの記載が義務化されました。
一方、未導入の事業所については、当面は記載任意(空欄可)とされています。
とはいえ、将来的には全国で統一運用される見通しのため、今のうちから福祉用具事業者との連携体制を整えておくことが重要です。
3.実務での影響と対応のポイント
この制度改正は、単に様式が変わるだけではありません。記載義務が増えることにより、以下のような実務影響が想定されます。
▽ よくある現場の変化と課題
- 記録行数が増え、入力作業が煩雑になる
→ 利用者1人に対して複数の用具があれば、その都度コード・機種名を記載する必要がある - 記載ミスや入力漏れによる減算・返戻のリスクが高まる
→ 特に旧様式のまま運用している事業所では注意が必要 - 介護ソフトや業務フローの見直しが必要
→ 使用中のソフトが新様式に対応しているか、ベンダーに確認を - 福祉用具貸与事業所との情報共有が必須になる
→ 機種名やコードの一覧を事前に取り寄せ、記録に反映する体制が求められる
4.ケアマネが今すぐ着手したいこと
これらの変化に対応するため、居宅ケアマネとして以下の準備が推奨されます。
- ソフトのバージョン確認とアップデート
- 福祉用具業者からのTAISコードリスト取得と共有ルートの整備
- 記載ミス防止のための内部チェックシート作成
- 自治体や研修機関の説明会に参加して最新情報を収集
- 事業所内での業務分担や記録様式の統一化を検討
特に新任ケアマネの方には、「すべてを覚える」よりも「どこに聞けば正確な情報が得られるか」を把握することが大切です。
まとめ
今回の制度改正は、居宅ケアマネジメントの記録の精度と、事業所間の連携力を問うものでもあります。
- ケアプランデータ連携システムの導入は、将来的な必須対応
- TAISコード記載義務は、支援の質と給付の適正化を図る仕組み
- 対応の第一歩は、「まず確認」「必要な連携先とつながる」こと
令和7年の改正は、“ケアマネとしての成長のチャンス”でもあります。変化を前向きに受け止め、現場の仲間と協力しながら一つずつ取り組んでいきましょう。