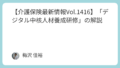— 形だけの訪問を卒業し、根拠にもとづく支援につなげる
居宅ケアマネジャーにとって、モニタリングは毎月の定例業務でありながら、支援の質を左右する最重要プロセスです。ここでの観察と聞き取りが浅いと、「変化に気づけない」「記録に落ちない」「ケアプランの修正が遅れる」という負の連鎖が起こります。反対に、具体性・客観性を意識したモニタリングは、利用者のニーズやリスクの早期発見に直結し、チーム全体の意思決定を強く後押しします。本稿では、定期訪問で注視すべき視点、記録への落とし込み方、「なんとなく」という曖昧さを観察と言葉に変える技術を、実例と手順で丁寧に解説します。
1.定期訪問で注視すべき3つのポイント
- 身体の状態:立ち上がり・歩行・食事量・睡眠・表情などの変化
- 生活環境:家屋の安全、動線、福祉用具の適合と使用状況
- 家族・支援体制:介護者の体力・時間・心身の余力、支援網の揺らぎ
定期訪問が「会話して帰る場」になっていませんか。まずは身体の状態です。立ち上がり動作に要する時間、歩幅、途中で家具に触れる回数、食事の摂取量、夜間覚醒の有無、起床時の疲労感、表情の明るさや声の張りなど、数値や行動で捉えられる項目に置き換えて観察します。たとえば、「ふらつきが強い」ではなく「玄関から居間まで約十メートルの歩行に前回より二十秒多く要し、壁に手を添えた回数が三回に増加」と記します。これだけで、比較できる具体的なデータが揃い、介護職・看護職・主治医に伝わる情報へ変わります。
次に生活環境です。通路が狭くなっていないか、じゅうたんやコードが躓きの原因になっていないか、照明の明るさは適切か、福祉用具は本人の体格と目的に合っているか、そして実際に使えているかを確認します。「手すりが設置している」という事より、「立位保持の際に手すりの位置が低く、肩がすくんで疼痛を訴える」というような適合性・非適合性を評価する視点が重要です。冷蔵庫の中身の消費期限や郵便物の滞留の有無は、利用者の生活状況を把握できる大事な兆候になります。
最後に家族・支援体制です。主介護者の腰痛や睡眠不足、勤務先や就労形態などの変更、近隣支援者の離脱など、支援網の微細な揺らぎは在宅介護の継続にとって大きく影響します。家族が本人の前で言いにくい体調変化や精神的疲労感などの本音は、事前連絡で聞き取り、会議や記録でケアマネが代弁し、本人を取り巻く環境課題として関係者間で共有します。
小さなサインを一つずつ「時間」「回数」「距離」「量」に置き換える
利用者の小さな変化は、あいまいな印象ではなく、「どのくらいの時間がかかったか」「何回繰り返したか」「どのくらい歩けたか」「どれだけ食べたか」といった具体的な数字や行動として記録することが大切です。そうすることで、前回との違いが比較でき、支援につながる確かな情報になります。
2.状態変化の兆しを記録に落とし込む方法
- 事実→解釈→対応の順で書く
- 比較(前月・退院直後・直近の発熱後 など)を必ず入れる
- 主観と客観を分け、数値・行動・場面で表現する
モニタリングの価値は、現場で得た観察を、誰が読んでも同じ理解にたどり着く記録へ変換できるかで決まります。おすすめは「三段構え」です。
1)事実:見たこと・聞いたこと・測ったことのみを書く
2)解釈:事実から推測される課題やリスクを簡潔に述べる
3)対応:次に取る支援・連絡・調整・検討事項を明記する
記録の具体例(望ましい書き方)
- 事実:居間から台所まで約十メートルの移動に前回より二十秒多く要し、途中で壁に手を添える場面が三回。昼食は半量のみ。会話中に目を閉じる行為が二度。
- 解釈:疲労感の増加と体力低下が推測され、転倒リスク上昇。栄養摂取の低下も併発の可能性。
- 対応:訪問看護へ本日中に情報提供。歩行補助具の再評価を福祉用具事業者へ依頼。次回まで食事内容の写真記録を家族へ依頼。
よくある惜しい書き方
- 惜しい:「最近元気がない様子」
→ 改善:「会話の継続時間が十分から三分に短縮し、途中で二回休止。声量が前回より低い」 - 惜しい:「食欲低下」
→ 改善:「昼食を半量で中止。昨日の夕食も半量との本人談。体重は先月から一・二キログラム減少」
さらに、比較の視点を必ず入れます。「前回訪問時」「退院直後」「発熱後三日目」などの基準を示すことで、時間軸上の変化が明確になり、サービス担当者会議での合意形成や、主治医への連絡の根拠が揃います。
また、記録のなかでは主観(本人の感覚・家族の感想)と客観(観察・測定・写真)を区別し、混在させないことが重要です。これにより、「本人はだるいと訴える(主観)」が「歩行時間の延長・食事量の減少(客観)」と照応しているかを、第三者が検証できます。
伝わる記録は、事実・比較・対応の三点セットです。ここまで書ければ、ケアプラン修正の判断が自然に導かれます。
3.「なんとなく調子が悪そう」という捉え方は不適切か
- 印象は入口、観察が本体
- 曖昧な書き方を具体的な書き方に置き換える手順をもつ
- 共有のための言い換えと優先度整理を行う
現場で最初に生まれるのは「雰囲気的な違和感」です。これは大切な入口ですが、印象のままでは支援に結び付きません。次の三段階のステップで、曖昧な表現を具体的な書き方に変えます。
第一段階:印象の言語化
「以前より疲れて見える」「反応が遅い気がする」など、感じたことをまず一文でメモに残します。印象を捨てず、手がかりとして保持します。
第二段階:行動・数値・場面への変換
印象を、目に見える行動、測ることができる数値、場面をイメージしやすい表現に書き換えます。
例)「疲れて見える」→「椅子からの立ち上がりに3回の試行を要し、成功後に15秒の休止を要した」「会話を3分継続できず一度休止」。
第三段階:共有に耐える表現へ整える
サービス事業者や医療関係者へ伝える際は、まず観察した事実(客観的情報)を書き、その後に本人や家族の訴え(主観的情報)を添えるようにします。
例)「歩行時間の延長と会話継続時間の短縮が同日に観察されました(客観)。前日睡眠が浅かったと本人が述べています(主観)。訪問看護へ本日連絡し、症状観察と水分摂取を依頼します(対応)。」
また、「どの課題から手を付けるか」は優先度で整理します。転倒・誤嚥・急変の恐れがあるものを最優先とし、次いで栄養や意欲、生活管理の課題を並べます。優先度は記録の見出しにも反映させると、関係者が即座に動けます。
「なんとなく」という気づきは重要です。最初に感じた違和感を大切にしながら、それを具体的な観察事実に置き換える習慣を身につけることが、ケアマネの専門性につながります。
まとめ
モニタリングの質は、観察の具体化と記録の客観化で決まります。
1)身体・生活環境・家族・支援体制の三視点で変化を拾う。
2)事実→解釈→対応、さらに比較を伴う記録で根拠を示す。
3)「なんとなく」は入口。観察と言葉に変換する手順を持ち、共有と優先度で動かす。
この三点を押さえれば、月一回の定期訪問は「形」から「成果」に変わります。次回の訪問から、ぜひ一項目でよいので数値と比較を加えて記録してみてください。チームの反応と、支援のスピードが変わります。