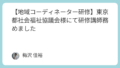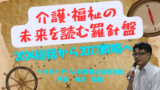(シリーズ:介護・福祉職のためのアンガーマネジメント&感情コントロール実践術
― 怒りに振り回されない支援者になるために)
介護や看護の業務では、一日の中で多くの感情に触れます。
利用者や家族への対応、職員同士の連携、思うように進まない業務……。
一度感じた怒りやモヤモヤが、退勤後まで心に残ってしまうことはありませんか?
「もう終わったことなのに、頭から離れない」「寝る前も思い出してイライラする」――。
この“ネガティブ反芻(はんすう)”を放置すると、怒りが慢性化し、心身の疲労が溜まってしまいます。
今回は、怒りを長引かせない“切り替え”の習慣をテーマに、現場でも実践しやすい方法をご紹介します。
1.反芻をやめるマインドセットとセルフトーク
怒りを長引かせる一番の原因は、「あの時こうすればよかった」「なんであんなことを言われたんだろう」と、何度も心の中で再生してしまう反芻思考です。
この思考から抜け出すには、次のような ‶セルフトーク(自分への声かけ)”を活用します。
- 「いまは過去ではなく“今”に戻ろう」
- 「事実は変えられないけれど、気持ちは切り替えられる」
- 「この経験から何を学べるだろう」
これらの言葉は、自分を責めるのではなく、怒りを“観察する側”に立つ練習になります。
怒りの渦の中にいるとき、人は「怒ってはいけない」と思いがちですが、感情を否定する必要はありません。
「いま、自分は怒っているな」と気づくだけで、怒りは少しずつ落ち着いていきます。
2.“切り替え”を助ける行動ルーティン
気持ちの切り替えには、体を動かす・場を変えるといった「行動のスイッチ」も効果的です。
仕事の後、怒りや疲れをそのまま家に持ち帰らないよう、‶リセットの儀式(ルーティン)”を決めておきましょう。
退勤後のリセットルーティン例
- 施設を出る前に深呼吸を3回
- 制服を脱ぐ瞬間に「仕事モード終了」と口に出す
- 家に帰る途中でお気に入りの音楽を聴く
- 電車通勤の場合は、1駅手前で降りて歩いてから帰る
- 車で通勤の場合は、「私ってすごい!頑張ってる!」と大きな声で自分を褒めてみる
- 帰宅後にお風呂で「今日の嫌なことを流す」イメージを持つ
こうした“区切り”が、脳に「もう終わったこと」と伝えるサインになります。
また、趣味や運動を取り入れることも、感情をうまくデトックスする方法です。
感情をほぐす活動例
- 軽いストレッチやウォーキング
- ガーデニングや手芸などの“手を動かす趣味”
- お笑い動画やラジオを聴いて笑う時間をつくる
重要なのは、「怒りを消す」ではなく、「怒りを抱えたままでも次に進む」こと。
怒りを無理に抑え込むのではなく、自然に薄れていく流れを作るのがプロの感情コントロールです。
小まとめ
- 怒りを長引かせるのは「※反芻思考」
- 自分に優しいセルフトークで“今”に意識を戻す。「いま、ココ!」が大事です。
- 行動ルーティンを作って気持ちを切り替える
- 趣味や運動は感情デトックスの最強ツール
介護や看護の仕事では、感情を完全に消すことはできません。
だからこそ、「切り替えの習慣」を身につけることで、自分の心を守り、支援の質も安定していきます。
小さな習慣の積み重ねが、怒りをためない職場づくりへの第一歩になります。
※反芻思考…ネガティブな出来事を何度も思い返しては落ち込むという行動のこと!
👉 関連リンク(参考)
- 厚生労働省「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」
https://kokoro.mhlw.go.jp/