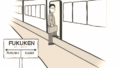介護・福祉の現場で働く皆さん、こんにちは。
前回は「怒りの正体」についてお伝えしました。
怒りの原因は“相手”や“出来事”ではなく、自分の中にある「〜べき」という価値観や欲求が裏切られたときに生まれる――そんなお話でしたね。
今回は、その「〜べき」や価値観が強く影響する、**“思考のクセ”**について深掘りします。
なぜ同じ出来事でも、人によって怒りの強さや頻度が違うのか?
そこには、日頃の考え方や受け取り方の習慣が関係しているのです。
1.なぜ“思考のクセ”が怒りを増幅させるのか?
私たちは出来事をそのまま受け取るのではなく、自分なりのフィルターを通して解釈しています。
このフィルターこそが“思考のクセ”です。
たとえば――
- 「あの人はいつも私を軽く見ているに違いない」
- 「利用者は感謝すべきだ」
- 「こういう時は○○するのが当たり前だ」
こうした思考パターンは、無意識に怒りを増幅させやすくします。
なぜなら、現実がそのパターンに沿わないとき、「裏切られた」という感覚が生まれるからです。
2.介護・福祉職に多い5つの“怒りを生む思考パターン”
① 白黒思考(オール・オア・ナッシング)
物事を「正しいか/間違いか」「やるか/やらないか」で極端に考えてしまうクセ。
例:
- 「説明を聞かない人は間違っている」
- 「挨拶をしないのは失礼だ」
→ 少しのズレでも“完全な間違い”として捉えやすく、怒りにつながります。
② 過度な期待思考
「〜すべき」「〜してくれるはず」という期待が強いクセ。
例:
- 「努力すれば必ず評価されるべき」
- 「新人でも社会人なら常識は身についているはず」
→ 現実が期待通りでないと、強い不満や苛立ちに変わります。
③ 被害者意識型思考
出来事を「自分が損をしている」「被害を受けている」と感じやすいクセ。
例:
- 「私ばかり大変な業務を押し付けられている」
- 「あの人は私にだけきつく当たる」
→ 怒りが積み重なり、関係の悪化を招きます。
④ 過去の引きずり思考
過去の出来事や失敗を何度も思い返して怒りを再燃させるクセ。
例:
- 「あの時の言い方は絶対に忘れない」
- 「以前も同じミスをされた」
→ 古い怒りがリピート再生され、心を消耗させます。
⑤ 過剰な責任感思考
「自分がやらなければ」「責任を果たさなければ」という思いが強すぎるクセ。
例:
- 「利用者の全ての要求に応えなければならない」
- 「職場の雰囲気を守るのは自分の役目だ」
→ 無理を重ねて疲弊し、些細な出来事でも爆発しやすくなります。
3.自分の“思考のクセ”を見つける方法
怒りのコントロールは、自分の思考のクセを知ることから始まります。
おすすめの方法は「怒りの記録」をつけることです。
- いつ(時間・状況)
- どこで
- 誰に対して
- 何が起きたか
- その時の気持ち(第一次感情も)
- その裏にあった“〜べき”や考え方
こうして書き出すと、自分がどんなパターンに反応しやすいかが見えてきます。
4.思考のクセに気づいたらどうする?
気づいたら、すぐに変えなくても構いません。
大事なのは、「これは自分のフィルターかもしれない」と一歩引いて見られるようになることです。
例えば――
- 白黒思考なら「中間のグレーゾーンもあるかもしれない」と考える
- 過度な期待思考なら「理想はこう。でも現実は違うこともある」と受け止める
- 被害者意識型なら「他の要因はないか?」と視野を広げる
この小さな意識の変化が、怒りの連鎖を断ち切ります。
5.介護現場で役立つ“思考クッション法”
介護・福祉の現場では、とっさの対応が求められます。
そんなときに役立つのが“思考クッション法”です。
やり方は簡単
- 「事実」と「解釈」を分ける
- 自分の考えに“別の見方”を1つ足す
例:
- 事実:「利用者が約束の時間に来なかった」
- 解釈①(怒りを生む):「約束を守らないのは失礼だ」
- 解釈②(クッション):「もしかすると体調が悪かったのかもしれない」
こうすることで、怒りが一気に高まるのを防げます。
まとめ|思考のクセを知ることが怒り対策の第一歩
怒りは、出来事そのものではなく、自分の“解釈”や“価値観”によって生まれます。
自分の思考パターンに気づき、柔軟に見直すことで、感情の波は穏やかになります。
介護・福祉職にとって、感情の安定は利用者への支援の質にも直結します。
次回は、実際に現場でできる「怒りを落ち着かせるための体の使い方・呼吸法」について解説します。
お楽しみに!