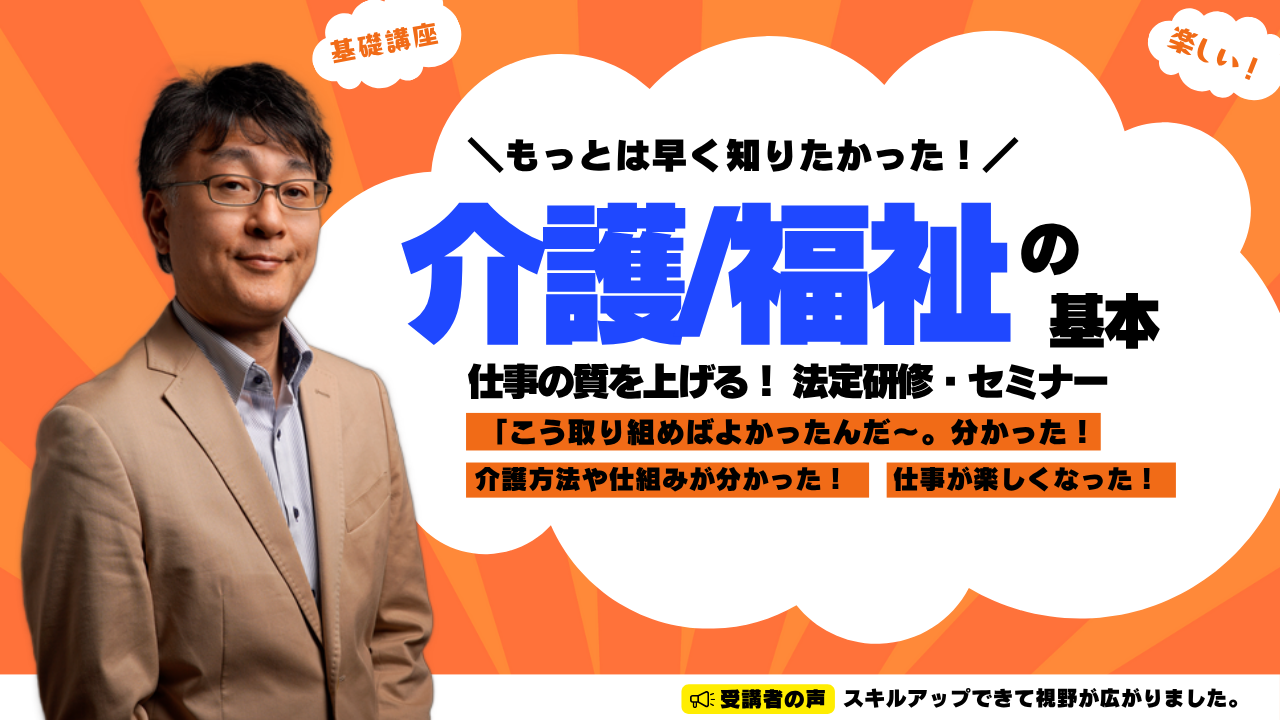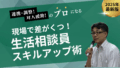― 業務でイライラしてしまった時に直ぐに実践できる感情コントロール法
はじめに:感情はコントロールできる“スキル”
介護や福祉の現場で働く私たちは、日々たくさんの感情に向き合っています。
利用者や家族、同僚との関わりのなかで、時には怒りや焦りを感じてしまうこともあります。
しかし、アンガーマネジメントは「怒らない方法」ではなく、怒りと上手につきあうための実践スキルです。
実はこのスキルにはいくつかの段階があり、それぞれを少しずつ身につけることで、
感情に飲み込まれず、冷静な判断を保つことができます。
今回はその中でも、最初のステップとなる“衝動を扱う方法”に少しだけ触れてみましょう。
1.怒りの“ピーク”をやり過ごすコツ
怒りの感情は、一瞬で高まり、そして数秒でピークを迎えます。
その短い間に、思わず強い口調で返してしまったり、表情を険しくしてしまったりします。
しかし、この数秒をやり過ごす技術を身につけることで、後悔の少ない対応が可能になります。
たとえば――
- まずは呼吸を整える。鼻から4秒吸い、口から4秒吐く。
- 「少し確認しますね」と一言残して間を取る。
- 手のひらを軽く握るなど、身体の固定動作を使って落ち着く。
こうした動作を意識するだけで、怒りの波をやり過ごすことができます。
これが“衝動のコントロール”の第一歩です。
2.心を落ち着かせる「コーピングマントラ」
感情が高ぶったとき、人の思考は狭くなりがちです。
そんなときに役立つのが、心の中で唱える「コーピングマントラ」です。
これは、自分の心を静めるための短い“おまじないの言葉”のようなものです。
たとえば――
- 「大丈夫、落ち着いて」
- 「今は判断しない」
- 「相手も困っているだけかもしれない」
短く、肯定的な言葉を自分に投げかけることで、
感情の流れが少しずつ落ち着いていきます。
呼吸+マントラの組み合わせは、最も実践的で効果的な方法の一つです。
3.現場での実践イメージ
この方法は、どんな場面で活かせるでしょうか。
いくつかの介護業務の場面を想像してみましょう。
- 食事介助の場面
利用者がなかなか口を開けず、何度も促しても拒否される。
→ そんなときこそ「一度深呼吸」「少し待とう」と心の中で唱える。
怒りが込み上げる前に、落ち着いて次の対応を考えられます。 - 家族対応の場面
面会に来た家族から、想定外のクレームや強い言葉を受けた。
→ すぐに反論せず、「いまは聴く時間」と自分に言い聞かせる。
感情を抑え込むのではなく、時間を置くことで誤解を減らせます。 - 同僚との連携場面
忙しい時間帯に声をかけても反応がなく、イライラしてしまった。
→ 「相手も今、必死で動いている」と視点を変え、6秒だけ黙る。
その間に、冷静さとチームワークを取り戻せます。
このように、“衝動のコントロール”は特別な場面だけでなく、
日常業務のなかで繰り返し活用できるスキルです。
4.感情を扱う力は、心の筋トレ
怒りをなくすことはできませんが、扱う力を鍛えることはできます。
それは筋トレと同じで、意識と反復が鍵です。
最初は難しく感じても、続けるうちに「一呼吸おく習慣」が自然と身につきます。
その結果、
- 利用者との関係が穏やかになる
- 職場の雰囲気が落ち着く
- 自分自身の疲弊が減る
といった変化が少しずつ現れてきます。
小まとめ
怒りは、誰にでも起こる自然な感情です。
しかし、その扱い方を学ぶことで、支援の質も自分の心の安定も守れます。
本研修「ストレスケアとアンガーマネジメント」では、
今回ご紹介した“入り口”だけでなく、より深い感情マネジメントの手法を体験的に学ぶことができます。
現場で“イライラを行動に移さない力”を育てたい方は、ぜひ本編の研修で体感してください。
📌 研修のご相談はこちら
研修プログラムの詳細やお見積りは、[お問い合わせフォーム]からお気軽にご連絡ください。
➡ [研修シラバス一覧ページへ]
■第1部はこちら
➡【法定研修】ストレスケアとアンガーマネジメント(第1部)
― 感情労働の時代を生き抜く介護職の“こころの整え方”