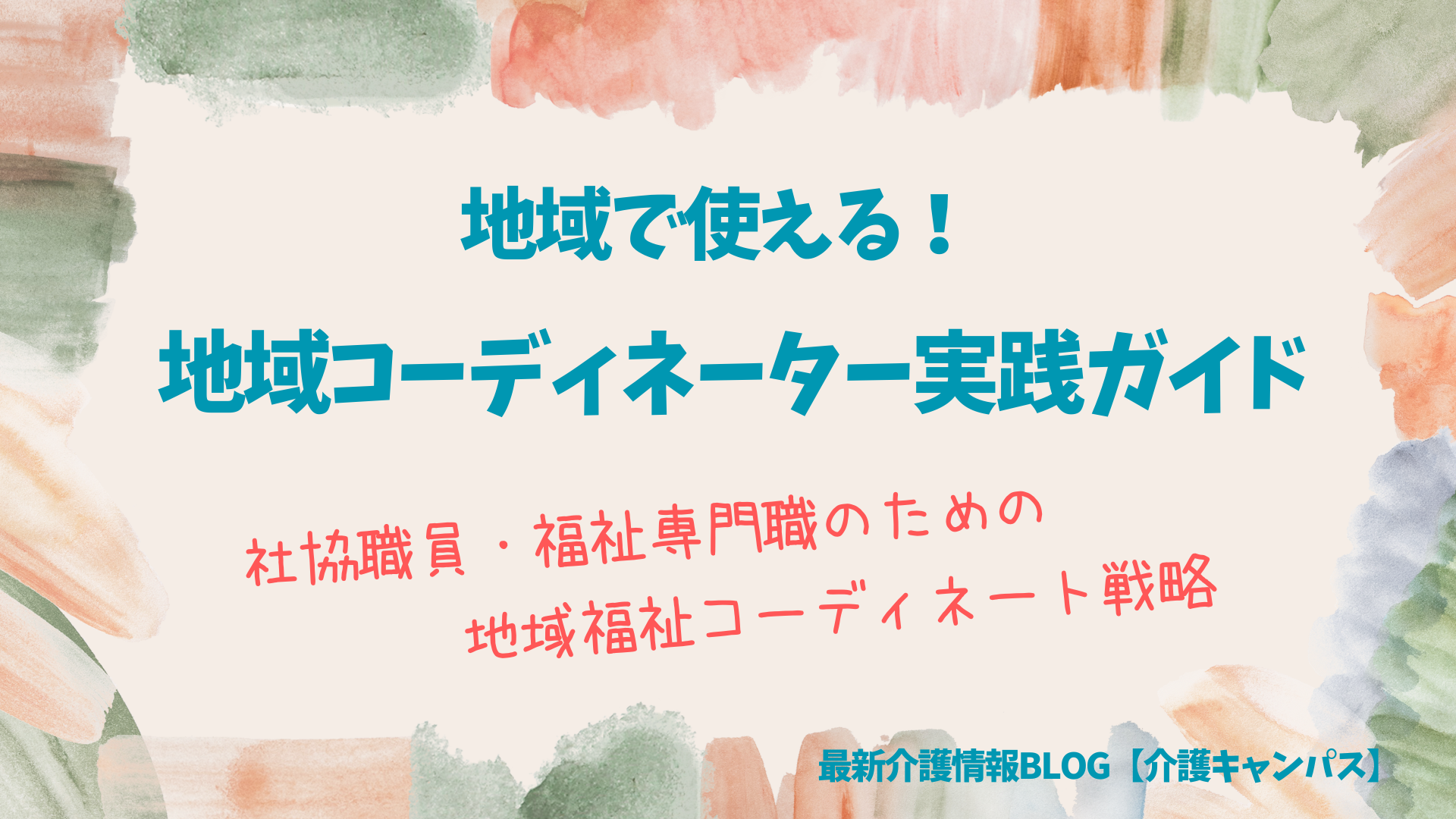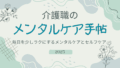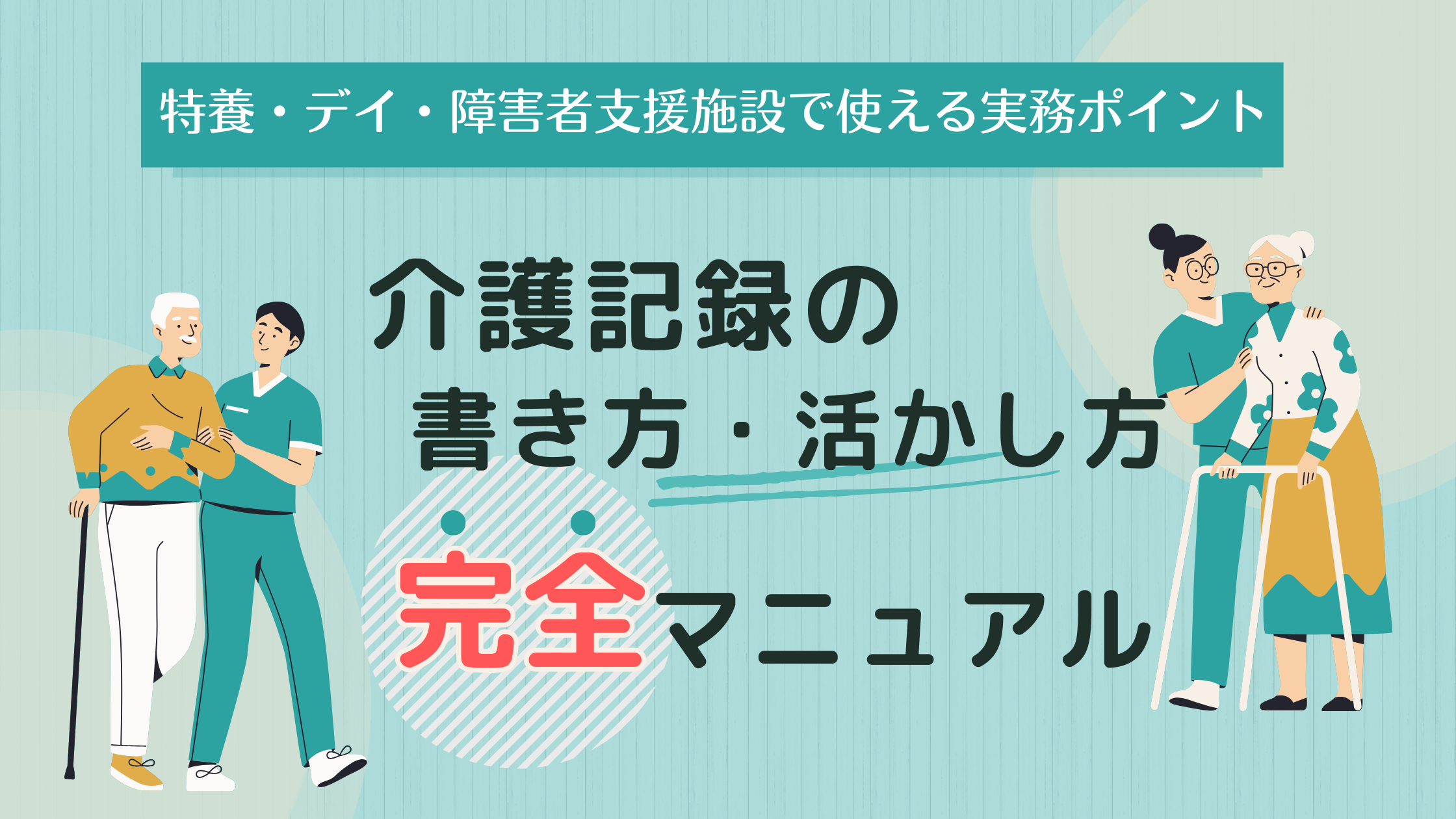(シリーズ:現場で使える!地域コーディネーター実践ガイド)
地域をつなぐ役割を担う地域コーディネーターや社協職員には、今、これまで以上に多様なスキルが求められています。
住民、行政、専門職、ボランティア団体、企業など、多様な立場の人と関わりながら「地域の課題を共に解決する力」が問われています。
今回は、これからの時代に欠かせない3つのスキル――コーディネート力・交渉力・評価力、ICT活用力、そして人材育成と自己研鑽――をやさしく具体的に解説します。
1. コーディネート力・交渉力・評価力 ―「人と人」「組織と組織」をつなぐ力
地域コーディネーターの仕事は、単に「人を紹介する」ことではありません。
それぞれの立場や目的を理解しながら、**“双方が納得できる関係性を築く”**のが真のコーディネートです。
- コーディネート力:課題の本質を整理し、最適な支援者や資源をマッチングする力。
→ 例:高齢者の買い物支援を、既存のボランティアグループと商店街の協力で仕組み化する。 - 交渉力:異なる意見や利害を持つ関係者の間に立ち、合意点を見いだす力。
→ 例:行政・地域団体・住民代表の三者調整において、目的を共通化して建設的な場を作る。 - 評価力:活動の成果を「数字」だけでなく「人の変化」でも捉える力。
→ 例:孤立していた住民が地域活動に参加するようになったことを「成果」として可視化する。
これら3つは、どれも“対話と観察”から生まれます。地域の声を丁寧に拾い、相手の立場を理解する姿勢が、最も大切な基盤です。
2. ICT活用 ― 情報を「共有」し、「見える化」する力
今、地域支援においても**ICT(情報通信技術)**の活用は欠かせません。
とくに、関係機関間での情報共有やデータ管理において、紙や口頭だけでは対応しきれない時代になっています。
たとえば、
- Googleフォームを使った活動アンケートの集計、
- Excelやスプレッドシートでの支援記録の一覧化・共有、
- Teams・Slackなどでのオンライン連携・定例ミーティング、
- ZoomやMeetによる住民説明会や研修のオンライン開催。
こうしたデジタル活用は、「効率化」ではなく「支援の質を高める」ための手段です。
ICTを使うことで、支援の重複や漏れを防ぎ、データに基づく意思決定(エビデンス・ベースド・プラクティス)が可能になります。
ただし、個人情報を扱う際はセキュリティ対策が必須です。アクセス権の制限、パスワード管理、クラウドの安全性確認を徹底し、安心できる情報共有環境を整えましょう。
3. 人材育成と自己研鑽 ― 学び続ける姿勢が地域を変える
地域の活動は「人づくり」から始まります。
どんなに優れた仕組みを作っても、それを動かす人が育たなければ続きません。
地域コーディネーター自身も、日々の業務の中で次のような姿勢を持つことが大切です。
- 学びの継続:研修・勉強会への参加、専門書や事例の定期的なインプット。
- 共有の習慣:学んだことを職場や地域で伝え、実践に活かす。
- 次世代育成:新たに地域に関わる人に役割を渡し、担い手の輪を広げる。
「自分だけで抱え込まない」「誰かと一緒に成長する」――。
これこそが、地域を支える力を持続させるエネルギーです。
コーディネーターが学びを止めなければ、地域の支援力は確実に強くなります。
小まとめ
これからの地域コーディネーターには、人と人をつなぐ力、ICTを活かす力、学び続ける力が欠かせません。
制度や仕組みの変化が早い今こそ、「現場で起きていることを見つめ、改善していく姿勢」が最も価値あるスキルです。
地域の支援は、あなたの一歩から始まります。
明日のつながりをつくるために、今日の対話と実践を重ねていきましょう。
外部リンク(厚生労働省)
- 包括的な支援体制ガイドブック(重層的支援を含む実践ガイド・2024年版)
地域コーディネートとICT活用、人材育成の最新方針を確認できます。
👉 https://www.mhlw.go.jp/content/houkatsuteki_guidebook.pdf