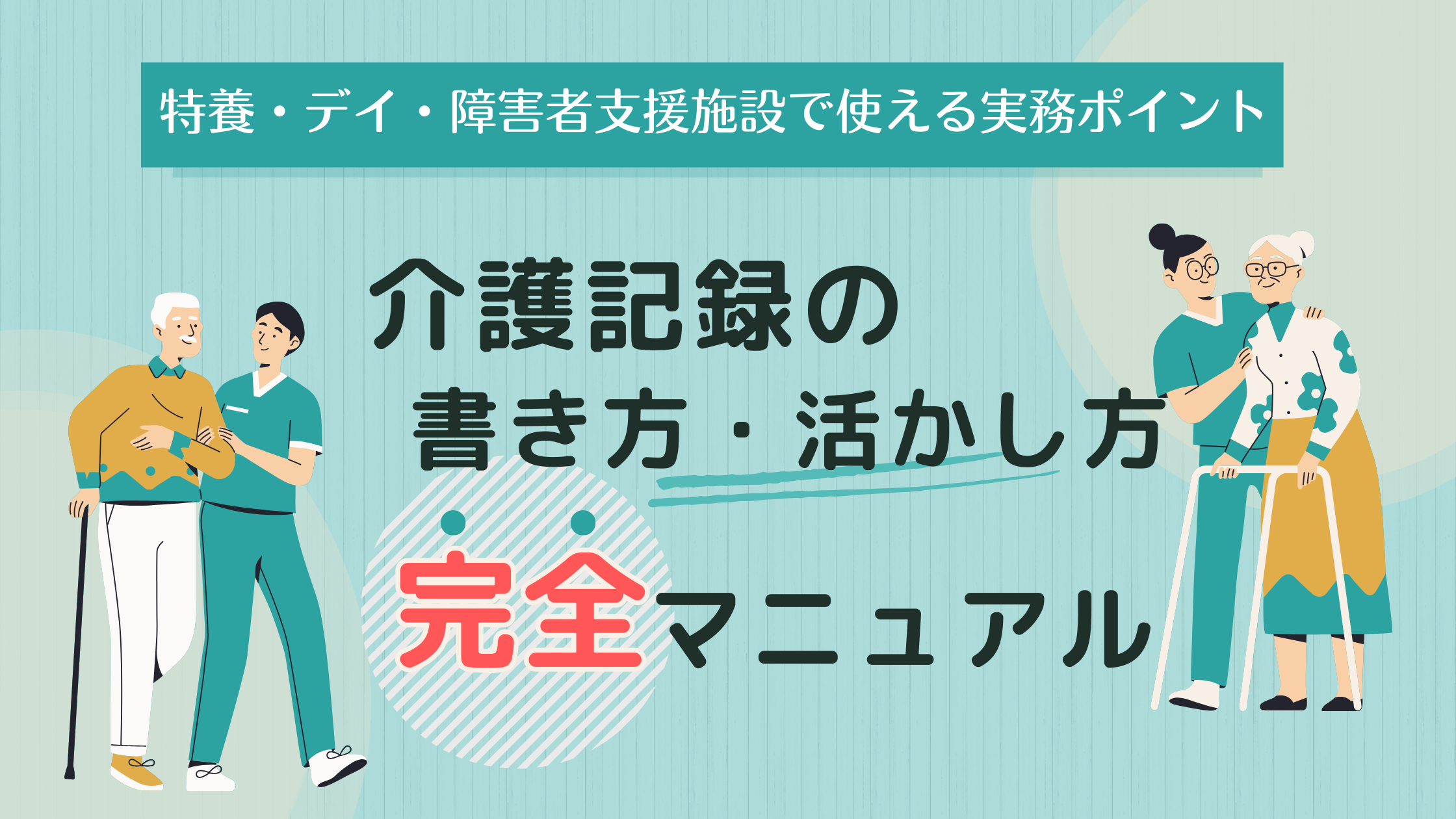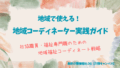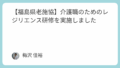家族や後見人とのやり取りは、信頼関係を支える大切な要素です。記録では「誰が」「どこで」「何を」「どう伝え、どう対応したか」を短く・正確に残します。推測や感情的な表現は避け、事実を中心に書くことがポイントです。介護記録は未来への道しるべ(介護の方向性を知るための指標のようなもの)です。
1.家族とのやり取り記録の基本と文例
●記録の目的
- 情報をチームで共有する
- 合意内容や対応履歴を明確に残す
- トラブル(言った・言わない)を防ぐ
●書き方の基本
- 日時・場所・手段(電話・面談など)
- 相手の氏名と続柄
- 要点(要望・相談・苦情の内容)
- 職員の対応と説明内容
- 結果(合意・保留)
- 共有先・次回対応
●短文の文例
6/10 15:00 面談室。A様長女B様より「昼食後の様子を知りたい」と要望あり。週報と体調変化時のみ当日連絡で説明しご了承をいただいた。本件の看護師・栄養士に連絡。
6/14 11:30 電話。C様次男D様より「洗濯代の内訳を明記してほしい」と要望あり。翌月から内訳追加で対応する旨を伝え了承を得た。本件を事務へ連絡。
→ 長文にせず、主語(誰が)+要点+対応+結果の順に一行でまとめます。
2.感情的なやり取りの客観的な書き方
●基本ルール
- 「怒っていた」「機嫌が悪い」ではなく、事実を描く(声の大きさ・話速・表情など)
- 「原因」や「推測」は書かない
- 発言は短く「」で引用する
●短文の文例
6/12 17:00 面談室。E様長男F様より「連絡が遅い」と大きめの声で要望あり。過去3日の記録を提示し、謝罪した。今後は17時までに連絡すると説明。了承あり。
6/18 9:10 電話。G様妻H様より「毎食後に電話を」と要望あり。体制上困難と説明し、週報のみの対応で提案。納得していただく。
→ 感情を「怒鳴る」「クレーム」ではなく、“声の大きさ”や“表現の実際”で残すのが正しい記録です。
3.障害者支援施設での保護者・後見人対応の記録ポイント
- 本人の意思表示手段(カード・絵・端末)を活用し、選択内容を記録
- 同意者(本人・保護者・後見人)の氏名と関係を明記
- 合理的配慮(環境調整・手順変更)を具体的に書く
- 情報共有範囲(学校・医療機関など)を限定して記載
●短文の文例
6/20 16:00 面談室。I様母J様より「タグの刺激が気になる」と相談あり。タグを内側に折り柔らかい布を当てる対応でご納得いただく。J様より口頭同意、署名済。生活支援員・学校人へ共有する。
6/25 10:30 電話。後見人K様へ皮膚科受診を説明。記録・写真をメールで送付し同意取得。7/3受診予定。看護・送迎担当へ共有する。
→ 重要なのは、誰が同意したか・どのように確認したかを短く明確に書くことです。
小まとめ
- 主語(誰が)を省かず、事実を短文で記す
- 要点→対応→結果→共有先の順に一行でまとめる
- 感情表現ではなく、観察事実で書く
- 障害者施設では、本人の意思・同意・配慮を明記
限られた時間でも、「正確な一行」は次の支援につながります。
記録は未来への道しるべです。