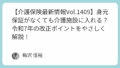介護・福祉の現場で日々奮闘されている皆さん、こんにちは。
このたび新たに、【アンガーマネジメント】をテーマとした連載をスタートします。
「アンガーマネジメントって、聞いたことはあるけど詳しくは知らない」
「怒っちゃいけないと思ってるけど、現場じゃ限界もある…」
そんな方のために、まずは“基本のキ”として「アンガーマネジメントとは何か?」を、わかりやすく解説します。
怒りの感情とうまく付き合うことは、介護職のセルフケアとしても、職場の人間関係を円滑にするうえでも重要なスキルです。
ぜひご一読ください。
1.アンガーマネジメントとは? 〜怒らない技術、ではありません〜
「アンガーマネジメント(Anger Management)」とは、“怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング”のこと。
1970年代にアメリカで生まれ、現在では教育、企業、医療福祉など多くの分野で活用されています。
ここで大切なのは、「怒ってはいけない」ではなく、「怒りをどう扱うか」という視点です。
怒りは、人間にとって自然な感情であり、完全に無くすことはできません。
問題なのは、怒りを“爆発させてしまう”ことや、“ため込んでしまう”ことによって、人間関係や心身に悪影響を及ぼすことです。
アンガーマネジメントは、怒りを我慢することではなく、「冷静に、自分の気持ちを伝える技術」を身につける手段なのです。
2.なぜ介護・福祉職にとって必要なのか?
介護・福祉の現場では、感情のコントロールが常に求められます。
- 認知症の利用者から暴言や拒否がある
- ご家族から無理な要求やクレームを受ける
- 同僚や上司との連携がうまくいかない
こうしたストレスフルな場面に日常的に直面するなかで、怒りや苛立ちがふと顔を出すことは誰にでもあります。
しかし、怒りに任せて反応してしまうと、支援関係が崩れたり、信頼を損ねたりするリスクがあります。
アンガーマネジメントを学ぶことで、感情に流されずに自分をコントロールし、対人関係においても冷静に対応できるようになります。
それは、職場の雰囲気を良くするだけでなく、自分自身を守るセルフケアにもなるのです。
3.怒りの“正体”とは?〜感情の仕組みを知ろう〜
「〇〇さんの態度に腹が立った」「あの出来事が許せない」と思うことはありませんか?
しかし、アンガーマネジメントでは、怒りの原因を「誰か」や「出来事」に求めるのではなく、自分の“内側”にあると考えます。
怒りの正体は、「〜すべき」「〜であるべき」といった自分の中の“価値観”や“期待”が裏切られたときに生まれる感情です。
例えば…
- 利用者に丁寧に説明したのに「うるさい!」と返された
→ 「説明には耳を傾けるべき」という期待が裏切られた - 忙しいのに、同僚が私語していた
→ 「忙しいときは全員協力すべき」という信念に反していると感じた - 頑張ったのに、家族から感謝どころかクレームを受けた
→ 「努力は報われるべき」という思いが傷つけられた
つまり、怒りの根底には「自分はこうしてほしい」「こうあるべきだ」という“思い”があるのです。
この“思い”が裏切られたときに、怒りという形で感情が表に出てくるのです。
また、怒りは“第二感情”と呼ばれます。
その奥には「悲しみ」「不安」「焦り」「寂しさ」など、もっと繊細な“第一次感情”が隠れています。
それがうまく表現できないとき、「怒り」という強いエネルギーになって表出します。
この仕組みを知るだけでも、感情に振り回されず、自分を客観的に見つめる力が身につき始めます。
4.まずは“6秒待つ”だけでも効果あり
怒りのピークは「最初の6秒間」と言われています。
この6秒をやり過ごせば、怒りはスーッと落ち着き、冷静な判断がしやすくなります。
- 深呼吸をする
- 一度その場を離れる(トイレに行くなど)
- 「今は判断しない」と自分に言い聞かせる
この「6秒ルール」は、アンガーマネジメントの基本中の基本です。
まずはこの“ワンアクション”から始めてみましょう。
5.介護現場で使えるアンガーマネジメント3つの基本技術
① コーピングマントラ(気持ちを整える言葉)
「大丈夫」「落ち着いて」「あとで話そう」など、自分自身をなだめる“心の口ぐせ”を決めておくことで、感情の高ぶりを和らげられます。
② タイムアウト(その場を離れる)
イライラを感じたら、いったんその場を離れてクールダウンする。物理的な距離を取ることで、感情も鎮まりやすくなります。
③ 怒りの記録(トリガーを見つける)
どんなときに、どんな場面で怒りが湧いたかをメモしておくと、自分の“怒りのスイッチ(トリガー)”が見えてきます。
まとめ|怒りは「なくす」ものではなく「扱う」もの
怒りの感情は、人間にとって自然で大切なものです。
しかし、そのままぶつければ人を傷つけ、自分にもダメージを残します。
アンガーマネジメントは、怒りを否定するのではなく、「感情と上手に付き合う」技術です。
介護・福祉職にとっては、信頼される支援者であるための土台づくりにもなります。
※この記事は、日本アンガーマネジメント協会の「アンガーマネジメント・ファシリテーター」として筆者が書いたものです。
次回は、「怒りを生みやすい“思考のクセ”」について詳しくご紹介します。
引き続きご覧ください。
\この記事が役に立ったと思ったら、ブックマーク&シェアをお願いします!/