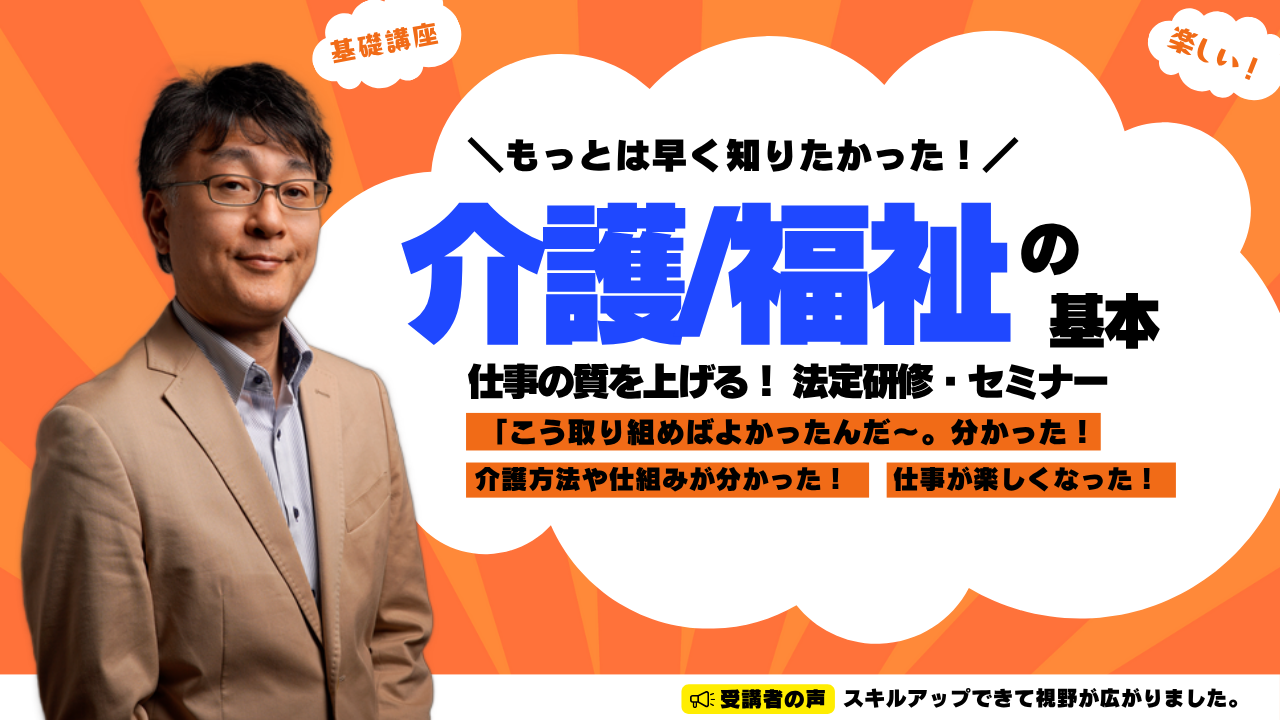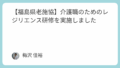―― 感情労働の時代を生き抜く介護職の“こころの整え方”
介護・障がい福祉の現場では、日々利用者の笑顔を支える一方で、強い緊張や責任感の中で働く職員が少なくありません。
こうした職業特性を心理学や社会福祉学では「感情労働」と呼んでいます。相手に安心を与えるため、いつも笑顔などの感情を働かせ表情を相手に合わせて意図的に作りながら接する一方、内心は疲労や苛立ちを抱えている――この“感情の不一致”がストレスの抱え込みになります。
1.介護現場におけるメンタルケアの必要性
介護や支援の仕事では、心身の負担だけでなく、「人との関係」そのものがストレス要因となります。
とくに現場では、
- 利用者や家族からの理不尽な要求
- シフト不規則による睡眠不足
- 同僚や上司との人間関係の軋轢
などが重なり、気づかないうちに「職業性ストレス」が蓄積していきます。
その結果、怒りっぽくなる、集中力が落ちる、欠勤やミスが増えるといった「ストレス反応」が現れます。
心理的な反応(イライラ・不安)、身体的な反応(頭痛・不眠)、行動的な反応(孤立・無言化)など、サインは人によって異なります。
重要なのは、まず「自分がどこでストレスを感じているかに気づくこと」です。
2.感情労働がもたらすストレスと燃え尽き
「燃え尽き症候群(バーンアウト)」は、対人援助職に多くみられる典型的なストレス障害です。
仕事への意欲を失い、「朝起きられない」「人に会いたくない」と感じる状態にまで至ることもあります。
仕事には頭脳労働でも肉体労働などがありますが、介護という仕事は第三の労働=「感情労働」と呼ばれ、相手の感情に寄り添う中で自身の感情を抑える必要があるため、ストレスの影響を最も受けやすい職種の一つです。
このようなストレスをため込まないためには、セルフケアが欠かせません。
リラクゼーション呼吸法、マインドフルネス、アサーション(率直で思いやりある自己表現)などの方法が有効ですが、その中の一つにアンガーマネジメントも含まれています。こうした「心の整え方」は、研修の中でも具体的な方法として紹介しています。
3.アンガーマネジメントの基礎
怒りの感情は、誰にでも自然に湧き起こるものです。
しかし、その感情を適切に扱えないと、職場トラブルや虐待の引き金にもなります。
アンガーマネジメント(Anger Management)とは、怒らない人になることではなく、
「怒る必要のあることは上手に怒り、怒る必要のないことは怒らなくて済むようにする」
という“感情との向き合い方の方法”です…。
もともとアメリカで犯罪者の再教育プログラムとして始まりましたが、今ではビジネスや教育、福祉現場にも広く応用されています。
介護職の中にも「怒ってはいけない」と思い込み、感情を抑え込みすぎてしまう人が少なくありません。
大切なのは、「怒ならいようにミルに蓋をする」ことではなく「感情コントロールしながら上手に怒る」を学ぶこと。
感情のエスカレート(爆発)を防ぎ、感情に振り回された反射をせずに自分の意見を冷静に伝える技術が、アンガーマネジメントの目的です。
4.問題となる怒りの特徴と認知のクセ
アンガーマネジメントでは、怒りが強くなる人に共通する4つの特徴を挙げています。
- 強度が高い(小さなことでも激昂する)
- 持続性がある(思い出して何度も怒る)
- 頻度が高い(些細なことでイライラ)
- 攻撃性がある(人・モノ・自分を傷つける)
さらに、怒りの根底には「~すべき」「~であるべき」という‶コアビリーフ(思い込み”が存在します。自分の内面には「こうなったらいいなという望み、こうあるべきという規範、こうなってほしくないななどの望まないこと」などさまざまな常識や価値観。考え方(思考グセ)があります。
この“理想と現実のギャップ”が裏切られた瞬間に、怒りの火花が散るのです。
つまり、怒りとは「自分の価値観が裏切られたときの反応」であり、感情そのものを悪とするのではなく、その背景を理解することが第一歩です。
第1部では、感情労働の理解と怒りの仕組みを学びました。
次回の第2部では、実際に怒りをコントロールする3つの方法を中心に、介護現場での実践的アンガーマネジメントを解説します。
🔗 研修プログラム案へのご案内
この記事は、法定研修「ストレスケアとアンガーマネジメント」のダイジェスト版です。
実際の研修構成や詳細内容をご覧になりたい方は、下記の紹介ページをご参照ください。
【研修紹介】ストレスケアとアンガーマネジメント
➡ [研修プログラム案はこちら]
■ 第2部はこちら
➡【法定研修】ストレスケアとアンガーマネジメント(第2部)
― 業務でイライラしてしまった時に直ぐに実践できる感情コントロール法