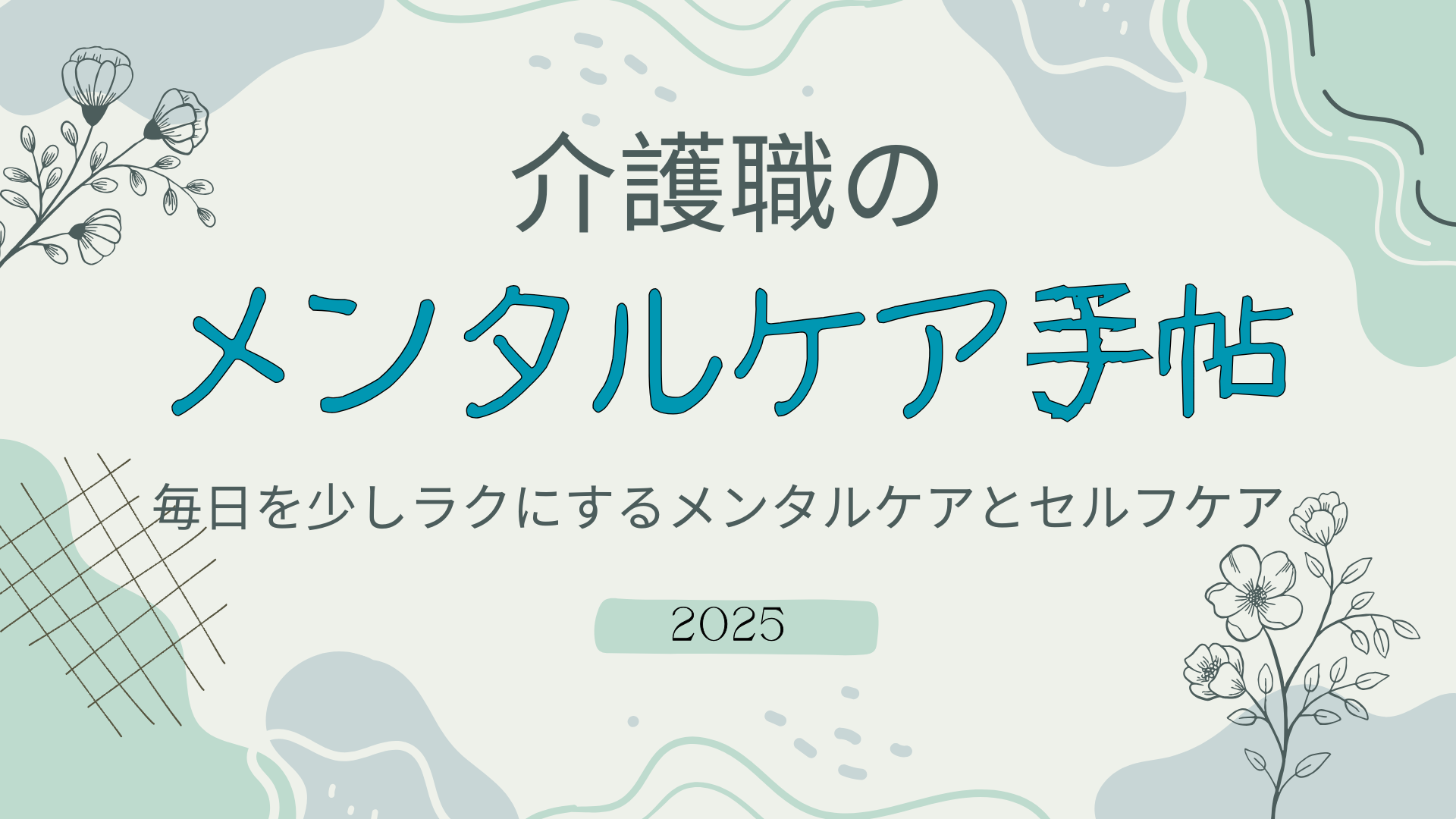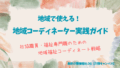― カスハラ・クレーム対応で心を守るスキル ―
「丁寧に対応しているのに、なぜか強い言葉をぶつけられる」
「理不尽だと感じても、笑顔で受け止めなければならない」
そんな場面に、日ごろの業務で戸惑うことはないでしょうか。
介護や福祉の現場では、利用者や家族の“怒り”に直面することがあります。ときにそれは、カスタマーハラスメント(カスハラ)とも呼ばれるような厳しい言動に発展することもあります。
本記事では、そうした場面で心をすり減らさないために必要な「感情距離の取り方」と「心を守る技術」を、専門的な視点からわかりやすく解説します。
1.「怒りの矢」を受け止めすぎない
介護や福祉の現場では、利用者や家族から厳しい言葉を受けることがあります。
「どうしてもっと早く来ないの?」「前の職員はもっと丁寧だった」──。
言葉の刃が心に突き刺さり、その日の疲労が何倍にも感じられることはありませんか。
まず知っておいていただきたいのは、怒りの多くは“その人自身の不安や寂しさ”の裏返しであるということです。
高齢者の方は体調や生活環境の変化に不安を抱えやすく、「思い通りにならない状況」への苛立ちを、つい身近な職員にぶつけてしまうのです。
ここで大切なのは、「相手の感情を自分の問題として抱え込まない」ことです。
相手の怒りを“矢”のように真正面から受けると、自分の心が傷つきます。
一歩引いて、「この方はいま不安なんだ」と気持ちを“理解する”方向にシフトすると、必要以上に自分を責めずに済みます。
特養の介護職員Aさんは、理不尽な叱責を受けた時、「私のせいではなく、この方が今つらいのだ」と心の中で唱えるようにしたそうです。
それだけで、怒りの矢が体に刺さらず、心の中でそっと横に流れていくような感覚が得られたといいます。
心理的距離を取ることは“冷たさ”ではなく、“自分を守るための優しさ”なのです。
2.感情の波にのまれないための技術
相手が感情的になっている時、こちらまで感情的に反応すると、状況は悪化します。
ではどうすれば、冷静さを保ちつつ対応できるのでしょうか。ここでは3つの実践スキルをご紹介します。
① まず呼吸を整える
怒りや緊張を感じた瞬間、人の呼吸は浅く速くなります。
そんな時こそ、深呼吸が“感情ブレーキ”の第一歩です。
3秒吸って、5秒でゆっくり吐く。たったこれだけで自律神経が整い、声のトーンも落ち着きます。
これは「アンガーマネジメント」でも推奨される基本スキルです。
② 言葉を“反射”で返さない
強い言葉を浴びせられると、つい言い返したくなるものです。
しかし感情的な反応は火に油を注ぐ結果になりかねません。
一呼吸おいて、「そう感じられたのですね」「ご不安なお気持ち、わかります」と相手の感情を受け止める言葉を返しましょう。
これは「アクティブリスニング(傾聴)」の基本です。受け止めたあと、落ち着いた声で事実を伝えると、相手の怒りは徐々に鎮まっていきます。
③ 自分の限界を超えそうな時は“共有”する
どんなにスキルを磨いても、人間ですから心が揺れることはあります。
対応が難しい時は、上司やチームに早めに相談・共有しましょう。
「一人で抱え込まないこと」も、立派なメンタルケアです。
特にカスタマーハラスメント(カスハラ)のように、人格を否定する言動が繰り返される場合は、速やかに報告・記録を行い、組織として対応することが重要です。
小まとめ
利用者や家族の怒りを「個人攻撃」として受け止めると、心が傷つき、やがて燃え尽きてしまいます。
一方で、「この方はいま不安なのだ」と客観的に見つめ、呼吸・傾聴・共有の3つを意識することで、介護職自身のメンタルケアが実現します。
怒りの矢を避けるのではなく、そっと受け流す。
その姿勢が、あなた自身を守り、そして利用者の尊厳を守ることにもつながります。
付記:自治体による介護職向けカスハラ相談窓口
介護や福祉の現場で発生するカスタマーハラスメント(カスハラ)への対応を支援するため、
一部の自治体では、介護職員や事業所向けの専門相談窓口を設置しています。
相談対象・受付時間・相談方法などは自治体により異なります。
最新情報は、以下の各自治体公式サイトでご確認ください。
■ 東京都
東京都介護職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口(東京都福祉局)
■ 神奈川県(川崎市)
川崎市 介護・障害福祉サービス事業所向けカスタマーハラスメント相談窓口
■ 千葉県
千葉県 介護事業者向けカスタマーハラスメント無料法律相談窓口
■ 大阪府
大阪府 介護事業者・従事者向けカスタマーハラスメント相談窓口
■ 兵庫県
兵庫県 訪問看護・訪問介護職員の暴力等お困り相談「ひょうご」
■ 岡山県
岡山県 介護職員安全確保・離職防止支援事業(ハラスメント等相談)
ご利用にあたって
- 相談対象・受付時間・連絡先などの詳細は、各リンク先の自治体公式サイトをご確認ください。
- 相談内容によっては、弁護士相談や事業所支援制度を案内される場合があります。
- 自治体によっては、地域の社会福祉協議会や介護人材センターでも独自の相談窓口を設けています。
📅 情報最終確認日:2025年10月21日現在
(今後の制度改正や連絡先変更等にご注意ください)