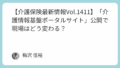ケアプランを作成するときに欠かせないのが、サービス担当者会議(担会)です。
しかし、業務が多忙になってくると・・・「形式的に開くだけになっていないか?」
「利用者や家族が本音を言えずに終わってしまっていないか?」
そんな悩みを持つケアマネも少なくありません。
実はこの担会こそ、本人・家族・多職種が一堂に集まり、生活を支える仕組みを再構築できる貴重な場です。今回は、円滑に進めるための準備・進行の工夫、家族への配慮、記録方法について具体的に解説します。
1. サービス担当者会議の役割と重要性
居宅ケアマネジャーにとってサービス担当者会議は、ケアプランの妥当性を検証し、関係者の意見を整理・合意形成する場です。制度上も、初回プランや大幅変更時の必須手続きとされており、形だけで終わらせるのではなく、実効性ある会議にする必要があります。
2. 準備の要点と進行時の工夫
事前準備
- 参加者の調整:利用者・家族、主治医、介護サービス事業者を早めに調整。オンライン併用も検討。
- 資料準備:アセスメント結果や暫定プラン、直近のモニタリング内容を簡潔に整理。
- 進行シナリオ作成:優先順位の高い課題から話し合うように段取りを考える。
進行時の工夫
- 利用者・家族の声を冒頭で取り上げる:「まず○○さんのお気持ちを伺います」と安心感を与える。
- 専門用語を避ける:家族も理解できる平易な言葉で説明する。
- 論点を見える化:ホワイトボードや配布資料で議題を示し、話し合いを整理する。
3. “言いたいことが言えない家族”への配慮
実際の会議では、家族が本音を言い出せないまま進んでしまうケースが少なくありません。
- 本人の前では「介護が大変」と言えない
- 事業者の前で「サービスを変えたい」と言いにくい
ケアマネの配慮例
- 事前に本音をヒアリング:会議前に電話や訪問で気持ちを聞いておく
- 発言の順番を工夫:会議冒頭で家族の意見を促すか、最後に安心して発言できる場を設ける
- 代弁者となる:「ご家族からはこういうお気持ちを伺っています」と客観的に提示
こうした工夫で、家族の不安や負担感を可視化し、サービスに反映できます。
4. 記録の簡素化と法的要件の両立
会議記録は「誰が・何を・どう発言したか」を残す必要があります。
しかし詳細に書きすぎると負担が大きくなるため、要点を整理して簡潔に記録することがポイントです。
最低限押さえるべき要件
- 発言要旨:「利用者:デイ週3回希望」「家族:送迎負担で週2回希望」「主治医:体力的に週2回が妥当」
- 合意内容:「デイサービス週2回、訪問リハ週1回追加」
- 参加者署名または出席確認:法的要件として必須
ICTや標準様式を活用すれば、簡素化しつつ法的要件を満たすことができます。
5. 実例:合意形成を導いた会議の工夫
Eさん(80代男性)。本人は「在宅を継続したい」、家族は「介護負担が限界」、主治医は「施設入所を推奨」と意見が割れていました。
ケアマネは事前に家族の本音を聞き取り、担会では「在宅継続+定期ショートステイ利用」という折衷案を提案。全員が合意し、本人の希望と家族の安心を両立できました。
まとめ
サービス担当者会議を実効性あるものにするためには、
- 事前準備と進行工夫
- 家族の声を拾い上げる配慮
- 記録の簡素化と要件遵守
この3点を意識することが、利用者・家族・多職種の合意形成につながります。担会は“形式的な儀式”ではなく、生活を支えるための協働の場です。
次回予告
次回(第5回)は、
「モニタリングで“変化”を読み取るスキル」 をテーマに解説します。
月1回のモニタリングを“形だけ”で終わらせず、利用者の小さな変化をどう拾い、ケアプラン改善につなげるのか。実務に役立つ具体的な視点をお伝えします。