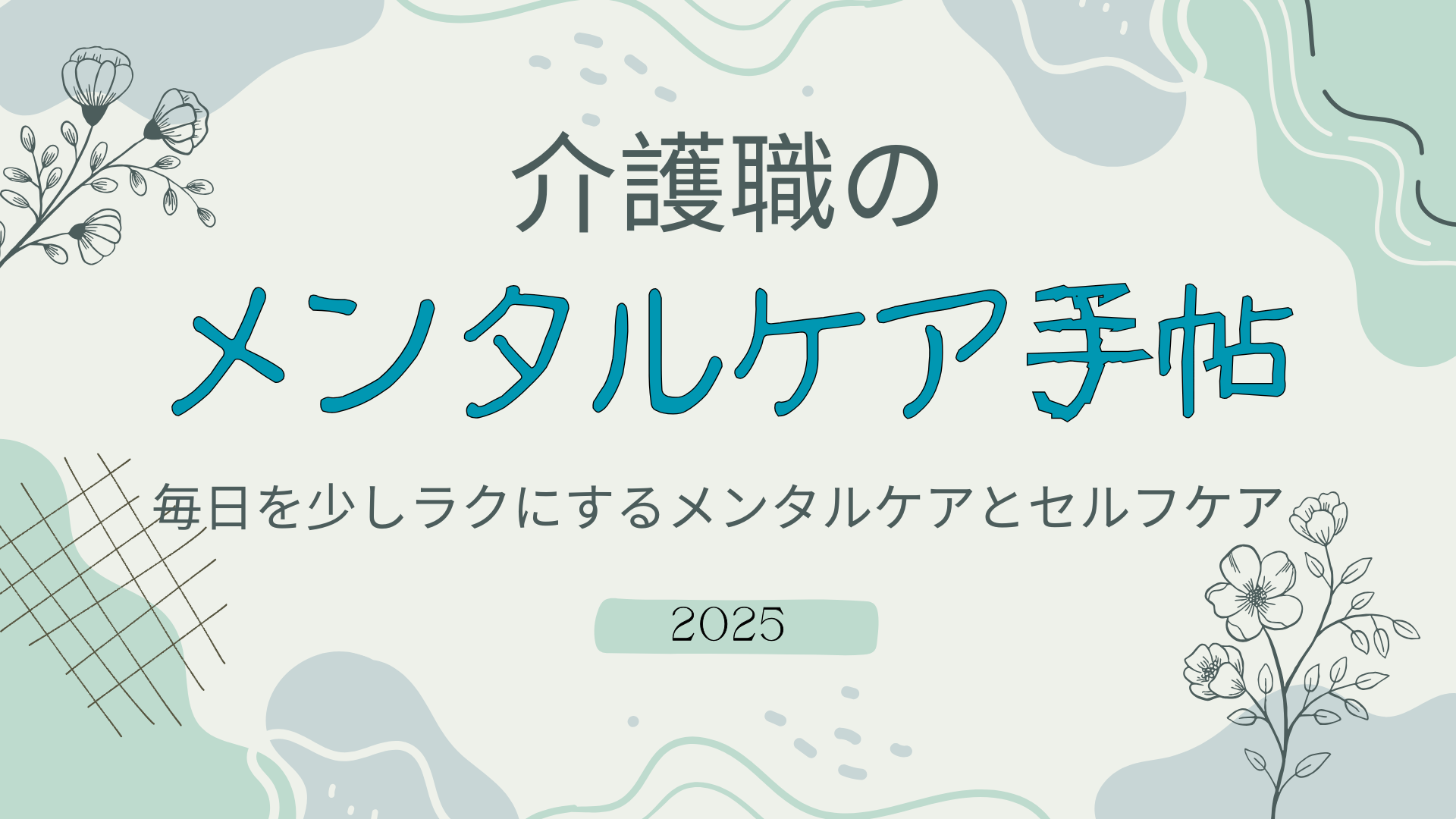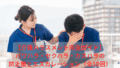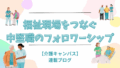― 同僚との声かけと心理的安全性のつくり方 ―
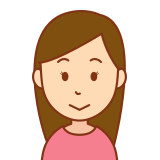
最近、職場の空気が少しピリピリしている気がするんです…
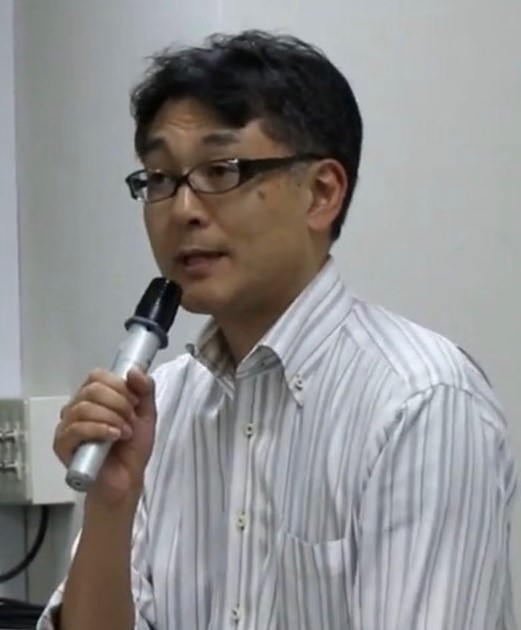
うん、みんな頑張ってるからこそ、疲れも出やすい時期だね。
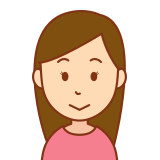
困っている同僚を見ても、声をかけづらくて…。私も誰かに相談したいけど、迷惑かなって思っちゃって…
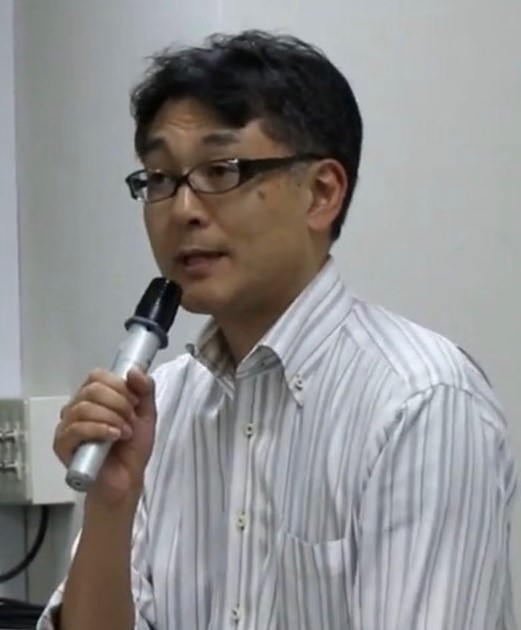
それ、まさに今の介護現場で多くの人が抱えている悩みなんだよ。
介護の仕事はチームで支え合うもの。
けれど、忙しさや人手不足が続くと、知らず知らずのうちに「個人任せ」にされてしまいます。
今回は、仲間と支え合うストレスケアをテーマに、
心理的に安心できる職場づくりのヒントを一緒に考えていきましょう。
1.心理的安全性は、毎日の声かけから始まる
1.心理的安全性は、毎日の声かけから始まる
介護の現場は、人との関わりが中心です。
利用者の感情を受け止めながら、自分の感情も整える――そんな繊細なバランスが求められます。
このように、「自分の感情をコントロールしながら人に接する仕事」を、心理学では感情労働(emotional labor)と呼びます。
アメリカの社会学者アーリー・ホックシールド氏が提唱した概念で、
「笑顔や思いやりなど、感情の表現そのものが業務の一部となる仕事」を指します。
介護士、看護師、保育士などの対人援助職がその代表的な例です。
たとえば、利用者に叱責されても笑顔で対応したり、悲しい場面でも冷静さを保ったり――
感情を表に出さず、相手を安心させることが求められます。
この“感情を使う仕事”は、人の心に深く寄り添う反面、感情エネルギーの消耗が大きいという特徴があります。
だからこそ、職場の雰囲気がぎくしゃくしたり、意見を言いづらい空気があると、
一人のストレスがチーム全体に広がってしまうのです。
そこで重要なのが、心理的安全性です。
これは「ミスや意見を伝えても否定されない」「安心して話せる」職場の雰囲気を指します。
特別な制度ではなく、日々の声かけや言葉づかいで少しずつ育てることができます。
たとえば、終礼で「今日一日、大変だったことはありますか?」と聞いてみる。
ほんの一言の対話が、仲間同士の信頼を生み出す最初の一歩になります。。
2.チームで回すストレスケア ― 小さな工夫が大きな支えになる
心理的安全性を保つには、特別な制度よりも日常の仕組みが大切です。
まずおすすめは「朝礼・終礼の2分ルール」。
朝礼では「今日の注意点を1つ」「助けてほしいことを1つ」を共有。
終礼では「ありがとう」を1言伝える。
「さっきの対応、助かりました」と伝えるだけでも、心がほぐれます。
同僚が疲れている様子を見たら、観察+提案で声をかけましょう。
「入浴介助、大変そうでしたね。私が次の配膳を代わりますよ。」
“どうしたの?”よりも“こうしましょうか?”のほうが、相手の負担を軽くします。
また、クレームやカスハラのように強い言動を受けた場合は、
「一人で抱えない」ルールをあらかじめ決めておくことが重要です。
担当者→責任者→管理者の順に報告を上げ、
必要に応じて法人や自治体の相談窓口につなぐ――その手順を明文化しておくことで、
誰か一人が背負い込むことを防げます。
さらに、朝のミーティングで体調と気分の見える化を。
「体調:○△×」「気分:↑→↓」をボードや自分の手帳に書くだけでも、
「今日は△だから無理せず補助に回ります」といった柔軟な対応ができ、
無理や事故を防ぎます。
こうした小さな習慣を積み重ねることが、チームのストレス耐性を高める第一歩です。
小まとめ
介護現場のストレスはゼロにはできません。
けれど、「相談しても大丈夫」「話しても受け止めてもらえる」と感じられる職場は、
確実に心の支えになります。
心理的安全性は、制度ではなく日々の言葉と行動から生まれるもの。
今日の終礼で「ありがとう」を一言伝える――
その小さな習慣が、あなたのチームの空気をやさしく変えていきます。