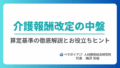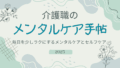居宅ケアマネジャーにとって「記録」は、単なる事務作業ではありません。
それは、支援の一貫性と専門性を可視化する“安全ネット”であり、利用者の生活を守るための大切な仕組みです。しかし、実地指導や監査では「記録の一貫性がない」「根拠が不明確」と指摘されるケースが後を絶ちません。
今回は、居宅ケアマネの主要書類の整備ポイントと、実地指導で評価される“良い記録”の書き方を整理します。
1.アセスメントから経過記録まで ― 一貫性のある記録をつなぐ
(1)アセスメントシート:支援の出発点
アセスメントは「どんな支援が必要か」を整理する最初の工程です。
重要なのは、本人の希望(主観)と課題(客観)を分けて記録することです。
たとえば、
「自分のことはできるだけ自分でやりたい」(本人)
「調理動作で包丁使用に不安あり。安全面の支援が必要」(客観)
このように主観と客観を並記することで、支援の根拠が明確になります。
また、アセスメント項目のうち「心身の状態」「生活環境」「家族の支援力」は、
後のモニタリングとつながるため、変化があった際に比較できるよう定型文ではなく具体的な表現にしておくことが大切です。
(2)居宅サービス計画書(ケアプラン):目的と手段を対応させる
ケアプランでは、長期目標・短期目標・サービス内容の対応関係が実地指導で最も見られる部分です。
目標が抽象的すぎたり、サービス内容と結びついていないと「一貫性がない」と判断されます。
例:
- ✕「安心して生活できるように支援する」
- 〇「買い物が一人でできるよう、週2回の訪問介護で外出練習を行う」
また、記録の日付・署名・作成年月の抜け漏れは、加算減算の対象となることがあります。
最新の様式(令和6年度改定版)を使用しているかも必ず確認しましょう。
(3)経過記録:プロセスを“ストーリー”で残す
経過記録は、「その時どう対応したか」だけでなく、
‶なぜそう判断したのか(支援意図)”を添えることで、専門職としての考察を示すことができます。
たとえば、
「デイサービス休みたいとの訴えあり → 家族に確認し、疲労感が続いていることを確認。次回訪問時に受診勧奨予定」
このように「情報」「判断」「対応」を一文の中で明確にすることが、実地指導で高く評価される書き方です。
単なる事実羅列ではなく、「思考の流れ」がわかる記録を意識しましょう。
2.実地指導・監査でよくある“NG記録”とその改善例
(1)テンプレート依存の記録
同じ文章が複数人に繰り返されていると、「実態を反映していない」と見なされます。
→ 改善策:定型文に「利用者個別の状態」や「支援内容」を一文加える。
(2)主語の欠落
「歩行不安定」「服薬忘れ多い」など、誰が観察したのかが不明な記録。
→ 改善策:「〇〇訪問時にケアマネが確認」「家族より聴取」など情報源を明示。
(3)結果だけを記す記録
「訪問した」「説明した」で終わる記録は、行動の意図が伝わりません。
→ 改善策:「介護保険負担割合証更新の必要を説明し、次回申請同行予定」など支援の方向性を記す。
(4)修正履歴の欠落
訂正や追記の際、修正日・署名がないと「改ざん」とみなされることがあります。
→ 改善策:日付・理由・署名を明記し、追記扱いで残す(削除・上書きはNG)。
小まとめ ― “書くこと”は責任と信頼の証
記録は「自分を守る盾」であり、「支援の質を伝える鏡」です。
実地指導で求められるのは“完璧な文書”ではなく、支援の根拠と流れが伝わる一貫性のある記録です。
新人ケアマネほど、最初から丁寧に「なぜ」「どうして」を書く習慣をつけておくと、
後の監査や引き継ぎ時に大きな安心につながります。
書くことは、“信頼されるケアマネ”への第一歩なのです。