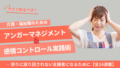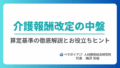「LIFE(科学的介護情報システム)は提出するもの」──そう思っていませんか?
多くの介護事業所では、LIFEの入力や報告を“義務”として捉え、日々の記録や業務の延長線上で処理しています。しかし、LIFEの本来の目的は「データをケア改善に生かすこと」にあります。
令和9(2027)年度介護報酬改定を見据え、国は「科学的介護」と「生産性向上」を両輪として位置づけています。LIFEを上手に活用できる事業所ほど、成果が見える経営へと近づく時代です。
今回は、LIFEを‶提出″から‶活用″へと変えるための実践ステップと、現場で数値をケアに生かす運用のコツをやさしく解説します。
1.LIFEを‶提出″から‶活用″へ転換する方法
LIFE(科学的介護情報システム)は、データを提出して終える仕組みではありません。国は、提出とフィードバックを往復させることで、計画見直しやケアの質向上につなげる運用を想定しています。つまり、皆さまの法人がデータを受け取り、比較し、毎月の会議で改善行動に落とすことで初めて価値が生まれます。
実務では、まずフィードバックの閲覧と配布を「定例化」してください。毎月、LIFEの事業所フィードバックから栄養、口腔、褥瘡リスクなど主要指標の推移を抜き出し、簡潔なグラフにして現場へ共有します。次に、数値の変化が小さい領域を「翌月の重点テーマ」に指定し、ケア計画の修正と担当割当てをその場で決めます。翌月は、修正が反映されたかどうかを同じ指標で確認し、効果を検証します。こうした小さなPDCAが、提出中心の運用から活用中心の運用へと組織文化を変えていきます。
LIFEを扱う担当者の「読み解き力」も鍵になります。数値の上げ下げを追うだけでは不十分で、全国平均とのギャップ、年齢構成、認知機能の分布といった背景を合わせて解釈し、なぜ変化が起きたのかという仮説を持って次の行動へ結び付けます。厚生労働省は「利活用の手引き」や操作マニュアルを公開しており、現場研修の教材として活用できます。
2.‶数値″をケアに反映させる現場運用のコツ
最も成果が出やすいのは、テーマを絞った「小集団レビュー」です。毎月一つの症例を選び、LIFEの該当指標と日々の記録を並べて検討します。原因仮説を立て、計画を一つ修正し、翌月の同指標で結果を確かめるという小さなサイクルを繰り返します。こうした症例ベースの議論は、データと実感を結び付け、現場の納得感を伴う改善を進めます。
評価軸は、全指標を追いかけるよりも、事業所の重点に合わせて三〜四項目に絞ると運用が安定します。通所介護であれば、栄養関連指標、口腔機能、活動性、褥瘡関連など「転びやすい領域」をKPIとして定点観測し、停滞時には具体的な改善案をその場で合意します。さらに、日々の記録様式をLIFE項目と対応させると、二重入力の回避とエビデンスの蓄積が同時に進みます。
なお、介護分野の生産性向上は「質の向上」と「職員の定着・確保」を同時に目指す観点で整理されています。データ活用による業務の見える化や情報共有の効率化は、職員の負担軽減とやりがいの向上に直結します。LIFEを中心に据えたアウトカム志向の運用は、この政策の考え方と整合します。 ●厚労省:介護分野における「生産性向上」とは?
小まとめ
LIFEは「提出義務」ではなく、皆さまの法人にとっての‶改善の羅針盤″です。フィードバックを毎月の議題に組み込み、指標を絞ったKPI運用と症例レビューで小さく回すことが、アウトカムと経営評価を結び付けます。政策が掲げる‶質の向上と職員定着″の両立にも資するため、次の定例会から始められる仕組みに落としていきましょう。