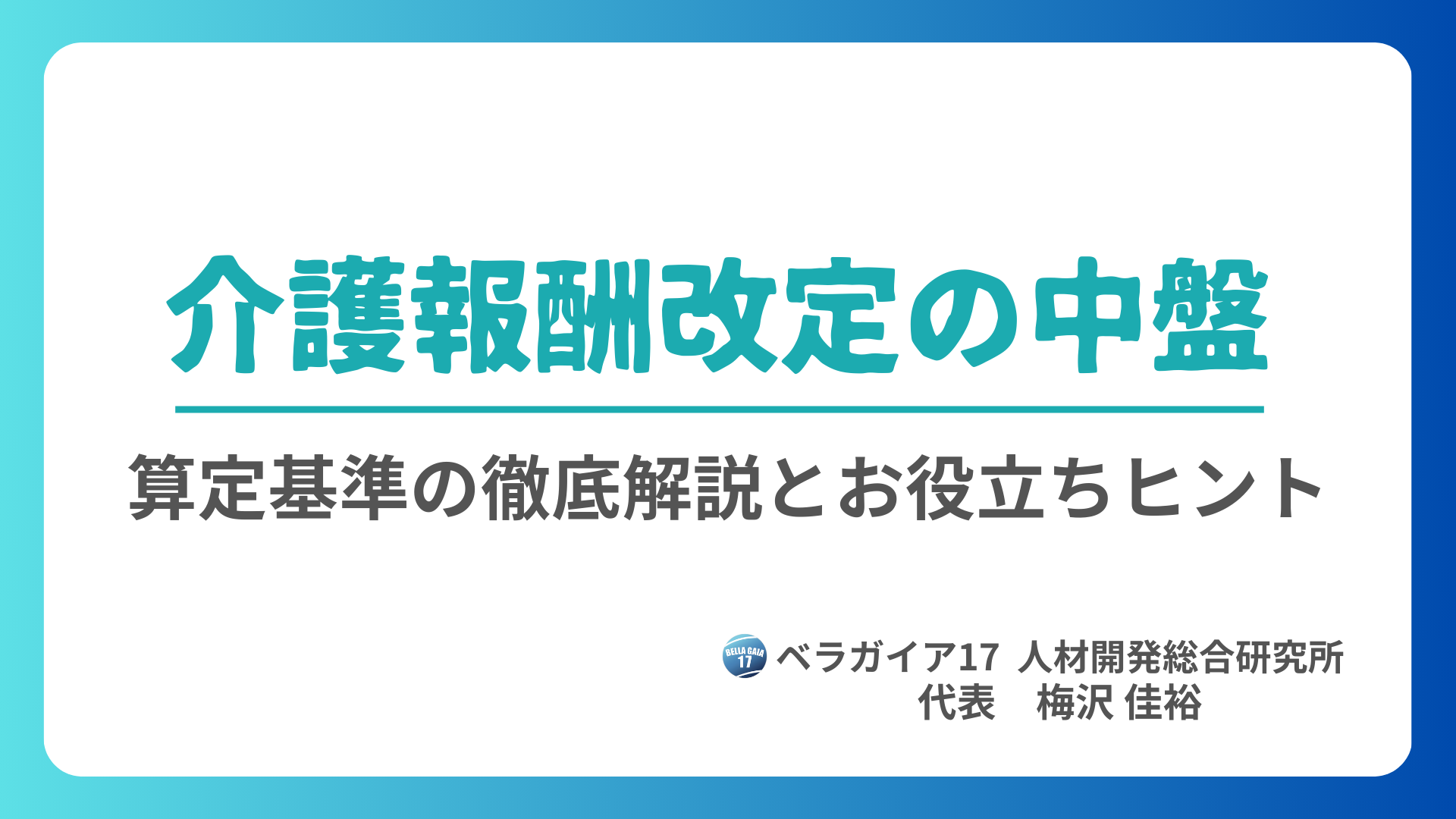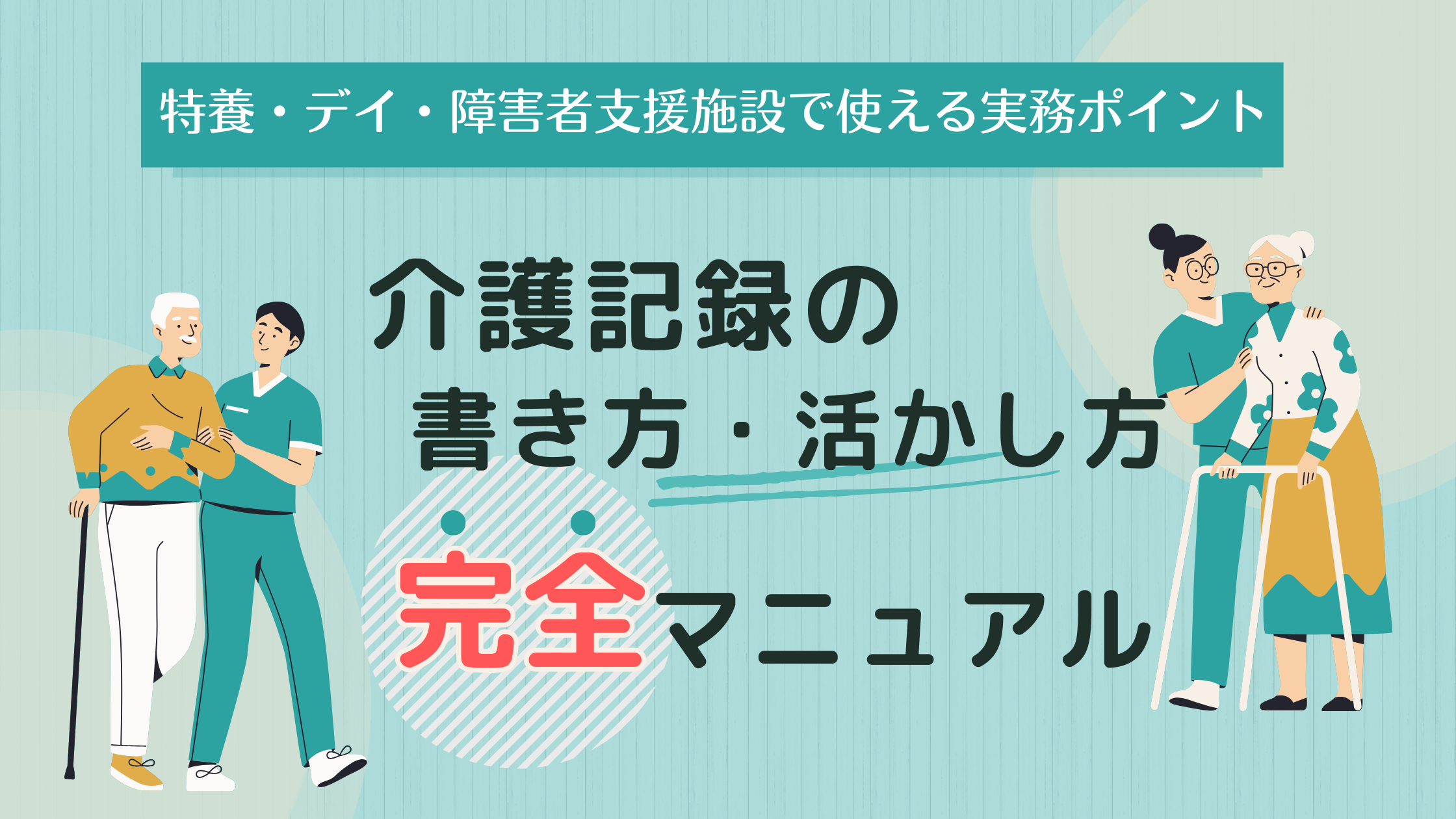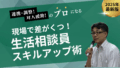1.加算Ⅰとは:介護現場の「成熟度」を示す指標
2024年度介護報酬改定で導入された「生産性向上推進体制加算」は、
介護現場における業務効率化・ケアの質向上・職員の負担軽減を総合的に評価する仕組みです。
このうち‶加算Ⅰ(100単位/月)”は、加算Ⅱ(10単位)をさらに発展させ、
「組織的に継続して改善に取り組む体制」を持つ事業所を対象としています。
加算Ⅰの対象と要件(厚生労働省告示より)
- 加算Ⅱをすでに算定していること(委員会設置・ICT導入・改善活動が機能している)
- 複数のICT機器を導入し、職員間で活用できていること(基本的に3つすべて導入すること)
- 業務改善活動を職員全体で推進していること(PDCAサイクルの定着)
- 取り組み成果をデータで検証し、外部にも発信していること
詳しくは、厚生労働省「令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について」をご参照ください。
👉 厚生労働省公式PDFはこちら
2.加算Ⅰの算定条件と現場での進め方
加算Ⅰでは、「形」よりも「中身」が問われます。
要件を満たしていても、実態が伴わないと監査で指摘されることがあります。
現場での実行力と継続性こそが、算定のカギです。
① 職員参加型の改善活動
改善活動は、管理者や委員会だけが行うものではありません。
介護職員・看護職員・調理・送迎担当など、全職種が参加できる仕組みを整えることが重要です。
- 例:「記録作業時間を15分短縮するには?」をテーマに、各職種で提案を出す。
- 月1回、ミーティングで改善案を共有・決定し、翌月に効果検証を行う。
② 外部研修・専門家の活用
厚労省は、外部専門家・研修機関の活用を推奨しています。
ICT導入研修、介護ロボットメーカーの実地指導、
または生産性向上の専門講師による改善手法研修などが該当します。
研修後は、学んだ内容を職場で共有し、改善策に落とし込むことが求められます。
③ データに基づく効果検証
加算Ⅰでは、「成果を見える化すること」が必須です。
主な評価指標として、次のようなデータを用いると効果的です。
- 記録業務時間・夜勤業務負担の変化
- 利用者満足度・転倒件数などの安全指標
- 残業時間・有給取得率の推移
- 業務支援者や機器活用による作業分担率
数値化できる部分を明示することで、
「取組の実効性」が審査や監査時に説得力を持ちます。
3.加算Ⅰの効果と組織が得られるメリット
加算Ⅰを目指すことは、単に報酬を得るためだけではありません。
それは職員の働きがい・利用者の安心・経営の安定を同時に育てる仕組みでもあります。
主なメリット
- 職員のモチベーション向上と離職防止
自分の提案が実行に移ることで、やりがいを実感。 - 経営の安定化
100単位の加算収益を、ICT投資や職員教育に再投資できる。 - 組織文化の成熟
「改善することが当たり前」のチーム文化が根づく。 - 外部評価の向上
加算Ⅰを取得している施設は、自治体・採用者・家族から信頼されやすい。
注意点
- 書面だけ整えて「実行が伴っていない」場合は、監査で不備とされる。
- 改善活動が一部職員に偏ると、全体の成果が上がらない。
- 成果のデータを取らずに感覚評価のまま終えると、証拠として認められにくい。
小まとめ:生産性向上は「制度」ではなく「文化」へ
生産性向上推進体制加算Ⅰは、介護現場が自立的に進化していくための道しるべです。
ICT導入は手段であり、最も大切なのは職員一人ひとりの参画と継続的改善です。
「生産性を上げる=ケアの質を下げる」ではありません。
むしろ、より人に寄り添える時間を生み出すための工夫が評価される時代です。
現場の努力が制度で正当に評価されるよう、
日々の改善の一歩一歩を積み重ねていきましょう。