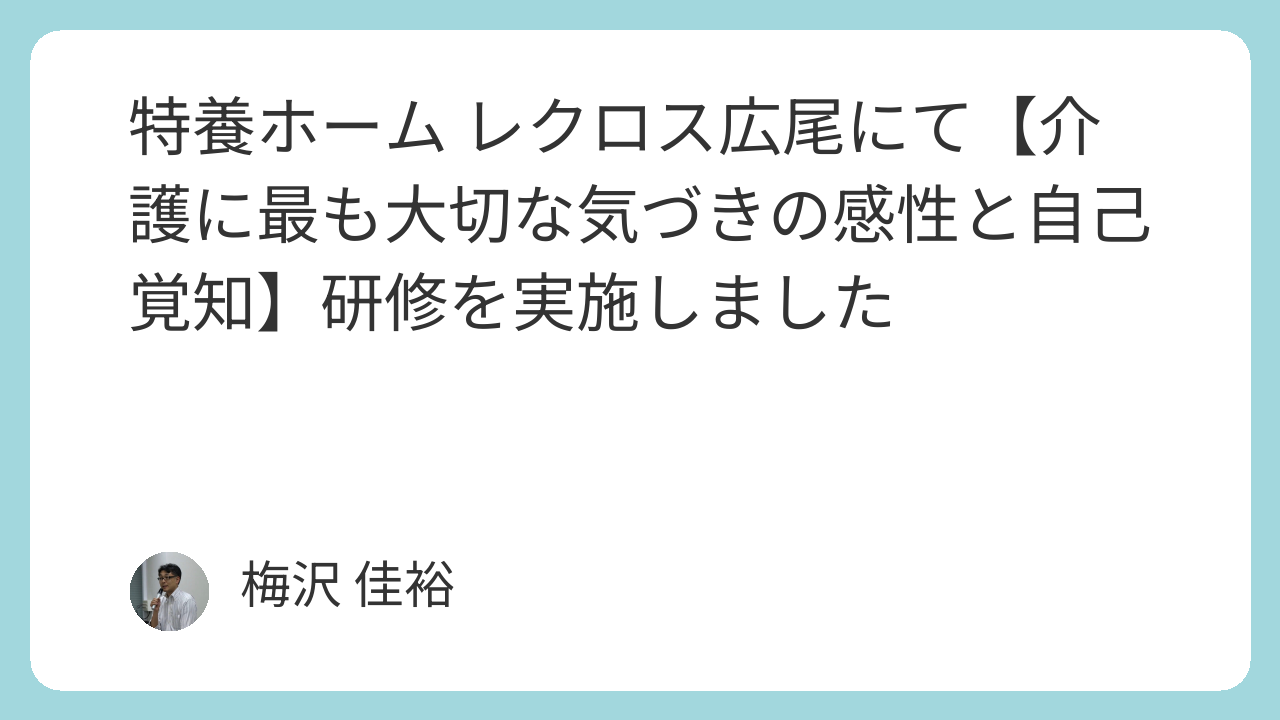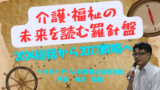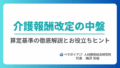皆さま こんにちは ベラガイア17の梅沢佳裕です。
「介護に最も大切な気づきの感性と自己覚知」をテーマに研修を実施|特養ホームレクロス広尾様
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.研修概要
■テーマ:介護に最も大切な気づきの感性と自己覚知
■開催日時:2025年10月(集合研修)
■研修場所:日本赤十字社総合福祉センター|特別養護老人ホーム レクロス広尾
●https://hiroo.jrc.or.jp/care_welfare.html
【研修プログラム】
- 講義①:気づきの基礎と自己覚知
- ワーク①:気づき体験の振り返り
- 講義②:気づきの感性を育てる
- ワーク②:気づきプロセスを鍛えるケーススタディ
- まとめ・振り返り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.研修の様子
今回の研修は、特別養護老人ホームレクロス広尾様の職員の皆さまを対象に行われました。参加者の方々は日々の現場で多忙な業務を担う中でも、「利用者の小さな変化に気づき、適切に対応する力を高めたい」という強い意欲を持っておられました。その姿勢が研修全体を通じて真剣な雰囲気を生み出していたのが印象的です。
最初の講義①「気づきの基礎と自己覚知」では、まず「気づきとは何か」を改めて言語化しました。利用者の表情や声のトーン、日々の行動に見られるわずかな変化を敏感に察知することが、重大な事故やトラブルを未然に防ぐ第一歩であることを確認しました。さらに、自分自身の感情や価値観に左右されて判断を誤ることがあるため、自己覚知の重要性について具体的な例を交えながらお伝えしました。参加者は、自分の「思い込み」や「先入観」が介護記録や声かけにどのように影響しているかを振り返るきっかけとなったようです。
続くワーク①「気づき体験の振り返り」では、各自が過去の経験から「気づけたこと」と「気づけなかったこと」を書き出し、グループで共有しました。「入浴を嫌がる利用者の行動の背景に、寒さや羞恥心があった」と気づいた体験や、「他の利用者と比較して気づきが遅れた」といった反省が出され、場は大変活発な意見交換となりました。
講義②「気づきの感性を育てる」では、観察力を養うための具体的な視点に基づく全人的な理解の枠組みを示しました。単に「食べない」「動かない」と記録するのではなく、「表情が曇っていた」「咀嚼が弱くなった」「声かけに反応が乏しい」といった事実を丁寧に拾い上げることの重要性を強調しました。
さらにワーク②「気づきプロセスを鍛えるケーススタディ」では、仮想事例を用い、利用者が「ため息をつく」「突然食事を拒む」「夜間に居室を徘徊する」といった場面を設定しました。参加者はその背景にある心理や身体状況を推測し、どのような声かけや支援を行うかをグループで議論しました。実際の介護現場さながらに活発な意見が交わされ、「自分だけでは思いつかない視点を他の職員から得られた」という声も多く聞かれました。
最後のまとめでは、参加者一人ひとりが「明日からできる小さな一歩」を書き出しました。「利用者の目線に立ち、気持ちを想像して声をかける」「曖昧な表現を避け、記録を具体的に残す」など、実践的で具体的な宣言が多数出されました。
今回の研修を通じて、職員の皆さまが気づきの感性と自己覚知を自分事として捉え直し、日常業務の中で活かすための視点を獲得されたことを強く感じました。私自身も、現場の皆さまの真剣なまなざしに触れ、改めて介護における「気づき」の奥深さを実感いたしました。