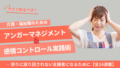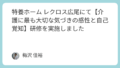1.なぜ「業務改善」が人材定着に直結するのか
‶令和9(2027)年度介護報酬改定″を前に、介護経営者が重視すべきは「人材定着」を見据えた業務改善です。処遇改善や給与引き上げは確かに必要ですが、それ以上に「毎日の仕事がやりやすい」と感じられる環境を整えることが、離職防止の決め手になります。
典型的な課題は入浴介助です。予定が毎回変動し、誰が担当するのか不明確だと、現場は混乱します。しかし、入浴日を週ごとに固定化し、担当者を明示すれば、準備やシフトの負担が減り、現場のストレスは大幅に軽減します。
また、介護記録を紙に残したあと請求システムへ再入力する二重作業は、職員にとって大きな負担です。ICTを活用して記録と請求を一体化すれば、記録業務は効率化し、同時に「入力漏れによる請求エラー」という経営リスクも防げます。
さらに、夜勤帯の巡視負担も大きな課題です。ある施設では、1時間ごとに巡回しバイタル測定を行っていましたが、見守りセンサーと自動記録システムを導入したことで必要時に重点ケアを行う形に移行できました。その結果、安全性を維持しつつ夜勤職員の疲労を減らすことに成功しました。
このように業務改善は、
- 身体介助や夜勤業務の負担軽減
- 二重作業や記録ミスの防止
- 成果の見える化によるやりがいの創出
という三つの効果をもたらし、結果として「ここで働き続けたい」という思いにつながります。業務改善は経営課題の解決策であると同時に、人材戦略の中核です。
2.ICT導入は小さな成功体験から始める
‶介護DX″という言葉を聞くと大がかりなシステム投資を想像しがちですが、実際には小さな導入と成功の積み重ねが鍵となります。
ある特養では、夜勤帯に限定して音声入力を導入しました。最初は戸惑いもありましたが、1か月後には記録時間が短縮され、残業が減少しました。デイサービスでは送迎ルートをICTで最適化したところ、走行距離が減り、担当職員の疲労が和らぎました。さらに、LIFE(科学的介護情報システム)のフィードバックを会議で共有し、栄養や口腔の改善につなげた施設もあります。小さな改善を数値とエピソードで示すことで、職員の納得感が広がり、継続した取り組みに結びつきました。
経営層に求められるのは、まず「目的を具体的に明確に発信すること」です。たとえば「記録時間を30%削減する」と掲げれば、導入の意図が明確になります。そのうえで、まずは小規模に試し、成果を共有し、現場の「これならやれる」という手応えを醸成してください。
小まとめ
生産性向上は、単なる効率化ではなく「職員が安心して働き続けられる環境」を整える経営戦略です。入浴や夜勤といった日常業務の改善から始め、ICT導入で小さな成功体験を積み重ねてください。それが文化として根づけば、‶令和9(2027)年度介護報酬改定″を追い風に変えることができます。