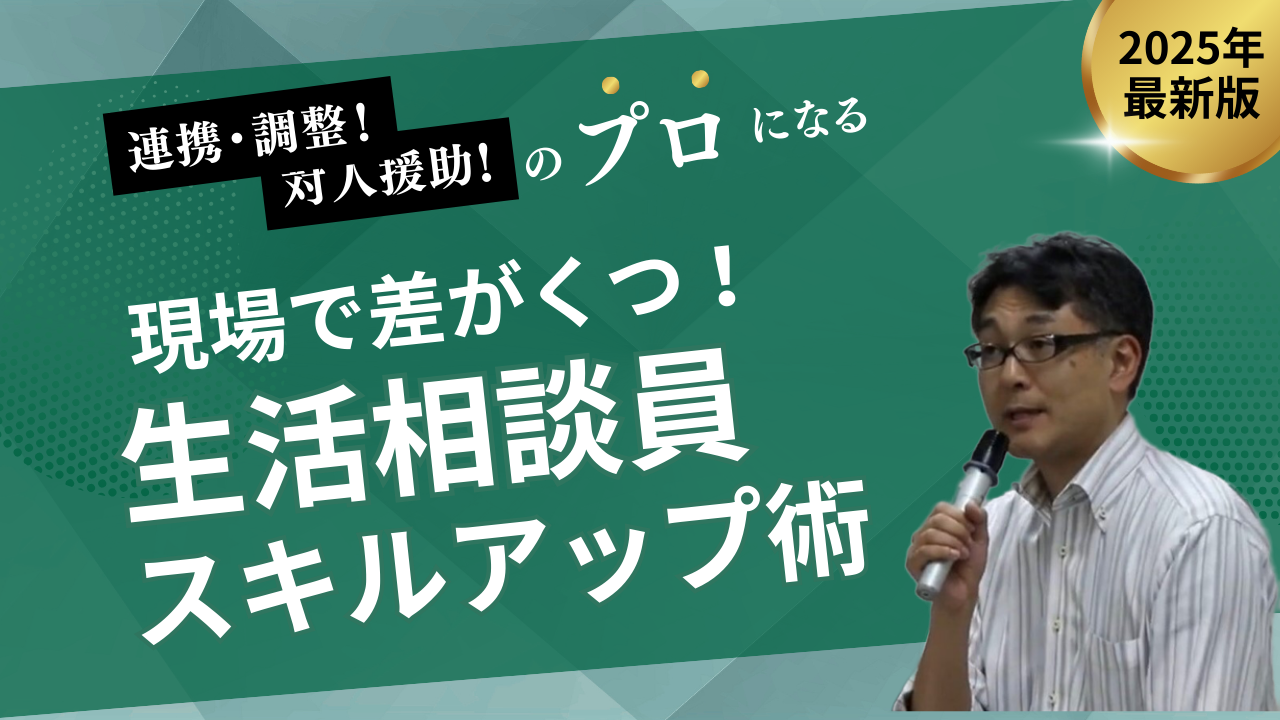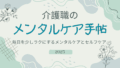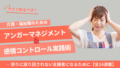介護施設で働く生活相談員にとって、日々直面するのは「職員との意見の相違」や「家族との見解の違い」です。特養ホーム、デイサービス、老健、有料老人ホームなど、どの場でも起こり得る現象です。しかし、この板挟みの場面こそ、相談員の相談援助職としての力量が問われる重要な機会です。
1.職員との意見の違いにどう向き合うか
介護職や看護職は、それぞれの専門的判断に基づき日常支援を行っています。たとえば「外出を希望する利用者に対し、転倒リスクがあるから控えるべき」と介護職が主張する一方で、「本人の‶生活の質(QOL)”を大切にする観点から外出の機会を設けたい」と考える場面は珍しくありません。
このようなときに生活相談員に求められるのは、調整と合意形成を進める姿勢です。
- アセスメントの共有:本人の身体状況、既往歴、認知症の有無などを整理し、事実を基盤に職員間で共通理解を図る
- 視点の整理:リスクを重視する立場と本人の希望を重視する立場、それぞれの妥当性を丁寧に言語化する
- 実現可能な工夫の提示:全面禁止か全面許可ではなく、「短時間・付き添い付き・見守り体制強化」など現実的な選択肢を示す
ある施設では、入居者の「買い物に行きたい」という希望に対し、介護職は「外出は危険」と反対しました。しかし相談員が「買い物という行為自体が重要なのではなく“選ぶ体験”が大切」だと捉え直し、施設内での模擬ショッピングや短時間の近隣散歩を提案しました。結果として、本人は満足感を得られ、職員の安全面への懸念も軽減されました。ここで示されたのは、相談員が多職種間の視点を整理し、本人の意向を基盤に合意形成を進める専門職であるということです。
2.家族とのすれ違いを信頼に変えるプロセス
家族との関わりにおいても相談員の力量が試されます。本人が「好物を食べたい」と望む一方で、家族は「誤嚥や糖尿病の悪化が心配」と反対することはよくあります。ここで重要なのは、どちらかの立場に立つのではなく、本人の意思を中心に家族の不安も受け止める姿勢です。
調整を進める際の基本は次の5段階です。
- 傾聴:本人と家族双方の思いを否定せず聴き取り、感情を受け止める
- 事実の共有:健康状態や事故歴など客観的データを整理して可視化する
- 価値とリスクの並列化:本人の望む活動と想定されるリスクを同じテーブルで検討する
- 代替案の検討:全面否定か全面承認かの二者択一ではなく、調整案を複数提示する
- 合意の文書化と再評価:その時の合意を記録し、一定期間ごとに再確認する
デイサービスでの事例では、糖尿病を持つ利用者が誕生日にケーキを望んだ際、家族は強く反対しました。相談員は栄養士や介護職と連携し、カロリー調整を行ったうえで少量を提供し、誕生会を一緒に楽しむ方法を提示。本人の満足感と家族の安心感を両立できました。このように相談員は本人の意思を軸に置きながら、家族の不安を和らげる支援調整を行う専門職なのです。
小まとめ:板挟みを「相談援助の機会」に変える
生活相談員の仕事において、職員や家族との意見の食い違いは避けられません。しかし、それを「問題」ではなく「調整の場」と捉えることで、信頼構築のきっかけに変えることができます。
- 職員との相違は、アセスメントの共有と実現可能な調整案で解決を図る
- 家族とのすれ違いは、傾聴と事実共有を基盤に代替案を設計し、合意形成につなげる
こうした積み重ねこそが、相談員を調整力を持つ専門職として成長させ、利用者の**生活の質(QOL)**を高めることに直結します。
👉 次回予告
【生活相談員】第4回:介護保険制度の基礎から現場活用へ ― 相談業務とのつながりを知る