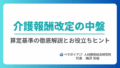高齢者・障がい者福祉の現場で、利用者の安全を守るために行われる対応の中には、実は「身体拘束」にあたる行為が含まれていることがあります。現場では「転倒を防ぐため」「事故を避けるため」といった理由で行われがちですが、その裏には利用者の尊厳や人権を奪ってしまうリスクが潜んでいます。
今回から始まる【身体拘束適正化】の連載では、介護職として必ず理解しておきたい「身体拘束」の基本から、現場での防止策までを全10回(前半5回・後半5回)にわたり取り上げます。第1回では、身体拘束の定義と具体例、そして法的根拠について考えてみたいと思います
1.身体拘束の定義と具体例
身体拘束とは、利用者の行動を制限し、自由を奪う行為を指します。表面的には「安全確保」のように見える対応であっても、本人の意思に反して自由を奪う場合には拘束に該当します。
代表的な例としては、次のようなものがあります。
- ミトン型手袋
→ 自分や他者を傷つけないようにする目的で装着し、手の動きを制限する。 - ベッド柵の両側使用
→ 転落防止のために設置するが、結果的にベッドからの離床を妨げてしまう。 - 車椅子の腰ベルト固定
→ 転倒を避ける目的でも、立ち上がる自由を奪ってしまう。
これらはすべて「良かれと思って」行われることが多いのですが、利用者の立場に立つと自由を奪う重大な行為であることを忘れてはいけません。
2.法的根拠:介護保険法と高齢者虐待防止法
身体拘束が問題とされる理由の一つは、法律で明確に禁止されているからです。
まず、介護保険法に基づく指定基準では、身体拘束やそれに類する行為は原則禁止とされています。事業者は「利用者の尊厳を守ること」を基本理念とし、安易な拘束はその理念に反するものです。
また、高齢者虐待防止法でも、身体拘束は虐待に含まれる可能性があるとされています。安全のためという名目であっても、常態化した身体拘束や場当たり的な行為は虐待と見なされることがあります。
ただし、すべての身体拘束が即虐待なのかというと、いわゆる例外があります。それが緊急やむを得ない場合の身体拘束(例外3要件)です。それについては後程詳しく解説させて頂きます。
以下の3要件をすべて満たした場合のみ、一時的に身体拘束が認められています。ただし本人が望んでいる事ではないということは明白ですので、認められているとはいえ、代替手段がない場合の最終的な対応方法と理解しておくべきです。
- 切迫性:本人や他者に生命や身体の重大な危険が差し迫っている。
- 非代替性:ほかに代わりとなる方法が存在しない。
- 一時性:必要がなくなればすぐに解除できる。
この3要件を満たさなければ、いかなる理由があっても身体拘束は認められていません。
小まとめ:現場での認識が第一歩
身体拘束適正化の出発点は、「これは拘束になり得る行為かどうか」を正しく認識することです。たとえばベッド柵を片側だけ設置していても、結果的に利用者の自由を奪っているなら身体拘束にあたる場合があります。
現場で働く介護職は、「自分たちにとって便利だから」という視点ではなく、常に利用者の立場から考える姿勢を持つことが求められます。チーム全体で知識を共有し、共通認識を持つことが、身体拘束廃止を実現する大切な一歩です。
次回は「身体拘束のリスク ― 利用者と職員に及ぶ影響」について解説します。
(筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕)