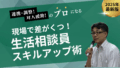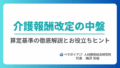デイサービスを取り巻く現実と未来への課題
‶令和9年度介護報酬改定″を見据える今、デイサービス経営は大きな岐路に立っています。‶令和6年度介護報酬改定″では、機能訓練の強化や‶科学的介護(LIFE)″の活用推進、委員会運営や記録整備の厳格化が示されました。これらは単に事務負担を増やすものではなく、デイサービスの存在意義や経営の方向性を根本から問い直すものでした。
現場の声を拾うと、「加算は算定できても委員会や記録業務が増えて職員が疲弊している」「LIFEの提出に追われ、利用者支援の時間が減ってしまった」といった課題が浮かび上がります。経営者にとって重要なのは、制度を知識として理解するだけではなく、‶制度を現場語に翻訳し、日々の運営に落とし込む視点″を持つことです。
事業を担う皆さまにとって、三年先を見据えた備えは不可欠です。制度改定は待ってはくれません。今の取り組みこそが、‶令和9年度介護報酬改定″を追い風に変える力となります。
生き残りの戦略は制度を‶現場語″に翻訳すること
‶デイサービスの差別化″は、大きな投資を伴わなくても実現できます。重要なのは、利用者が無理なく継続できる仕組みを整えることです。たとえば、午後になると活動意欲が低下する利用者が多い場合には、短時間のプログラムを組み込み、参加しやすい環境を作ることが効果的です。こうした工夫の積み重ねが、利用者やご家族から「この施設に通いたい」と評価される基盤となります。
また、‶委員会や記録の仕組み化″も欠かせません。会議アジェンダを標準化すれば、毎月の準備にかかる時間と負担を減らせます。記録を‶LIFEの提出データと連動″させれば、二重記録を避けられ、業務効率が高まります。これらは単なる効率化にとどまらず、‶職員に余裕を与え、利用者と向き合う時間を確保するための投資″です。
そして最も重視すべきは‶人材定着″です。制度対応をいかに進めても、職員が離職してしまえば経営の持続性は損なわれます。送迎ルートを見直したり、ICTを導入して出欠管理を効率化したりすれば、日常業務の負担を減らせます。さらに、法人として研修や資格取得を支援することで、職員は「成長できる職場」と実感できます。利用者の歩行改善や嚥下機能の回復といった成果を共有すれば、日々のやりがいが明確になり、働き続けたいと感じる環境が整います。
‶令和9年度介護報酬改定″は、デイサービスの未来を決定づける大きな節目になります。制度を「加算要件」として読むだけではなく、‶経営に効く仕組み″として現場語に翻訳し、実務に活かせるかどうかが生き残りを左右します。皆さまが今から備えを進めれば、三年後には確かな成果を得られるはずです。
(筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕)