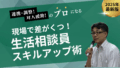介護や福祉の現場で虐待を防ぐには、職員一人ひとりの努力だけでは限界があります。どれほど熱意を持った職員であっても、日常的なストレスや孤立感を抱えれば、不適切な言動につながる可能性は否定できません。そこで重要となるのが、チーム全体で支え合う虐待防止の仕組みです。その中心となるのが、誰もが気軽に相談できる職場風土の構築です。
1.相談できない職場が抱えるリスク
高齢者サービスでは、夜勤や人手不足により、職員が多大な負担を抱える場面が少なくありません。疲労や焦燥のなかで「早くしてください」「言うことを聞いてください」と強い口調で接してしまうのは、心理的虐待の入口となり得ます。こうした状況でもし相談できる雰囲気がなければ、職員は孤立し、さらに追い込まれてしまいます。
障害者サービスでも、突発的なパニックや自傷・他害行動に一人で対応せざるを得ない場面があります。支援方法に迷いを抱えても相談できなければ、「叱るしかない」「強く制止するしかない」といった誤った対応に陥る危険が高まります。結果として支援の質は低下し、虐待リスクが増大します。
つまり、相談できない職場は虐待リスクを高める要因です。逆に、相談が日常的に行える職場では、職員同士が互いを支え合い、安心感を持って業務に臨めます。
2.相談できる風土を育てる実践方法
日常的な声かけと共有の仕組み
「困っていない?」「今日の利用者の様子はどうだった?」といった声かけは、相談を自然に引き出します。朝礼や終礼で短時間でも気づきを共有できる場を設けると、悩みを話すハードルが低くなります。
上司やリーダーの受け止め方
相談を受けたときに「それくらい我慢して」と否定する態度を示せば、職員は二度と相談しなくなります。「話してくれてありがとう」「一緒に考えよう」という姿勢を示すことで、安心して声を上げられる環境がつくられます。
チームでの事例検討
定期的な会議や勉強会で「どう対応すればよかったか」を振り返ることは有効です。個人を責めるのではなく、事例から学ぶ機会とすることが大切です。これにより、相談が自然に促進され、職場全体のスキル向上にもつながります。
外部相談窓口の活用
内部だけで解決できない場合は、市町村や第三者機関の相談窓口を利用することも必要です。「外に出してもよい」という安心感は、職員を孤立から守り、利用者の権利擁護にも直結します。
まとめ ― 相談できる風土が虐待を防ぐ力になる
虐待防止は個人の力だけで成り立つものではなく、相談できる職場風土によって支えられます。日常的な声かけ、上司の受け止め方、チームでの学び、外部窓口の活用――これらを積み重ねることで、職員と利用者の双方が守られる現場を実現できます。
次回は新企画として、【身体拘束適正化】第1回:身体拘束とは何か ― 定義と法的根拠を理解する をお届けします。身体拘束に関する正しい理解と法的背景を押さえ、現場での判断に役立つ内容を解説します。
筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕