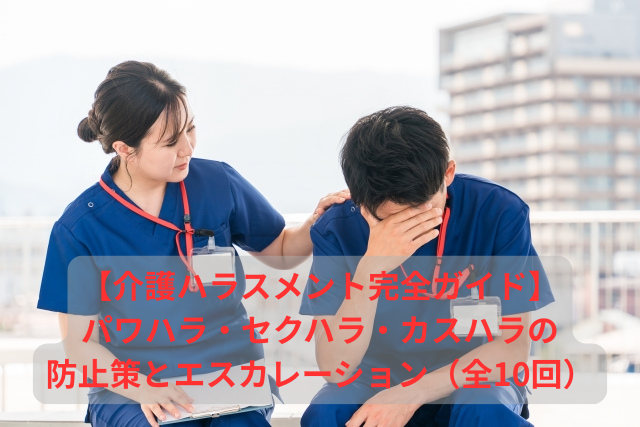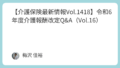介護現場で問題となるセクシュアルハラスメントは、単なる「人間関係トラブル」ではありません。職員の尊厳を深く傷つけ、働く意欲を失わせる深刻な問題です。言葉によるからかい、視線での圧迫、身体への不要な接触など、その形は多様ですが、いずれも受け手に不快感や恐怖心を与える行為です。さらに介護の現場には、利用者やその家族から性的な言動を受けるケースもあり、他産業とは異なる特有の難しさがあります。
まずは「職場内でのセクシュアルハラスメント」と「利用者からの性的言動」の二つを切り分けて考えることが必要です。前者は組織的なルールで防止・対応すべきものであり、後者は厚生労働省の指針に基づき、疾患や障がい特性をふまえた個別ケアとして取り組むことが求められます。
職場内のセクシュアルハラスメントを防ぐために
施設や事業所では、上司や同僚による不適切な言葉や態度が見過ごされることがあります。「業務だから断れない」「上司だから言えない」といった背景が、問題を放置してしまう原因です。
ここで大切なのは、被害にあった時点ではっきりと拒否を伝える勇気です。曖昧な態度は誤解を生み、行為が繰り返されやすくなります。感情的になる必要はなく、事実を淡々と示すことが効果的です。
対応のポイントは以下のとおりです:
- 拒否を明確に伝える
「その言葉は不快です」「その接触は必要ありません」と短く伝える。 - 記録を残す
・日時・場所
・発言や行為の内容(できれば原文)
・自分の対応と相手の反応 - 相談につなげる
信頼できる上司や相談窓口に報告し、個人で抱え込まない。
さらに管理者やリーダー層は、以下のような仕組みを導入して予防に努める必要があります。
| 予防策 | 内容例 |
|---|---|
| 二人一組での業務配置 | 身体介助などで孤立しないようにする |
| 定期的な面談 | 職員の声を拾い上げ、早期発見につなげる |
| 職場ルールの明文化 | 「セクシュアルハラスメントを許さない」姿勢を示す |
利用者からの性的言動への対応:個別ケアを基本に
介護職員が直面するもう一つの大きな課題は、利用者からの性的言動です。多くの場合、認知症・精神障がい・発達障がいなど疾患や特性に起因しており、厚生労働省は「個別ケアを基本に対応すること」を指針として示しています。
対応の工夫としては:
- 環境調整
・照明を落とす、静かな場所へ移す
・衣類やタオルで肌の露出を減らす - 手順の見える化
・ホワイトボードやカードで「次に何をするか」を伝える - 同性対応や複数人対応
・不安や誤解を避け、職員の安全を守る
それでも職員の尊厳が脅かされる場合は、短く明確に拒否を伝えます。
例:
- 「その表現は受け入れられません」
- 「その接触は介助には不要です」
同時に記録を残し、必要に応じて責任者に交代します。その後、医師・家族・相談支援専門員と連携し、ケア計画を見直すことが再発防止につながります。
小まとめ
- 職場内のセクシュアルハラスメント
→ 拒否を明確にし、記録と相談で組織的に対応。 - 利用者からの性的言動
→ 個別ケアの工夫で対応。それでも危険なら拒否を伝え、ケア計画を調整。
セクシュアルハラスメントを個人で抱え込まず、職場全体の仕組みとチームの力で解決することが、介護現場の安心を守ります。
筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕