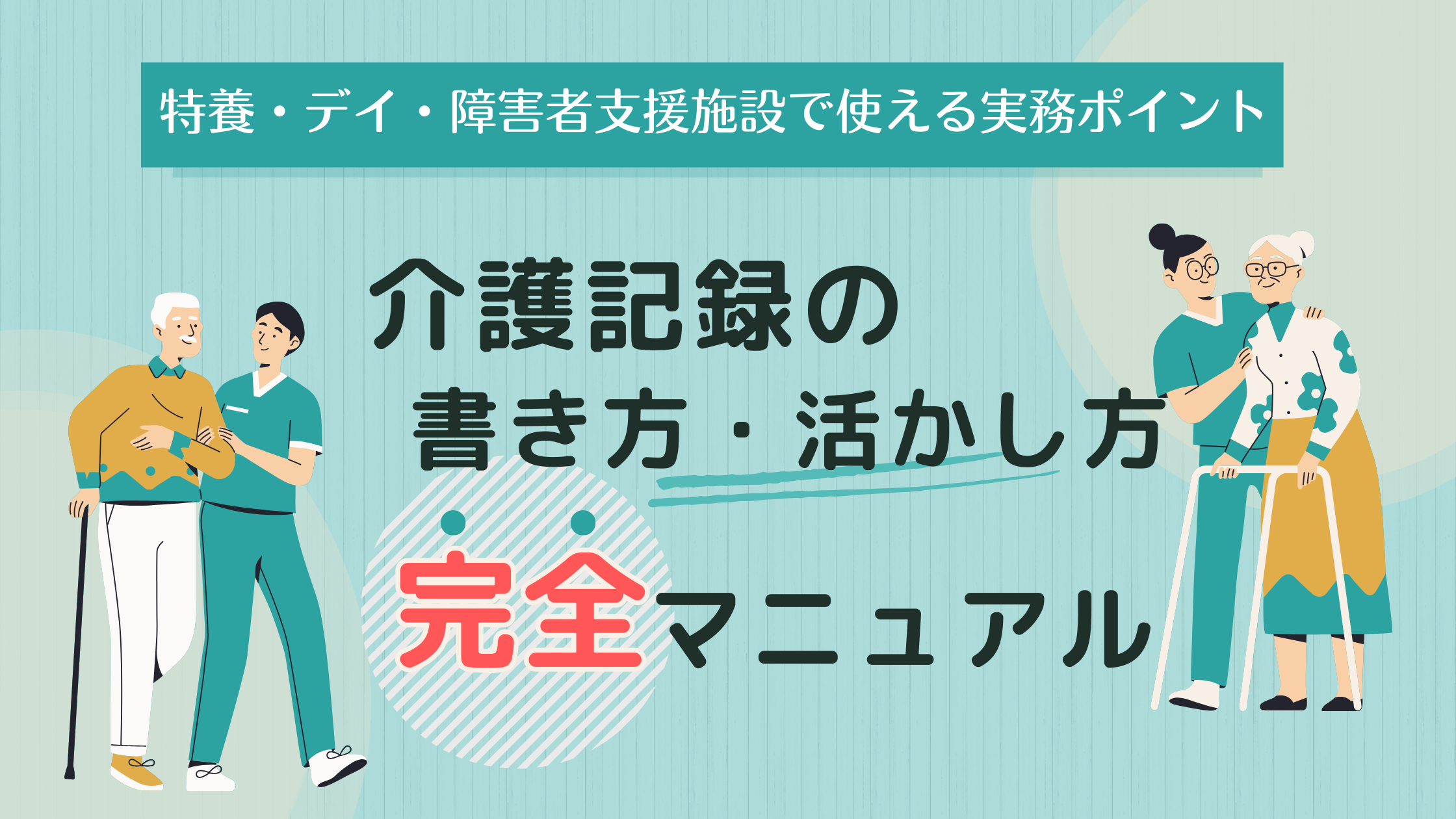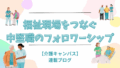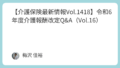排泄は利用者の尊厳を守るうえで最も繊細なケアであり、同時に健康状態を見極める重要な観察場面です。介護記録では「出た/出なかった」だけでは不十分で、排泄パターン・便性状・尿量・対応と結果を具体的に残すことが欠かせません。今回は、特養ホームやデイサービス、障害者支援施設などで活用できる、排泄介助の記録の書き方と文例を紹介します。
1.排泄パターン・便性状・尿量を正確に残す
排泄の記録は、日々の観察による変化の早期発見に直結します。まず押さえておきたいのは「時刻・方法・自立度・状態」の4点です。
- 排泄パターンの文例
10:15 トイレ誘導にて排尿。自立で実施。声かけにスムーズに応じ、排泄後は安堵した表情を見せた。
- 便性状の文例
14:30 トイレで排便。普通便、中等量、茶褐色で形状安定。終了後に手洗いも自立で実施。
- 尿量の文例
11:00 ポータブルトイレで排尿。約200ml、淡黄色。臭気の異常は認められない。
記録では、あいまいな表現は避けることが大切です。「少し硬め」「かなり多い」といった感覚的な言葉ではなく、「硬便」「約200ml」といった客観的で比較可能な言葉を用いましょう。これが、便秘や感染症の兆候を見落とさない基本姿勢となります。
障害者支援施設では、利用者本人が排泄の状況を伝えにくい場合もあります。その場合は表情やしぐさ、衣類の状態といった間接的な観察情報を記録に残すことが支援の精度を高めます。
2.失禁・便秘・下痢の対応と記録の工夫
排泄介助では、失禁や便秘、下痢といった予期せぬ場面に直面することが少なくありません。ここで重要なのは「何が起きたか」だけでなく、その後の対応と結果、そして報告先まで一連で記録することです。
- 失禁の文例
15:20 ベッド上で衣類湿潤を確認。尿失禁。衣類・寝具を交換し、陰部を洗浄。本人へ安心の声かけを行った。皮膚異常なし。看護師に報告済み。
- 便秘の文例
3日間排便なし。腹部に軽度の張りを認める。水分摂取を促し、看護師へ報告。下剤内服の有無を確認予定。本人は表情穏やかで不快感少ない。
- 下痢の文例
10:40 下痢便(泥状・中等量・淡褐色)を2回確認。皮膚洗浄と保湿クリーム塗布を行った。脱水予防のため水分を提供。看護師に報告し、トイレは消毒実施。感染症対応へ切り替え。
こうした記録は、次の勤務者や看護師が「何がすでに行われ、何がこれから必要か」を判断するための大切な情報源です。特に下痢や繰り返す失禁は、感染症や疾患の兆候である可能性があるため、観察事実に基づいた冷静な記録が不可欠です。
小まとめ
排泄介助の記録は、単なる事実の記録ではなく、未来への道しるべです。
- 時刻・方法・自立度を正確に
- 便性状や尿量は具体的な観察事実で
- 失禁・便秘・下痢は「事実→対応→結果→報告」の流れで
たった一行の記録でも、その精度が翌日の介助を支え、利用者の安心と安全を守ります。排泄というデリケートな領域だからこそ、尊厳に配慮しながら丁寧に残すことが、介護の質を高める第一歩となります。