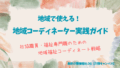介護や福祉の現場では、「利用者を守ること」ばかりが強調されがちですが、同じくらい大切なのは職員を守ることです。夜勤や人手不足による疲弊、突発的な自傷や他害行動に直面する心理的負担は、日々介護・福祉に携わる人々を確実に追い込んでいきます。こうしたストレスを放置し続ければ、職員のストレスはピークとなり思わぬ感情の高ぶりから、不適切ケアや虐待リスクに繋がってしまうことも…。今回は、高齢者サービス・障害者サービス双方に共通する「感情コントロール」と「ストレス対策」の実践法を解説します。
1.高齢者サービスと障害者サービスでのストレスのかたち
高齢者サービスにおける慢性的ストレス
特別養護老人ホームやデイサービスでは、夜勤や人手不足が職員の大きな負担になります。例えば、夜勤明けに複数の入浴介助や排泄介助を連続で行う場面を想像してください。睡眠不足や疲労の蓄積により、「早くして」「言うことを聞いて」といった強い言葉が出やすくなります。これは心理的虐待の引き金になり得る危険な状態です。
また、高齢者は認知症を合併している場合も多く、繰り返しの質問や拒否行動に対応するうちに、職員の心はすり減っていきます。「どうせ分かってもらえない」とあきらめの気持ちを抱けば、ケアの質も低下します。
障害者サービスにおける突発的な心理的負担
グループホームや生活介護の現場では、突発的な自傷・他害行動に直面することがあります。突然の大声、物を投げる行動、身体的な接触を伴うパニック。こうした場面で職員は強い恐怖や無力感を覚え、「次にまた起きたらどうしよう」という予期不安を抱えやすいのです。
この不安や緊張は、次第に「防衛的な態度」や「距離を置く対応」として表面化し、利用者との関係を悪化させます。つまり、ストレスを適切に処理できなければ、関係性そのものがケアの阻害要因になってしまうのです。
2.感情を整えるための技術と仕組み
さまざまな感情のコントロール方法
介護職・支援職にとって有効なのがさまざな感情コントロールの方法です。怒りの感情は自然なものですが、爆発すれば虐待リスクに直結します。現場で実践しやすいのは以下の3つです。
- 6秒ルール:アンガーマネジメントの一つ。カッとなった瞬間、深呼吸して6秒待つ
- 言語化:「いまイライラしている」と自分の気持ちを声に出す
- 視点の転換:「相手は困っているからこそこうしている」と考える
こうした小さな工夫で、感情の暴発を防ぐことができます。
タイムアウトの実践
どうしても感情が高ぶってしまうときは、タイムアウト(一時的にその場を離れること)が有効です。数分間別の職員が対応を引き継ぎ、本人は心を落ち着ける時間を持つ。これにより、危険な衝動的対応を避けられます。
相談窓口とチーム支援
最後に欠かせないのは、相談できる場の整備です。上司や虐待防止委員、外部の専門相談窓口に、日常的にストレスを話せる環境を作ることが重要です。「弱音を吐いてはいけない」という組織風土は、職員を孤立させ、一人で悩みを抱え込むことが大きなリスクとなります。むしろ「相談するのが当たり前」といえる環境を職場全体で育てる必要があります。
まとめ ― 職員を守ることが虐待防止につながる
虐待防止は「利用者を守ること」だけでは成り立ちません。職員の心身を守ることこそが、虐待の芽を摘む最大の予防策です。高齢者サービスでは慢性的ストレスへの対応を、障害者サービスでは突発的な心理的負担への対処を。それぞれの現場での違いを理解しながら、アンガーマネジメント・タイムアウト・相談窓口を組み合わせることで、安心して働ける環境を整えることができます。
次回(第5回)は、「チームで取り組む虐待防止 ― 相談できる職場風土づくり」をテーマに、具体的な仕組みづくりのヒントを紹介します。