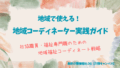介護や福祉の現場では、職員が意図せずに行ってしまう「不適切ケア」が少なくありません。その多くは悪意から生まれるものではなく、忙しさや慣れ、知識不足から生じる“グレーゾーン”です。しかし、このグレーゾーンを放置すれば、やがて本格的な虐待へとつながる危険性があります。
今回は、高齢者サービス・障害者サービスの現場で起こりやすい不適切ケアの具体例を取り上げ、どのように境界線を理解し、修正につなげるかを考えます。
1.不適切ケアと虐待の違い
不適切ケアとは
- 利用者の尊厳を損なう言動や配慮不足
- 職員の意図は「効率」「安全」のつもりでも、結果的に不快や苦痛を与える行為
虐待とは
- 法的に定義された行為(身体的・心理的・性的・経済的・放置)であり、明確に“権利侵害”が生じた状態
つまり、不適切ケアは「すぐに虐待と断定はできないが、境界に近いリスク行為」です。ここを正しく理解し、早めに修正することが大切です。
2.高齢者サービスに見られるグレーゾーン事例
事例①:排泄介助での声かけ
「もう、おむつにしておけばいいのに」
→ 悪気はなくても、利用者の尊厳を傷つけ、心理的虐待に近づく発言です。
事例②:食事介助の急かし
「早く食べてください」「時間がないんです」
→ 職員側は業務効率を考えていても、利用者にとっては“脅迫感”や“恥辱”となり得ます。
事例③:身体拘束に近い介助
ベッドから落ちないように柵を高く上げすぎる、抑制ベルトを長時間使う
→ 安全確保のつもりでも、身体的虐待に抵触する可能性が高まります。
3.障害者サービスに見られるグレーゾーン事例
事例①:パニック時の強制対応
「静かにしなさい!」と大声で叱責し、無理に押さえ込む
→ 感覚過敏や特性を理解しない対応は、心理的・身体的虐待に発展します。
事例②:特定の利用者への“扱いの差”
言葉が通じにくい人を放置しやすい、行動障害のある人に冷たく接する
→ 「どうせ分からないから」という態度がネグレクトにつながります。
事例③:過度なルールの押しつけ
職員の都合を優先して、一律のスケジュールを強要
→ 本人の意思や特性を無視した関わりは、不適切ケアの典型です。
4.グレーゾーンを修正するための実務の視点
①その場で“言い換える”
- NG:「早くして!」
- OK:「もう少しでお食事の時間が終わってしまうので、一緒に頑張りましょう」
②気づいたら“記録と共有”
「言いすぎたかも」「強く当たったかも」と感じたら、まずはメモや日誌に残すこと。上司や虐待防止委員に相談することで、再発防止に活かせます。
③振り返りを“学び化”する
ケース検討会やOJTで、「この場面をどうすればよかったか」をチームで振り返る。グレーゾーンを組織学習に変えることで、職場全体の防止力が高まります。
5.“気づける職場”をつくるために
グレーゾーンの怖さは、「見過ごされ、当たり前になってしまうこと」です。新人が先輩の不適切ケアを真似してしまえば、それは文化として定着してしまいます。
だからこそ職場では、
- 「この対応、どう思う?」と意見交換できる雰囲気
- ミスや失敗を責めるのではなく“改善のきっかけ”として扱う風土
- グレーゾーンを学びに変える仕組み(勉強会・研修)
を整えることが大切です。
まとめ ― グレーゾーンは“早めの修正”がカギ
不適切ケアと虐待の境界線は、思った以上に曖昧です。だからこそ「これは危ないかもしれない」と思った時点で記録・相談・修正につなげることが重要です。
高齢者サービス・障害者サービスの両方で共通するのは、小さな配慮の積み重ねが利用者の尊厳を守り、虐待を防ぐ最大の武器になるということです。
次回(第4回)は、「職員を守るメンタルケアと感情コントロール」について、現場で役立つストレス対処法をお届けします。