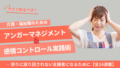~制度・情報・風土が企業を変える~
介護離職を「防げなかった企業」と「防げた企業」の違いとは?
介護離職を防ぐためには、偶然や成り行き任せではなく、明確な戦略が必要です。
前回のブログでご紹介したとおり、年間約10万人が「介護を理由に退職」している国内企業の現状では、企業が積極的に両立支援に乗り出さなければ、人材の流出は避けられません。
では、どうすれば「介護と仕事を両立できる職場」を実現できるのでしょうか?
その答えが、今回のテーマである「3つのカギ」=制度・情報・職場風土です。
カギ①:制度を“形だけ”で終わらせない
✔ 仕事と介護の両立支援制度の整備はスタート地点
企業がまず整えるべきは、法定・任意を問わず「仕事と介護の支援制度」です。
例えば以下のような制度は、多くの企業がすでに導入済み、あるいは導入可能です。
- 介護休暇(年5日:要介護家族1人につき)
- 介護休業(通算93日:分割取得可能)
- 時短勤務、フレックスタイム制、在宅勤務
- 所定外労働の免除・制限
- 積立有給制度(私傷病・介護への流用)
- 社外相談窓口(EAPなど)
✔「使えない制度」は“存在しない”のと同じ
大切なのは、制度が「あるか」ではなく、「使われているか」です。
特に管理職や同僚の理解がない職場では、「制度があっても使いにくい」「休むとキャリアに悪影響がある」と社員が感じ、実際には利用をためらうケースが後を絶ちません。
→ 制度の運用とともに、周囲の受け入れ体制や業務調整ルールの明確化が不可欠です。
カギ②:正しい情報を“事前に”届ける
✔「介護はある日突然」は本当
親の病気や転倒をきっかけに、明日から突然「介護生活」が始まる——。
こうしたケースは非常に多く、介護の前兆や段階的な移行がなく、本人も職場も準備不足のまま突入してしまうことが問題です。
✔ 会社が情報発信を行うメリット
そのため、企業が行うべきは、“介護の備え”に関する情報を、予防段階から社員に届けることです。
- 社内イントラネットに介護制度の案内ページを設置
- 人事面談の際に家庭状況をヒアリング
- 社内セミナーや外部講師による両立支援講座の開催
- パンフレットや事例集の配布(「こうすれば両立できた」)
「親が高齢だけど、まだ元気だから自分は関係ない」と思っている社員にこそ、早期から「情報の種まき」が重要です。
情報は「トラブルが起きてから探すもの」ではなく、「事前に得ておくべき備え」なのです。
カギ③:風土が“制度の使いやすさ”を決める
✔ 制度があっても、職場の雰囲気がNGなら使えない
ある企業では、時短勤務の制度があるにもかかわらず、実際には利用率が極端に低い状態が続いていました。理由は、「使ったら昇進に響く」「周囲に迷惑をかけたくない」という“職場の空気”が原因でした。
制度だけ整っていても、社員が「使いにくい」と感じている時点で、それは機能不全です。
✔ 「両立支援=特別扱い」ではないと伝える
風土づくりのポイントは、「仕事と介護の両立支援制度を使うことは特別ではない」という企業の明確なメッセージです。
たとえば、
- 経営トップが制度利用の促進をメッセージとして発信
- 管理職が制度の内容と活用事例を学ぶ研修の実施
- 制度利用社員が孤立しないようなチーム運営方法の共有
といった取り組みが、職場全体に「使っていいんだ」という空気を醸成します。
→ 風土改革なくして制度の定着なし。これは企業の長期的な競争力にもつながる重要施策です。
まとめ|3つのカギは“セット”で考える
介護離職を防ぐためには、次の3点を“同時に”動かすことがカギとなります。
| カギ | 具体的な取り組み例 |
|---|---|
| 制度 | 介護休業、時短、在宅勤務、EAPなどの整備 |
| 情報 | セミナー、イントラ、パンフ配布、相談窓口の紹介 |
| 風土 | 管理職研修、制度利用のメッセージ化、職場の理解 |
制度だけ導入しても、情報が届かず、風土が冷たい――そんな状況では意味がありません。
3つのカギをバランスよく機能させてこそ、社員も企業も安心できる「両立職場」が実現するのです。