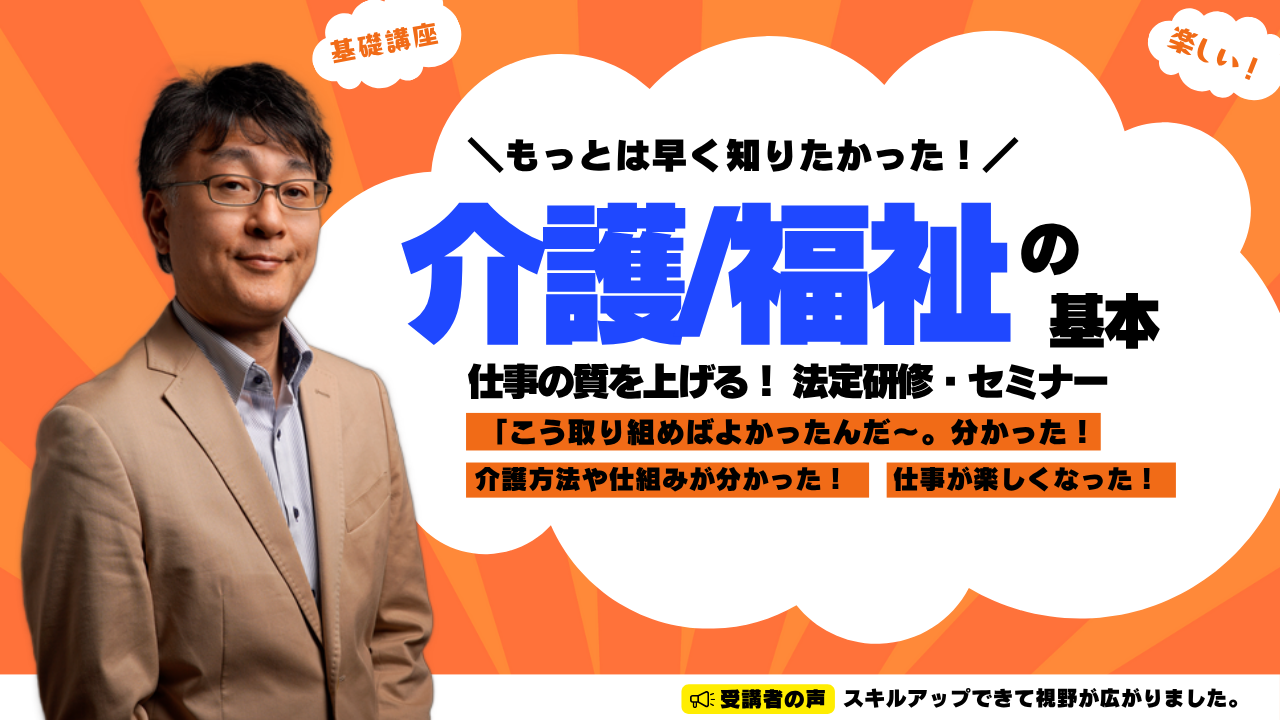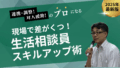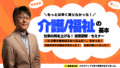―― 制度を“現場のしくみ”として動かすために
はじめに:形だけの「委員会」になっていませんか?
虐待防止は、いまやすべての介護・障がい福祉事業所に求められる法定研修の必須テーマです。
しかし現場では、「委員会は設置しているけれど機能していない」「指針はあるが職員が読んでいない」など、形だけの体制になってしまっているケースも少なくありません。
虐待は特別な職場だけで起きるわけではなく、日常の延長線上に潜むリスクです。
忙しさのなかで、つい強い口調で声をかけてしまう。
言葉を選ぶ余裕がなく、支援が機械的になる。
そうした「小さなズレ」の積み重ねが、職場全体の雰囲気を変えていきます。
1.現場の“グレーゾーン”をどう見える化するか
高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法が目指すのは、「虐待を起こさない仕組み」だけではありません。
本来は、職員が安心して支援できる職場環境をつくることが目的です。
たとえば――
- 食事介助の際、「早く食べて!」と急かしてしまう。
- 声かけを省略し、身体介助を無言で進めてしまう。
- 職員同士の人間関係の悪化が利用者対応に影響している。
これらはいずれも「不適切ケア」と呼ばれるグレーゾーンに位置します。
虐待防止委員会が機能している職場では、こうした事例について“起きした個人だけ”を責めずにチームで共有し、個人・組織での改善策を話し合う場を設けています。
体制づくりの第一歩は、この“躊躇なく話し合える雰囲気(風土)”を育てることにあります。
2.制度の4つの柱を、現場で動かす視点
令和6年度介護報酬改定では、虐待防止体制の整備がさらに明確化されました。
委員会、指針、研修、担当者――この4つの要件は、どれも「カタチだけ整えて終わり」ではなく「職場を動かす・実際に機能する仕組み」です。
| 要件 | 内容 | 現場でのポイント |
|---|---|---|
| 委員会 | 虐待防止の検討・振り返りの場 | 実例を共有し、対話型で進める |
| 指針 | 行動規範・対応マニュアル | 形式文書ではなく、実務の基準に |
| 研修 | 職員への啓発と実践力向上 | 体験型・ケース検討型で継続実施 |
| 担当者 | 窓口・相談・調整の中核 | 現場の相談しやすさを重視 |
制度としての4要件は、単なるチェックリストではなく、人が動くための仕組みです。
行政監査で指摘を受けやすいのは、「書いてあるけど機能していない」ケース。
この研修では、体制整備を“運用”に変えるための行動変容を促進する視点をわかりやすく解説します。
小まとめ:制度を“文化”に変えるために
虐待防止の仕組みを形づくるのは「人」です。
委員会も指針も、職員一人ひとりの意識と行動がなければ機能しません。
本研修では、法制度の理解だけでなく、現場で動かすための工夫と実践モデルを学びます。
第2部では、支援者自身の「心の安定」や「感情マネジメント」の視点から、
防止体制を支える“人づくり”のアプローチを紹介します。
📌 研修のご相談はこちら ― 研修企画担当の皆さまへ
介護施設・障がい福祉事業所の研修委員会のご担当者様、
また老施協・社協など団体で研修を企画・運営されている皆さまへ。
虐待防止の取り組みは、すべての事業所に求められる法定研修ですが、
その目的は「年度内の義務を果たすこと」ではなく、
職員が気づき、考え、行動を変えるきっかけを生み出すことにあります。
ベラガイア17 人材開発総合研究所では、
特養・デイサービス・障がい者支援施設・地域包括支援センターなど、
多様な現場や職員層に合わせたオーダーメイド型の虐待防止研修を実施しています。
本ページでご紹介している内容は研修プログラムの一部です。
ご依頼者様の意向や現場の課題を丁寧に伺いながら、
内容・時間・形式を柔軟にカスタマイズいたします。
「まずは内容を相談したい」「既存の研修を刷新したい」など、どの段階からでもお気軽にご相談ください。
実施形式(集合・オンライン・ハイブリッド)や時間設定(90分・半日・終日研修)にも対応可能です。
ご要望により、虐待防止指針づくりや行政提出用の研修報告書の作成ポイントも解説可能です。
📎 研修内容・講師派遣の詳細はこちら
➡ [研修シラバス一覧ページへ]
➡ [お問い合わせフォーム] ※外部リンク(ホームページ)