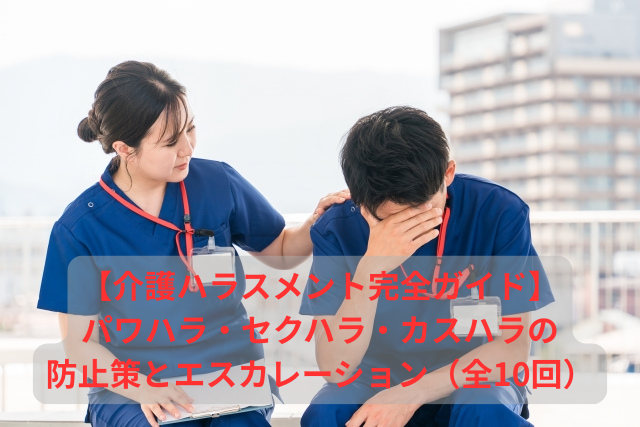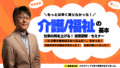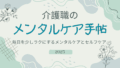介護の現場では、毎日のように「記録」を書きます。
しかし、その書き方次第で、あなた自身を守る“盾”にもなれば、逆に“誤解を招く記録”にもなります。
トラブルやクレーム、カスタマーハラスメント(カスハラ)が起きたとき、最も重視されるのは「何をどう記録したか」です。
記録は「思い出」ではなく、「証拠」であり、「信頼の証」でもあります。
今回は、介護職が自分とチームを守るために押さえておきたい“記録の型”と“注意点”を紹介します。
1.「見たこと」と「感じたこと」を分けて書く
介護記録で最も多いミスは、事実と感情を混同することです。
「怒っていた」「理解していない」と書くと、読む人によって受け取り方が変わります。
客観性を保つためには、“見たこと”と“感じたこと”を分けて記録することが基本です。
| NGな書き方 | 改善された書き方 |
|---|---|
| 利用者が怒っていた。 | 利用者が大声で「なんで遅いんだ」と発言した。 |
| 家族がクレーマー的対応をした。 | 家族が「今すぐ責任者を出せ」と発言し、10分間対応を求めた。 |
| 説明を理解していない。 | 説明後も「納得できない」と繰り返し発言した。 |
このように、「誰が・いつ・どこで・何をした」を具体的に書くことが大切です。
主観的な判断を避け、第三者が読んでも状況がイメージできるようにします。
2.「行動の流れ」を残す ― 対応の意図と結果まで
記録は単なる“出来事の報告”ではなく、どう考え、どう動いたかを残すものです。
特にトラブル対応では、「発生→対応→結果」の3つを意識して書きましょう。
- 発生した事実
例:「入浴拒否の際、『今日は入らない』と発言。」 - 職員の対応
例:「無理に促さず、10分後に再訪問。希望を確認し更衣のみ実施。」 - 結果・評価
例:「更衣後は落ち着き、『明日は入る』と発言。」
この流れで記録すると、あとで読み返した際に「職員が冷静に判断した」ことが伝わります。
カスハラへの対応記録でも同じです。
たとえば、家族から強い要求や暴言があった場合、
- どんな発言があったのか
- どのように対応したのか
- どの段階で上司に報告したのか
を具体的に記録しておくことで、「職員として適切に行動した証拠」になります。
※ただし、利用者本人の発言や行動が認知症や疾患に起因するものである場合は、厚生労働省の指針にもあるとおり、ハラスメントとして一律に扱うのではなく、支援(ケア)枠として対応を検討することが重要です。
医師・ケアマネジャー・家族などと連携し、症状や心理的要因を踏まえてケア計画を見直すことが望まれます。
(出典:厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」)
記録の目的は「責めること」ではなく、「支援の質を高めること」。
この視点を忘れず、事実と対応を正確に残すことが信頼につながります。
小まとめ
- 事実と感情を分けて、客観的に書く。
- 発生→対応→結果の流れで、意図と行動を明確に。
- 疾患・認知症による言動は支援枠で対応を検討する。
日々の記録は、あなた自身とチームの安心を支える大切な基盤です。
一つひとつの記録が、介護の信頼と安全を守る力になります。