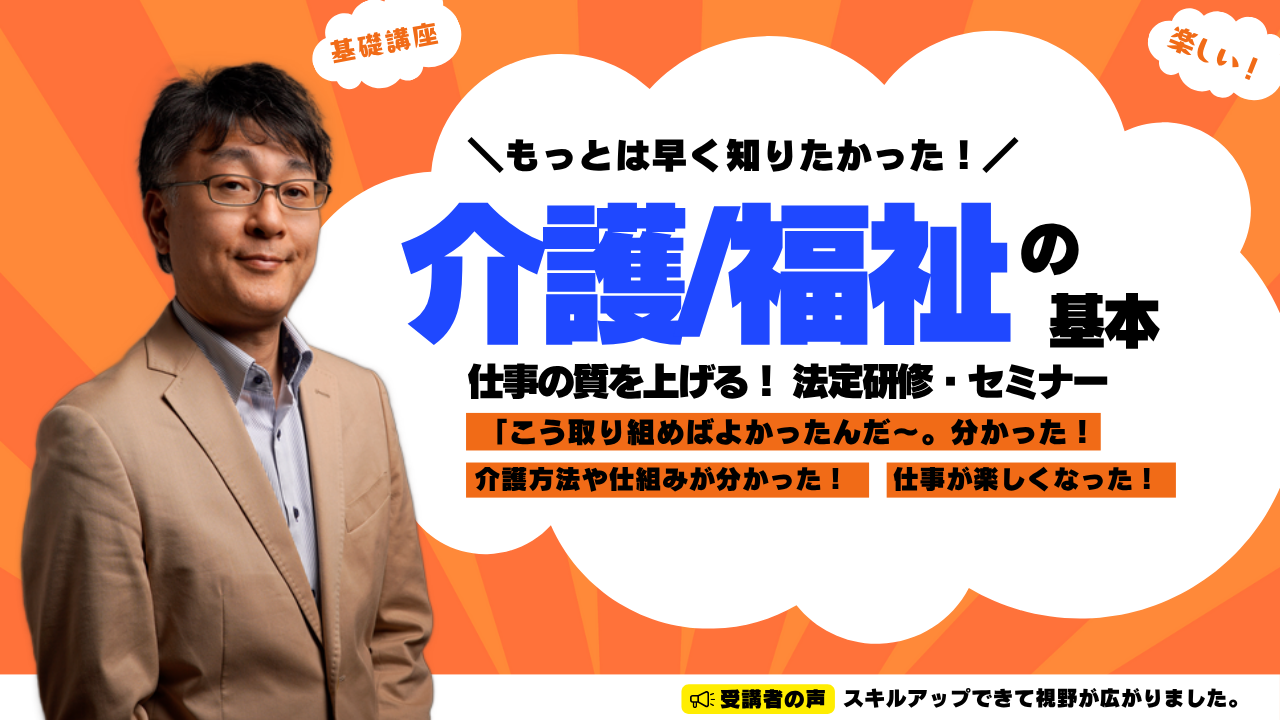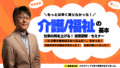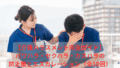― 絶対にあってはならない“虐待”を防ぐために、組織で動く
虐待は、どのような理由があっても決してあってはならない行為です。
それは支援を受ける方の尊厳を深く傷つけるだけでなく、
支援を担う職員や組織全体の信頼を失墜させます。
介護・障がい福祉の現場では、ほとんどの職員が「利用者の幸せを願って」支援をしています。
しかし、業務の多忙やコミュニケーション不足、人手不足などが重なると、
“意図せず”利用者の尊厳を損なう言動や対応が生まれてしまうことがあります。
だからこそ今、「虐待を防ぐ」ことを個人の努力に任せず、組織全体で守る仕組みが求められています。
1.虐待とは何か ― 法の定義と現場の理解
虐待とは、単なる不適切な言動ではなく、
**「支援を受ける人の権利・尊厳を侵害する行為」**を指します。
高齢者分野では「高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」、
障がい分野では「障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」に基づき、
事業者や職員には通報・報告の義務が課せられています。
虐待の類型は共通して5つです。
- 身体的虐待:たたく・押さえつける・身体拘束するなどの行為
- 心理的虐待:暴言・無視・威圧的な態度・人格を否定する言動
- 性的虐待:本人の同意のない接触・性的発言
- 経済的虐待:金銭・財産の不正使用、本人の承諾なしの管理
- 放置・ネグレクト:必要な介護・支援を行わない、または放置する
これらはいずれも、**「支援者の意図に関わらず、結果として相手の尊厳を傷つける行為」**として捉えられます。
つまり「悪意がないから虐待ではない」ということは、法的にも認められません。
2.個人・チーム・組織で守る ― 多層的な防止体制の考え方
虐待防止は、委員会や指針を整備しただけでは実効性を持ちません。
個人・チーム・組織・法人方針の4つの層が連携し、
“気づきが行動に変わる”仕組みとして動かすことが大切です。
- 個人の役割:日々の支援で「これは正しい対応か?」と自問できる意識を持つこと。
- チームの役割:お互いに声をかけ合い、記録・会議で違和感を共有すること。
- 組織の役割:委員会や研修で課題を可視化し、改善策を継続的に検討すること。
- 法人の役割:理念・方針に“虐待防止の視点”を明文化し、職員の判断を支える環境を整えること。
この4層がつながることで、
「見て見ぬふりをしない」「誰もが声を上げられる」組織文化が形成されていきます。
小まとめ
虐待防止は、“制度対応”で終わらせてはいけません。
現場の支援を守り、支援者自身を守るための体制づくりこそが目的です。
そのためには、法の理解と日常業務を結びつけ、組織全体で考える仕組みが欠かせません。
📌 研修のご相談はこちら ― 研修企画担当の皆さまへ
本研修は、特養・デイサービス・障がい福祉・地域包括など、
事業種別や職員層に合わせて柔軟に設計しています。
委員会研修、全職員研修、管理者研修など、目的に応じてアレンジ可能です。
内容のご相談・見積りはお気軽にお問い合わせください。
➡ [研修シラバス一覧ページへ]
➡ [お問い合わせフォーム]