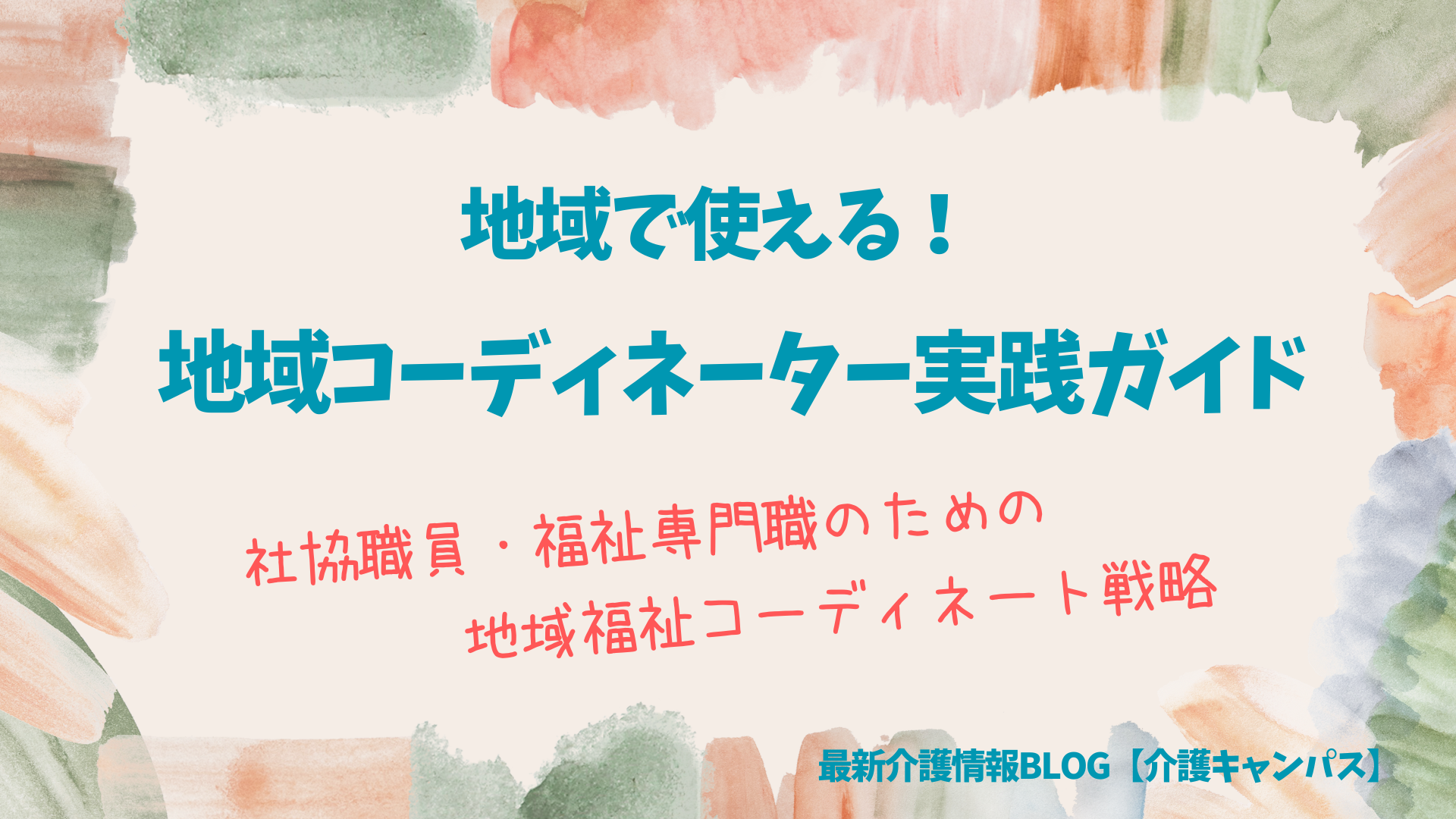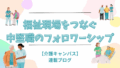(シリーズ:現場で使える!地域コーディネーター実践ガイド)
地域で活動している社協職員・ケアマネジャー・地域支援コーディネーター・ボランティアの皆さん。
日々の相談の中で、「この人はどの制度にも当てはまらない」「どこに相談すればいいのかわからない」と感じたことはありませんか?
今回は、そうした制度の“はざま”にいる人を支援するための考え方と実践のコツを、わかりやすく整理します。
1. 制度の“はざま”にいる人とは?
たとえば、介護保険の対象にならない高齢者、障害福祉サービスを受けるには軽すぎる方、生活困窮まではいかないけれど家計が不安定な世帯――。
そうした方々は、どの制度にも完全には当てはまらず、「支援が届きにくい人」になりがちです。
こうしたときに大切なのが、「断らない相談」の姿勢です。
最初から「それはうちの担当ではありません」と線を引かず、まず話を聴き、生活の全体像を一緒に整理していくこと。
たとえば、
- 日中ひとりで過ごす時間が長く、不安を抱える高齢者には「通いの場」や「見守り活動」を紹介する。
- 家計が厳しい家庭には、フードバンクや地域食堂など地域資源をつなぐ。
- 家族関係に悩む方には、民生委員や地域包括支援センターに橋渡しする。
“小さな支援の糸口を切らさない”ことが、制度のすき間を埋める第一歩です。
2. 複合課題のあるケースでは「支援ルートの設計」を
高齢・障害・生活困窮・子育て――こうした複数の課題が重なるケースは、ひとつの制度だけでは支えきれません。
支援がバラバラにならないように、地域では「支援ルート(支援の道筋)」を設計していくことが大切です。
たとえば、
- 健康や介護の問題 → 地域包括支援センター
- 就労や家計の問題 → 生活困窮者自立支援制度
- 住まいの不安 → 住宅確保要配慮者支援制度
- 医療・通院 → 訪問看護・訪問診療
こうした制度を“線でつなぐ”役割を担うのが、社協やコーディネーターの皆さんです。
関係機関を集めてケース会議を開き、「誰が主担当か」「どこまで支援するか」「どんな期限で進めるか」を明確にしていくと、支援の重なりや抜けが減ります。
また、本人の気持ちを大切にしながら、“一緒に考える支援”を心がけましょう。支援のゴールを「制度を使うこと」ではなく、「地域で安心して暮らせること」と捉える視点が大切です。
3. 守秘義務と情報共有のポイント
支援が複数機関にまたがるとき、避けて通れないのが「情報共有」の課題です。
守秘義務を守りながら必要な情報を共有するためには、次の3つを意識しましょう。
- 目的を明確にして、本人に伝える
「どんな目的で、誰に、何を伝えるのか」を説明し、本人や家族の同意を得ることが基本です。 - 共有は“最小限”に
必要な情報だけを共有します。医療情報や住所など個人が特定される内容は、匿名化する工夫も有効です。 - 記録を残す・見直す
いつ・誰と・どんな情報を共有したかを記録し、定期的に見直します。
もし支援内容が変わったら、古い情報を更新し、関係機関に再確認を。
近年では、オンラインツールを使った共有も進んでいますが、アクセス権限の管理やログの記録など、セキュリティ対策も忘れずに行いましょう。
小まとめ
制度と制度の“すき間”を埋めるのは、最前線で住民と向き合う皆さんの「気づき」と「つなぐ力」です。
「この人をどう支えるか」を一人で抱え込まず、地域包括支援センターや社協、行政、NPOなどと協働して“チームで支える”体制を築くことが、支援の漏れを防ぐ最善の方法です。
外部リンク
包括的な支援体制ガイドブック(重層的支援を含む実践ガイド・2024年版)
「断らない相談」「包括支援」の設計に役立つ最新の解説と実践事例が紹介されています。
👉 https://www.mhlw.go.jp/content/houkatsuteki_guidebook.pdf
💡この第5回の記事は、シリーズ全10回の折り返し地点。
次回(第6回)では、「これからの地域コーディネーターに必要なスキルセット」について、現場で使える具体例を交えてご紹介します。