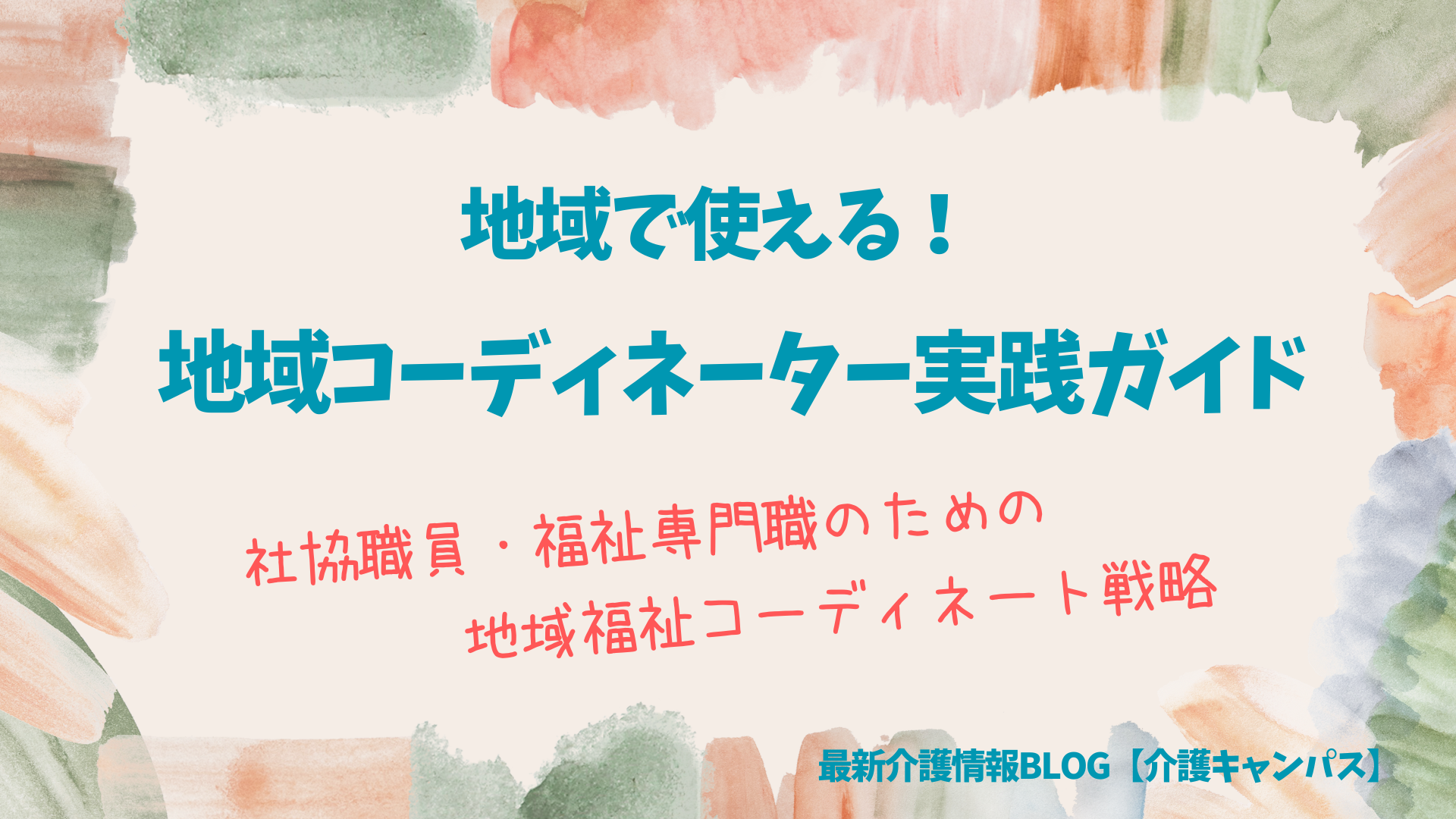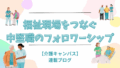(シリーズ:現場で使える!地域コーディネーター実践ガイド)
1. 関係機関連携の立ち上げ手順
地域の課題解決には、社協だけで動くのではなく、多機関連携が欠かせません。
最初の一歩は「顔の見える関係づくり」です。
まずは、地域包括支援センター、民生委員児童委員、医療機関、介護事業所、学校、ボランティア団体など、関係機関のリスト化を行います。リストを作る際には「その機関が持つ強み」を整理しておくと後の協働がスムーズです。
次に、小規模で構わないので「情報交換会」や「勉強会」を開催します。ここで大切なのは、最初から大きな成果を求めないことです。まずは「この人に相談してみよう」と思える関係を築くことを優先します。その後、地域課題に応じてテーマを絞り、協働の場を発展させていきます。
2. 会議運営とファシリテーションの技術
連携を続けるには、定期的な会議の場が必要です。会議が「報告の場」で終わらないようにするには、ファシリテーションの工夫が求められます。
会議を運営するときのポイントは三つです。
- 目的を明確にする:「情報共有」「課題解決の協議」など、会議の目的を冒頭で共有します。
- 発言の機会を均等にする:発言が偏らないよう、司会役がバランスをとります。小グループでの意見交換を挟むと参加意識が高まります。
- 決定事項を必ず整理する:次のアクションが不明確だと、会議が「話し合いだけ」で終わってしまいます。最後に「誰が・いつまでに・何をするか」を明文化しましょう。
また、会議記録はシンプルで構いませんが、合意形成を見える化するために残すことが重要です。
3. 利害調整や摩擦への対応
連携の場では、どうしても利害調整や摩擦が生じます。
「自分の業務が増えるのではないか」「うちの活動の成果が見えにくくなるのではないか」といった不安が背景にあることも少なくありません。
摩擦が生じたときの基本姿勢は、相手の立場を理解し、共通の目標に立ち返ることです。
例えば「高齢者の孤立を防ぐ」という共通課題を確認し合うと、意見の違いが調整しやすくなります。
さらに、相手が得意とする役割を尊重し、役割分担を明確化することも有効です。たとえば、医療機関は健康相談、学校は子どもの居場所づくり、社協は地域全体のコーディネートといった形で強みを活かせば、無理なく協働が続きます。
4. まとめ
ネットワーク構築と多機関連携のマネジメントは、地域コーディネーターにとって最も重要な実務です。
- 関係機関のリスト化と顔の見える関係づくりから始める
- 会議を工夫して参加意識を高め、合意形成を見える化する
- 摩擦が生じたら共通目標に立ち返り、役割を尊重する
これらを繰り返すことで、単なる連携ではなく、地域全体で課題を解決する協働の仕組みが生まれます。
次回は、住民主体の活動をどう立ち上げ、どのように伴走して支えるかについて取り上げます。
関連する公的・実践ガイド
- 重層的支援体制整備事業のガイドブック
多機関による協働事業や仕組みづくりについて行政視点から体系的に解説されています。
厚生労働省 - 地域福祉コーディネーターによるネットワーク会議の実践例
介護支援専門職や多機関連携会議の設計プロセスが具体的に紹介されており、会議設計や実施のヒントになります。
新潟市公式サイト - 生活支援コーディネーターと市民社協の協働体制
武蔵野市の実例として、連携会議や情報交換会議の運営方法を具体的に述べています。
日本リサーチインスティテュート
(筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所・梅沢佳裕)