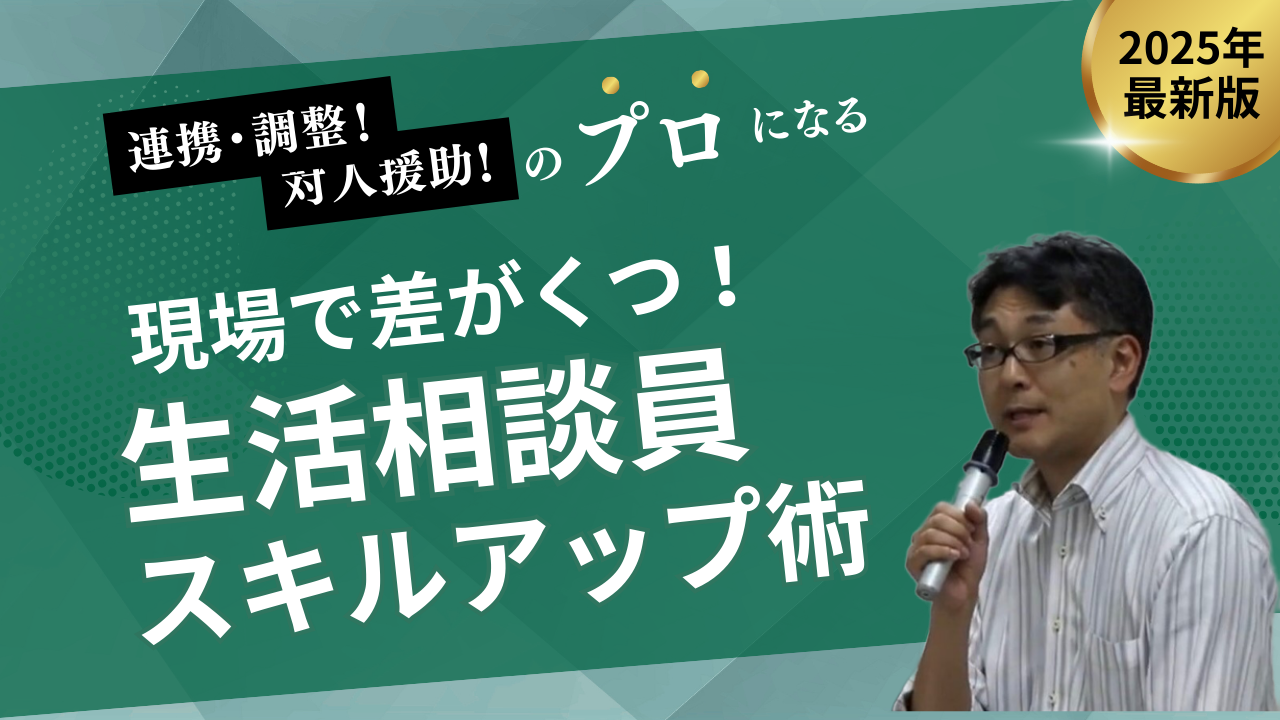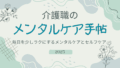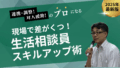皆さまこんにちは。ベラガイア17の梅沢佳裕です。
このたび、新たな連載ブログを【介護キャンパス】にてスタートすることになりました。
テーマは
「現場で差がつく!生活相談員スキルアップ術」
――生活相談員として、もっと成長したい方、専門職としての誇りを持ちたい方へ贈る、全21回のステップアップ連載です。
施設系(特養・老健・有老・ケアハウス)や通所系(デイサービス)など、どの現場にも共通する**「連携・調整・対人支援の実践力」**にフォーカスし、日々の業務に直結する知識とスキルを、豊富な実例・視点から丁寧に解説していきます。
【カテゴリ紹介|7つのスキル領域(A〜G)】
| カテゴリ | スキル領域 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| A | 生活相談員の役割と専門性 | 業務の全体像と専門職としての立ち位置・倫理観を整理します |
| B | 相談援助の実践と記録 | 面接技術やアセスメント、相談記録の具体例と考え方を紹介します |
| C | 家族支援と意思決定支援 | 利用者と家族の関係性、同意形成、意思決定の援助法などを扱います |
| D | 多職種・関係機関との連携・調整 | チームケア・地域連携の中での役割と実践ノウハウを深掘りします |
| E | 制度理解と給付管理の基礎 | 介護保険制度・サービス利用調整・給付管理の実務ポイントを整理します |
| F | 記録と情報共有・報告技術 | 報告・連絡・相談(報連相)の技術や記録の質向上を支援します |
| G | 人間力・ホスピタリティ・成長戦略 | 感受性・マナー・信頼関係の築き方、キャリア形成を応援します |
【全21回 連載構成】
(各回は順不同で公開される可能性があります)
A. 生活相談員の役割と専門性
- 生活相談員とは何者か? ― 役割・機能・期待される姿とは
- 制度上の「人員配置要件」から読み解く本来業務とは
- 生活相談員とソーシャルワーカーの違いと共通点
B. 相談援助の実践と記録
- 傾聴と受容の基本 ― 面接技法のベースを学ぶ
- 「相談を受ける」とは? 課題の聴き取りとアセスメント
- 相談記録・面接記録 ― 書き方と実例から学ぶ実践術
C. 家族支援と意思決定支援
- 同意形成の壁 ― 家族支援の難しさと向き合う
- 意思決定支援と「その人らしい選択」をどう支えるか
- 家族の抱える葛藤・罪悪感にどう寄り添うか
D. 多職種・関係機関との連携・調整
- 連携・調整の基本 ― チームケアを動かす「つなぎ役」
- 担当者会議の進め方と記録のポイント
- 地域とのつながり ― 地域包括・医療・他機関連携の実践法
E. 制度理解と給付管理の基礎
- 介護保険の仕組みと利用調整 ― サービス担当者会議を活かす
- 給付管理・報酬請求の基礎 ― ケアマネとの役割分担
- 介護報酬改定に対応する視点 ― 相談員の立場で読み解く
F. 記録と情報共有・報告技術
- 報告・連絡・相談 ― 報連相で信頼される相談員になる
- 申し送り・カンファレンス ― 情報共有の工夫と注意点
- 記録の質を高める ― 法的視点と「書き残す力」
G. 人間力・ホスピタリティ・成長戦略
- 信頼関係の築き方 ― 「安心感」と「人間味」を持つ
- クレーム対応・困難事例への対処 ― 心が折れない対応術
- 生活相談員として成長し続ける ― 学びとネットワークの活かし方
【こんな方におすすめ】
- 現場で相談員としてもっと力をつけたい!
- 役割が曖昧で悩んでいる…
- 新人〜中堅、ベテランでももう一度基礎を見直したい!
- 他職種との連携に不安がある
- 家族支援や意思決定支援に難しさを感じる
🔗 記事は順次【介護キャンパス】にて公開予定!
各記事へのリンクやまとめページも随時更新します。
現場に役立つ保存版スキル集として、ぜひご期待ください。