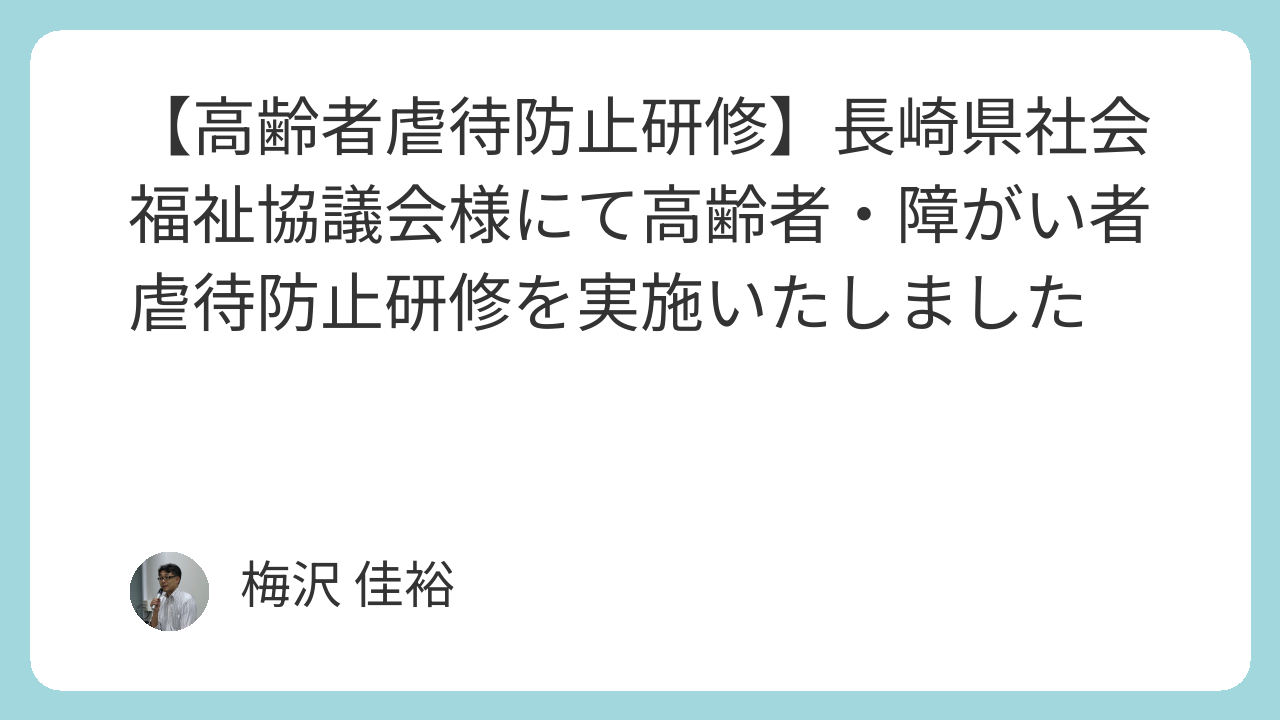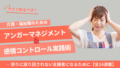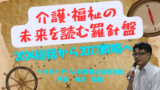皆さま、こんにちは。ベラガイア17の梅沢佳裕です。
このたび、長崎県社会福祉協議会様よりご依頼をいただき、「虐待防止〈高齢者・障がい者〉応用編」研修の講師を務めさせていただきました。本研修はオンライン形式で実施され、多くの施設職員や関係機関の方々にご参加いただきました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.研修概要
■テーマ:虐待防止<高齢者・障がい者>応用編
■開催日時:2025年8月21日(木)13:30~16:30
■研修場所:長崎県社会福祉協議会 ながさきのふくし(オンライン研修)
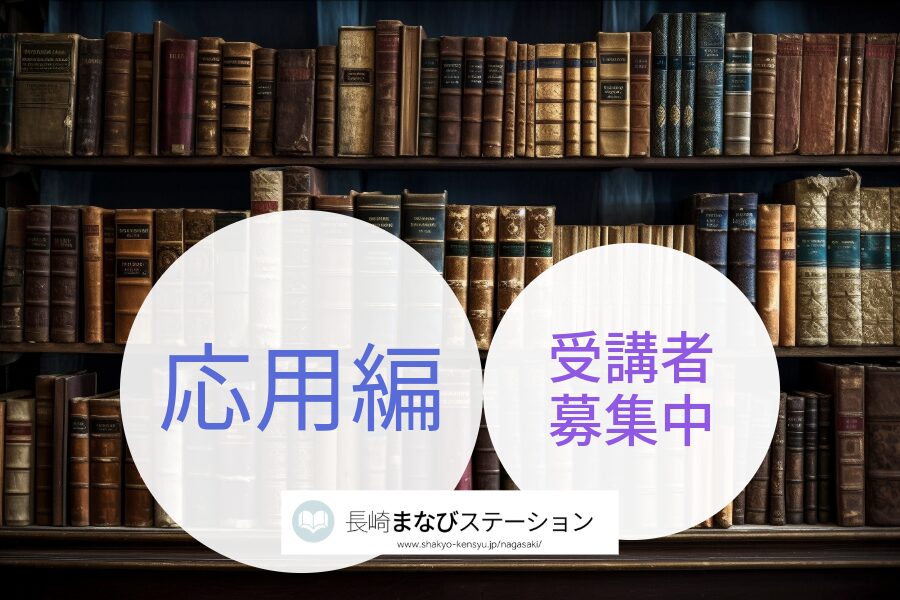
●長崎まなびステーション
【研修プログラム】
- 講義①:制度改定と虐待防止関連動向
- 講義②:委員会活動と連携体制づくり
- ワーク①:自施設の委員会体制・役割を点検する
- 講義③:虐待防止指針整備と身体拘束ゼロの取組み
- ワーク②:その時、職場はどう動いたか?虐待発生後の対応フローをたどる
- 講義④:虐待と身体拘束―“防止の鍵”
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.研修の様子
今回の応用編は、制度改定の最新動向を押さえるだけでなく、現場で実効性を持つ委員会活動や体制整備をいかに行うかに重点を置いた内容となりました。冒頭の講義①では、令和6年度の制度改定に伴う虐待防止関連のポイントを整理し、実務に直結する形で理解していただきました。虐待防止委員会の設置や定期研修の義務化といった要件に加え、単なる形骸化を防ぐために「どう現場に届かせるか」という視点を強調しました。
続く講義②では、虐待防止委員会の5つの役割を中心に、体制づくりと連携の在り方を解説しました。委員会が単なる形式的な会議にならないよう、日常のケアや職員研修へつなげる方法を具体的に提示し、参加者からも「委員会の機能を見直したい」といった声が多く寄せられました。ワーク①では、自施設の委員会体制や役割を点検し、実際にどのような課題があるのかを共有する場となり、各事業所のリアルな声を聴くことができました。
講義③では、虐待防止指針の整備と身体拘束ゼロへの取組みについて取り上げました。単なる規則の整備ではなく、現場で「使える仕組み」にすることが重要であることを強調しました。フローチャートやマニュアルの活用例を交えながら、曖昧な判断を避け、迷わず動ける体制づくりについて具体的な工夫をお伝えしました。さらにワーク②では、虐待が実際に発生したケースを想定し、委員会や管理職、現場職員それぞれがどう動くかをチームで検討しました。参加者の皆さんは真剣に意見を交わし、発生後の対応フローを実際にシミュレーションすることで、自施設に戻った際のイメージを深められた様子でした。
最後の講義④では、「制度だけでは防げない虐待防止」の視点から、現場の判断のゆらぎや虐待と不適切ケアのグラデーションの捉え方を取り上げました。小さな違和感や職員のストレスを早期に共有できる職場風土づくりが、虐待や身体拘束を未然に防ぐ鍵となることを強調しました。
今回の研修を通じて、多くの参加者が「気づきを組織全体で支え合う重要性」を実感されていました。虐待防止は制度やマニュアルの遵守にとどまらず、日々のケアの積み重ねや、チームとしての関係性の質に大きく左右されます。私自身も、現場の方々の真剣な学びの姿勢に触れ、今後の研修にさらに活かしていきたいと感じています。ありがとうございました。