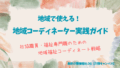介護や福祉の現場では、「転倒を防ぐため」「事故を減らすため」という目的で、利用者の動きを制限する対応を取ることがあります。
しかし、それが身体拘束にあたる場合、本人の尊厳や自由を奪うだけでなく、身体や心、そして支援する職員自身にも深刻な影響をもたらします。
今回は、「身体拘束がもたらすリスク」を利用者と職員の両面から整理し、現場で考えるべき視点を丁寧に解説します。
1.身体拘束が利用者にもたらす影響とは
身体拘束は、見た目には「安全な対応」に見えるかもしれません。しかし実際には、身体的な機能の低下や心のダメージを引き起こす可能性があります。特に高齢者や障がいのある方は、その影響を受けやすい立場にあります。
● 身体的な影響
身体拘束を行うと、まず「動くこと」が制限されます。すると、筋肉や関節を使う機会が減り、数日でも筋力が落ちてしまいます。長期間に及ぶと、立ち上がる力や歩く力が失われ、結果的に介護度が上がることにもつながります。
また、同じ姿勢のままで過ごす時間が長くなることで、褥瘡(じょくそう)や肺炎が発生しやすくなります。動かないことで体の循環が悪くなり、栄養や酸素が行き届きにくくなるのです。さらに、ベッド柵やベルトが逆に転倒時の外傷を重くしてしまうケースもあります。
このように、身体拘束は「安全」のつもりが、結果的に新たな危険を生む行為になりかねません。
● 心理的な影響
身体拘束は、本人の「自由」を奪う行為です。たとえ短時間であっても、「なぜ動けないのか」「なぜ止められるのか」が理解できない状況では、恐怖・怒り・不安・屈辱といった強い感情が生まれます。
特に認知症の方や、意思をうまく伝えられない障がいのある方は、「何か悪いことをしたのではないか」「見張られているのではないか」と感じ、心理的な混乱や拒否行動が増える傾向にあります。結果として、興奮・暴言・介護拒否などの行動が強まり、支援がより難しくなってしまいます。
また、障がいのある方の中には、過去に入院や隔離を経験した人もいます。そのような方にとって身体拘束は、‶過去の恐怖体験を思い出させるきっかけ(トラウマ)”になり、信頼関係を壊す原因となります。
つまり、身体拘束は「その場の安全」を得る代わりに、「長期的な安心」を失う行為でもあるのです。
2.法的なリスク ― 現場での誤解を防ぐために
身体拘束は、法律や制度上も厳しく制限されています。
「必要だから仕方ない」「安全のためだから大丈夫」という感覚で行うと、法令違反や虐待行為に該当するおそれがあります。
介護保険制度においては、各サービスの運営基準(厚生労働省令)で「緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない」と定められています。
これは特別養護老人ホームや介護老人保健施設だけでなく、訪問介護や通所介護など、あらゆる介護サービスに共通して適用される基本原則です。
また、高齢者虐待防止法では、正当な理由のない身体拘束は「身体的虐待」とみなされる可能性があるとされています。
さらに、障害者虐待防止法(第2条第7項第1号)では、明確に「正当な理由なく障害者の身体を拘束することは身体的虐待である」と定義されています。
つまり、身体拘束は「禁止」が基本であり、どうしてもやむを得ない場合に限り、以下の3つの条件(いわゆる“三要件”)をすべて満たす場合のみ認められます。
- 切迫性:本人や他者に生命・身体への危険が迫っていること
- 非代替性:他の方法では代わりがきかないこと
- 一時性:必要最小限の時間に限ること
これらを満たしていない身体拘束は、たとえ善意であっても違法・虐待と判断される可能性があります。また、実施した場合には、「なぜ必要だったのか」「どのくらいの時間行ったのか」「本人の状態はどうだったか」を記録し、委員会で検証・再発防止策を検討することが義務付けられています。
(参考:厚生労働省「身体拘束廃止・防止の手引き」)
3.職員への影響 ― 心の負担と現場のリスク
身体拘束は、利用者だけでなく職員にも重い影響を与えます。
「事故を防ぎたい」「周囲の安全を守りたい」と思って取った行動が、後に自分を苦しめることも少なくありません。
まず生じやすいのが倫理的な葛藤です。
「安全を守るためにやったことが、本当に良かったのだろうか」「他に方法はなかったのではないか」という迷いや後悔が残ると、心の疲労が蓄積し、バーンアウト(燃え尽き)につながることもあります。また、チーム内で意見が割れ、「あの対応は正しかったのか」と議論がこじれると、職場の雰囲気も悪化します。
さらに、身体拘束を行うと、必ず業務負担が増えます。観察記録や説明対応、解除後の報告など、細かな手続きが求められます。加えて、拘束によって利用者の不安や不穏が高まると、ナースコールや声かけの回数が増え、職員の労力が増大します。結果として「人手が足りないから拘束する」という悪循環に陥りやすくなるのです。
小まとめ:身体拘束は“安全”ではなく“リスク”を伴う行為
身体拘束は、「安全のため」という善意から行われることが多い一方で、利用者の心身を弱らせ、職員の心にも負担を与える行為です。
短期的な安全よりも、長期的な安心と信頼関係を守る視点が求められます。
大切なのは、次の3つの意識です。
- 本当に必要かどうかをチームで話し合う
- 代替策(声かけ・見守り・環境整備)を優先する
- 身体拘束を「特別な例外」として扱う文化を定着させる
身体拘束をなくす取り組みは、誰か1人の努力ではなく、組織全体の姿勢の問題です。
「安全」と「尊厳」を両立させる支援体制を築くことこそが、私たち介護・福祉職の使命です。
次回は、三要件の理解と適用 ― やむを得ない場合の基準について具体的に解説します。