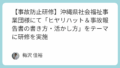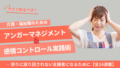介護や福祉の現場で最も恐ろしいのは、「気づかないうちに虐待が進んでしまう」ことです。虐待はある日突然起こるのではなく、必ず小さな“サイン”が前触れとして現れます。ところが、そのサインは「高齢だから仕方ない」「障害の特性だから」と見過ごされやすいのが実情です。
今回は、高齢者サービス・障害者サービスの両方で共通する“いつもと違う”に気づく視点を解説し、虐待を未然に防ぐための実務に役立つチェック方法をご紹介します。
1.高齢者サービスにおける虐待の兆候
高齢者施設や在宅介護では、身体や心理の変化が虐待のシグナルとして現れることがあります。
- 体調の変化
- 食欲低下や水分摂取量の急減
- 急な体重減少、脱水の兆候
- 繰り返し起こる転倒やあざ
- 心理の変化
- 表情の消失や笑顔の減少
- 特定の職員や時間帯を避ける行動
- 「ここにいたくない」といった拒否発言
例えば、ある特養ホームで「普段はよく話す利用者が急に無口になった」という事例がありました。調べてみると、夜勤時に対応する職員の声かけが乱暴になっていたことが背景にありました。こうした小さな変化を“見逃さない目”が虐待防止の第一歩です。
2.障害者サービスにおける虐待の兆候
障害者支援の現場では、特性に応じたサインが現れます。とくに発達障害や知的障害を持つ方では、虐待や不適切ケアによるストレスが行動変化として現れることが多いです。
- 行動の変化
- パニックの頻発や自傷行為の増加
- 特定の職員を回避する行動
- 予定変更や声かけに過敏な反応を示す
- 発達特性に基づくサイン
- 感覚過敏による拒否反応(触られると強く嫌がる等)
- 言葉で説明できない代わりに、問題行動として現れる
あるグループホームでは、利用者が夜間だけ激しいパニックを起こす事例がありました。調査すると、夜勤者が「うるさいから黙って」と強い口調で叱っていたことが判明しました。本人は言葉で訴えられず、行動でSOSを示していたのです。
3.“いつもと違う”を気づくための観察ポイント
虐待の兆候は、一見すると日常の変化に見えるため、意識的に観察しなければ見落とされます。以下の観点を現場で意識してください。
- 身体面:あざ・体重減少・脱水・不衛生な状態
- 心理面:表情が乏しい・不安そう・拒否発言
- 行動面:急な暴言・問題行動の増加・特定の職員回避
- 生活習慣面:急な食欲低下・排泄失敗の増加・睡眠障害
こうした観察は「昨日と今日の違い」「この職員のときと他職員のときの違い」に着目することがポイントです。
4.チェックリストと初動対応
気づきを確実に行動につなげるには、チェックリストの活用と初動対応の明確化が不可欠です。
チェックリスト活用例
- 表情や言動の変化を日ごとに確認
- 食事・排泄・睡眠など基本生活リズムを数値化して記録
- 「嫌がっている・避けている」サインを簡単にチェックできる欄を設ける
初動対応のステップ
- 気づきを記録:「〇〇時、食事を拒否、表情なし」など事実のみを記録
- 上司や虐待防止委員に報告:小さなことでも“声に出す”
- チームで共有:ケース会議や申し送りで早期対応
- 必要に応じ通報や外部相談:市町村や第三者機関に速やかに連絡
5.“気づく力”をチームで育てる
虐待の兆候は、一人の職員の目だけでは限界があります。
- 朝礼や終礼で「気になること」を短時間で共有する
- 「些細な変化でも書き残す」文化を育てる
- 新人職員にはベテランが観察ポイントを教える
こうした仕組みが“見逃しゼロ”を可能にします。
まとめ ― 小さな違和感を見逃さない
高齢者サービスでも障害者サービスでも、虐待は必ず“サイン”を発しています。それは体調の変化、表情の変化、行動の変化といった「いつもと違う」姿です。
その小さな違和感を「年のせい」「特性だから」と片づけず、記録・報告・共有に結びつけること。これが虐待防止の実践的な第一歩です。
次回(第3回)は、現場でよくある“不適切ケアと虐待の境界線”について、具体的事例を交えながら解説します。