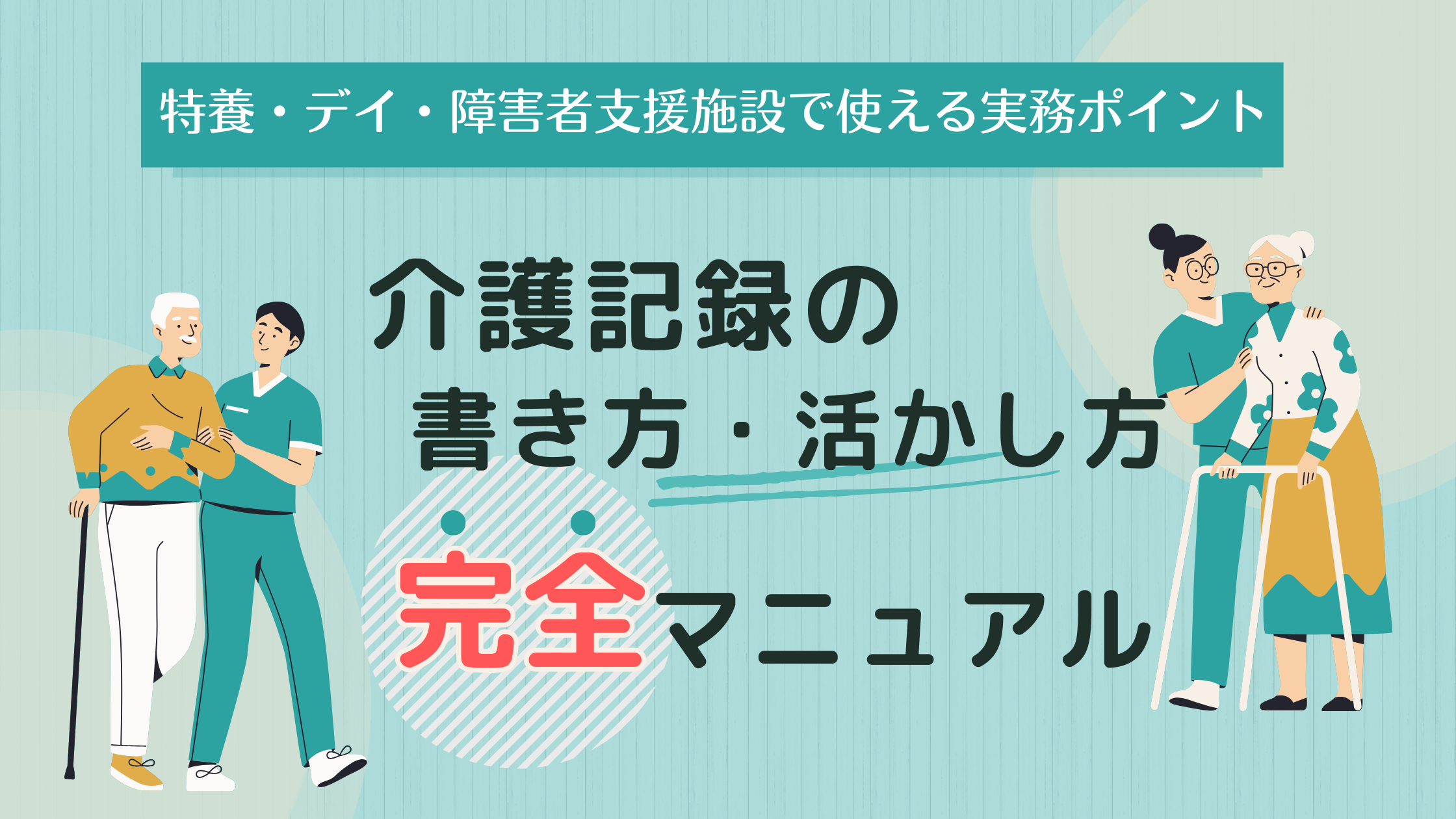介護・福祉の現場で働く皆さん、こんにちは。
前回までは「怒りの正体」や「怒りを生みやすい思考のクセ」についてお伝えしました。
今回は、現場で即実践できる呼吸法と身体の使い方を活用した、怒りの感情コントロール方法をご紹介します。
日々のケア業務では、予期せぬ出来事や相手の言動に感情が揺さぶられる瞬間が訪れます。
そんなとき、頭で「落ち着こう」と思っても、心と身体はなかなか追いつきません。
実は、怒りを鎮める第一歩は「思考」ではなく、「身体」からのアプローチが効果的なのです。
1.怒りを鎮めるには「身体から入る」のが早い理由
怒りやストレスを感じると、心拍数が上がり、呼吸が浅く早くなります。
この状態では、脳が「闘うか逃げるか」のモードに入り、冷静な判断が難しくなります。
そこで、意図的に呼吸や姿勢を整えることで、副交感神経が働き、心身が落ち着きやすくなります。
介護・福祉職は、緊張状態が長く続くと業務効率や判断力にも影響します。
だからこそ、現場で即できる身体アプローチが役立ちます。
2.現場でできる3つの呼吸法
① 腹式呼吸(お腹を膨らませる呼吸)
- 息を鼻からゆっくり吸い込み、お腹をふくらませます。
- 息を口から細く長く吐き、お腹をへこませます。
- これを5回繰り返すだけで心拍数が安定し、怒りの高ぶりが和らぎます。
ポイント:肩を上下させず、お腹だけを動かすイメージで。
② 4-7-8呼吸法
- 鼻から4秒かけて吸う
- 息を止めて7秒キープ
- 口から8秒かけて吐く
この方法は、瞬間的な怒りや不安を鎮めるのに有効です。
③ ため息+脱力呼吸
- 大きく息を吸い、口から「はぁ〜」と吐きながら肩の力を抜く
- 同時に背中や首の緊張も解放
- 1回のため息でも、自律神経が切り替わりやすくなります。
3.身体の使い方で怒りを和らげる
怒りや緊張は筋肉に現れます。特に首・肩・背中は固くなりやすく、呼吸も浅くなります。
そこで、短時間でできる緊張リリース法をご紹介します。
① 首回しストレッチ
- 息を吐きながら首をゆっくり回す(前→横→後ろ→横)
- 左右3回ずつ
- 血流が促され、脳への酸素供給が増えます。
② 肩甲骨ほぐし
- 両肩を耳に近づけるように上げ、ストンと落とす
- 肩を前回し・後ろ回しで各5回
- 肩の緊張が取れると呼吸が深くなります。
③ 背伸び+脱力
- 両手を上に伸ばし、全身をぐーっと引き上げる
- そのまま息を吐きながら手を下ろし、全身の力を抜く
4.「6秒ルール」と組み合わせると効果倍増
アンガーマネジメントの基本に「怒りのピークは6秒」という考えがあります。
この6秒をやり過ごすために、呼吸法やストレッチを組み合わせると、衝動的な言動を防げます。
例:
- イラッとしたら、腹式呼吸を2〜3回
- ため息+肩回しで6秒経過
- その後に言葉を選んで対応
これだけで、感情的な反応がかなり減ります。
■6秒ルール(衝動のコントロール)これは日本アンガーマネジメント協会が提唱している感情のコントロール法です。こちらのブログもご参照ください。https://www.angermanagement.co.jp/blog/68506?utm_source=chatgpt.com
5.介護・福祉現場での実践例
事例:利用者から急な強い言葉を受けた場面
- まずは一歩下がって腹式呼吸
- ため息とともに肩の力を抜く
- 気持ちが落ち着いたら、「今のお気持ちを聞かせていただけますか」とIメッセージで対応
この一連の流れを習慣化することで、衝動的な反応が減り、相手との信頼関係も守れます。
まとめ|呼吸と身体は最強の感情コントロールツール
怒りを抑えようと頭だけで頑張るのは限界があります。
身体から心を整えるアプローチは、介護・福祉の現場で即使える、シンプルで効果的な方法です。
次回は、「現場で使える“言葉の選び方”で怒りを和らげる」についてご紹介します。
呼吸・身体・言葉、この3つを組み合わせることで、怒りに振り回されない支援者へと近づけます。