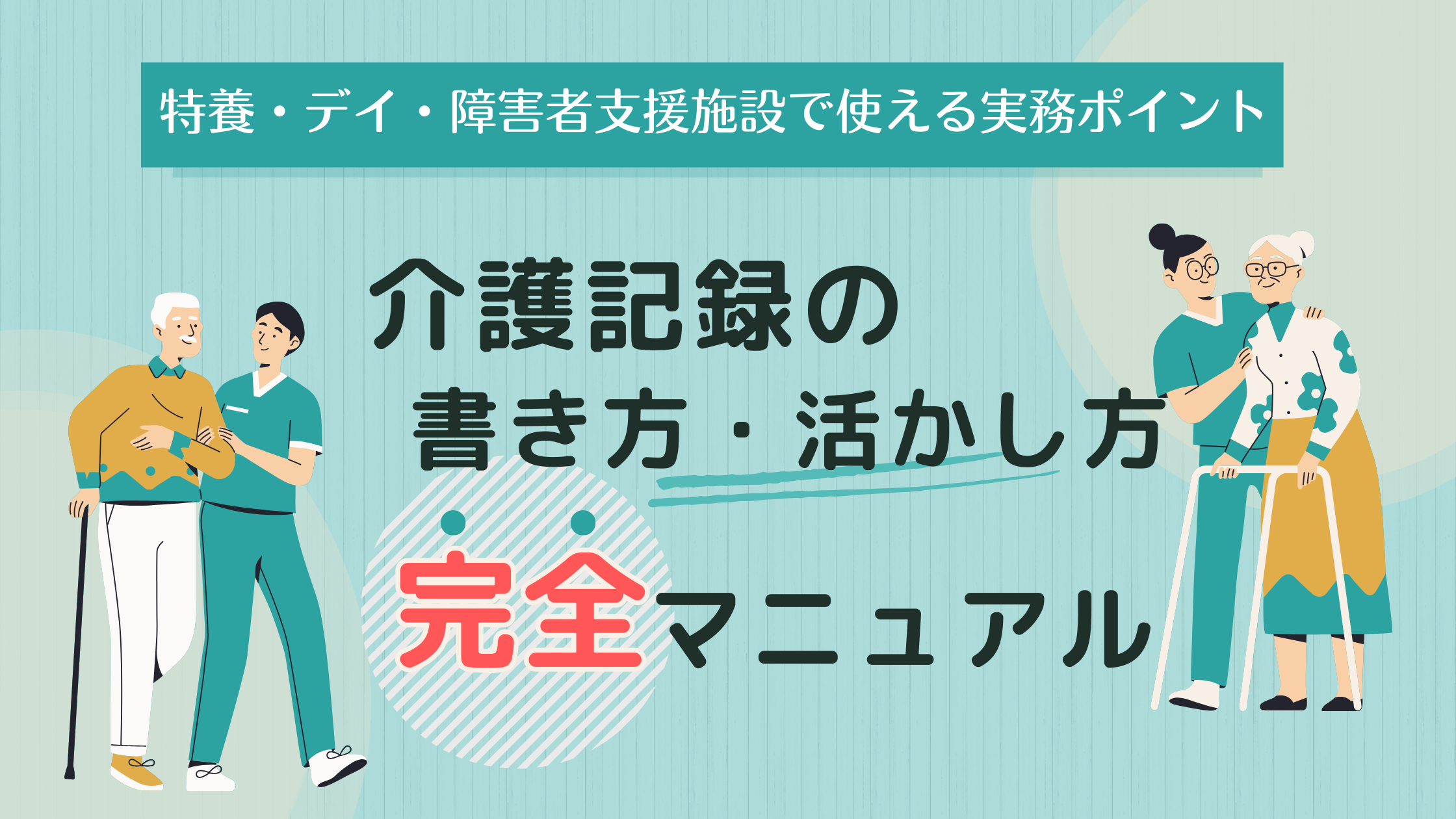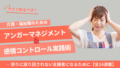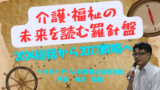食事は、利用者の健康と楽しみを支える大切な時間です。同時に、誤嚥や体調変化のサインが最も現れやすい場面でもあります。だからこそ食事介助の介護記録は、「食べた/食べない」だけで終わらせず、だれが読んでも同じ状況を再現できる形で残すことが重要です。私は研修で「記録はその先の介護の行動指針」とお伝えしています。次に介助へ入る職員が迷わないよう、観察→対応→結果が一目で分かる書き方を整えましょう。
1.食事場面の記録の書き方(新任向け・要点と実例)
合言葉は 「事実→数値→状態→対応→結果」。診断につながるような事や推測は書かない。ありのままに事実を書きます。
① 食形態(提供内容)
見る:常食/一口大/刻み/ミキサー/嚥下食、とろみ濃度、ゼリー化。
書く:その日の確定情報を明記。だから過去形になります。
例:「刻み食+とろみ茶(中等度)」
注意:途中変更は時刻と理由も。「12:20 むせ出現のため看護師指示でとろみ濃度を中等度へ」
② 姿勢・環境(誤嚥予防)
見る:座位角度、足底接地、テーブル高、義歯装着、騒音。
書く:簡潔に。「座位90°・足底接地・義歯装着」
障害特性があれば刺激要因も。「音刺激強で集中低下」
③ 介助方法・ペース・自助具
見る:見守り/部分介助/全介助、どの工程を手伝ったか、ひと口量と間隔、自助具。
書く:部位とペースを具体化。「自力摂取、スプーン1/2杯で20〜30秒間隔」
障害者支援施設では視覚支援やプロンプトの有無も。
④ 摂取量(品目別+飲水総量)
書く:割合+品目。「主食7割・主菜5割・副菜全量・汁物全量、飲水260ml」
コツ:コップ容量をチームで統一(例:1杯=200ml)。
⑤ 所要時間・離席
書く:開始–終了と平常との差、離席回数と時間。
例:「12:10開始〜12:35終了(平常+5分)。中盤に離席1回(2分)」
⑥ 嚥下・咀嚼(リスクの核心)
見る:むせの回数・タイミング、頬袋、湿性嗄声、食塊操作。
書く:事実のみ。「味噌汁後に咳込み2回。以後むせなし」
※“誤嚥”と断定せず、観察→対応→結果で記す。
⑦ 口腔・服薬・バイタルの前後関係
例:「義歯装着、食前薬内服済。食後に口腔ケア実施」
⑧ 情緒・行動・拒否(引き金→対応→結果)
例:「隣席の大声でスプーン停止。席替えで再開し約8割摂取」
⑨ 特記事項(アレルギー・誤配膳など)
例:「誤配膳を疑い提供直前で差し替え。看護師・厨房に即時連絡」
⑩ 対応と結果/引き継ぎ
例:「むせで一時中止→姿勢再調整→再開し計7割。看護師へ報告。次回:一口量1/2で観察」
2.文例集(そのまま使える簡潔フォーマット)
A|特養・デイサービス(高齢者)
12:15〜12:45 昼食(刻み食+とろみ茶:中等度)全量摂取。咀嚼に時間要すも嚥下時むせなし。飲水200ml。座位90°・義歯装着。終始穏やかで隣席者と会話がみられた。
B|障害者支援施設(行動特性の記録)
12:05〜12:35 昼食(常食)約8割。中盤で離席1回(2分)、声かけで再着席し再開。咀嚼・嚥下問題なし。デザートは完食。視覚支援(写真など)の提示で集中維持された。
C|嚥下リスクの手がかり
12:25 味噌汁摂取後に軽い咳込み2回。水分摂取で落ち着く。看護師へ報告し以後観察。湿性嗄声なし、SpO₂98%。
D|拒否・気分変化の把握
3口後に「今日は食べたくない」。咀嚼・嚥下異常なし、体温36.8℃。おやつでゼリー全量。夕食前に再度少量提供予定(看護師了承)した。
E|状況→対応→結果(テンプレ)
12:20〜12:50 ミキサー食7割。むせ1回で一時中止→嚥下姿勢再調整・一口量1/2で再開し完食。看護師報告済。次回も同手順で観察する。
3.迷いやすい表現の置き換え早見表
- 「よく食べた」→「主食7割/副菜全量」
- 「元気そう」→「会話あり・表情良好・中断なし」
- 「むせたかも」→「味噌汁後に咳込み2回。以後むせなし」
- 「落ち着かない」→「離席1回(2分)声かけで再着席」
4.“未来への道しるべ”としての心得
- 曖昧語は使わず、数値・事実で書く。
- 状況→対応→結果を一文の中で完結させる。
- 次回の注意点・指示者を明示して引き継ぐ。
一行の精度が、明日の安全を高めます。記録はその先の介護の行動指針です。
まとめ
- 食事記録は“その先の介護の行動指針”です。次の担当者が迷わないよう、観察→対応→結果が一目で分かる形に整えます。
- 書き方の合言葉は「事実 → 数値 → 状態 → 対応 → 結果」。推測や評価語ではなく、観察事実と数値で記載します。
- 必須の観察項目は、①食形態 ②姿勢・環境 ③介助方法・ペース ④摂取量(品目別+飲水総量)⑤所要時間・離席 ⑥嚥下・咀嚼 ⑦口腔・服薬・バイタル ⑧情緒・行動・拒否 ⑨特記事項 ⑩対応・結果・引き継ぎ、の10点です。
- 一文テンプレ:「12:20〜12:50 刻み食。主食7割・副菜全量・飲水260ml。味噌汁後に咳込み2回→一時中止・姿勢再調整→再開し7割。看護師報告。次回:一口量1/2で観察」。
- 避けたい表現:「よく食べた/変わりなし/元気そう」などの曖昧語は、割合・回数・時刻・所要で言い換えます。
明日からのアクション(3つだけ)
- 単位をそろえる:コップ容量(例:200ml)や摂取量の表記基準をチームで統一します。
- 誤嚥リスクを“見える化”:姿勢・一口量・間隔・むせ回数を必ず数値で残します。
- 引き継ぎを一行で:「誰の指示で/次回どうする」を最後に明記します。
一行の精度が、明日の安全を高めます。記録はその先の介護の行動指針です。