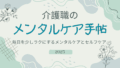~初動対応・面談・支援プランで介護離職を防ぐ~
社員から「親の介護で困っている」と言われたら?
企業の人事・労務担当者にとって、「社員が介護のことで悩んでいる」と相談してくる瞬間は、決して珍しいものではなくなってきました。
2025年以降、団塊世代の高齢化に伴い、介護を担う働き手はさらに増加していくと予測されます。そこで重要なのが、企業がどのように「介護を抱える社員」へ具体的に対応するかです。
今回は、介護に直面した社員に対し、企業が行うべき支援ステップを3つに整理して詳しく解説します。
ステップ①|最初の鍵は「初動対応」:状況把握と安心感の提供
✔ 急がず、慌てず、状況を丁寧にヒアリング
社員が介護の相談を持ちかけてきたとき、最初にやるべきことは「制度の説明」ではありません。まずは事実確認と感情面の受け止めです。
【初動で確認したい主なポイント】
- 介護対象者との関係性(親、義親、配偶者など)
- 介護の内容と頻度(同居・通い、付き添い、見守りなど)
- 要介護認定の取得状況、ケアマネジャーの関与有無
- 現在の勤務と介護の両立状況、困難な点
- 社員自身がどのように働き続けたいと考えているか
社員にとっては「相談するだけでも精一杯」の状態であることが多いため、否定や決めつけをせず、丁寧に聴き取る姿勢が信頼関係の第一歩となります。
ステップ②|「面談」は不安を受け止める対話の場
✔ 制度の“紹介”ではなく、“活用”を導く対話を
面談の目的は、単なる制度説明ではありません。社員の不安や迷いをくみ取り、「この会社でなら続けられる」と思ってもらうことが真のゴールです。
【面談で意識したい視点】
- 仕事と介護を天秤にかける心理状態を理解する
- 「迷惑になるのでは」といった罪悪感を軽減する
- 介護支援制度の柔軟な利用方法を提案する
- 中長期的に働き続けるための選択肢を整理する
また、可能であれば、管理職やチームメンバーとの調整にも踏み込み、制度の利用が浮いてしまわないような配慮も重要です。
ステップ③|「支援プラン」の策定で離職リスクを防ぐ
✔ オーダーメイドの支援計画が必要
介護の内容は人それぞれです。支援プランは画一的なものではなく、社員一人ひとりの状況に応じた“柔軟な設計”が求められます。
【主な支援プランの構成要素】
| 支援項目 | 対応例 |
|---|---|
| 勤務時間の調整 | 時短勤務、フレックス、コアタイム変更など |
| 勤務場所の変更 | 週2回の在宅勤務、一部リモート対応 |
| 業務量の見直し | 非定型業務から定型業務への一時的シフト |
| 休暇制度の活用 | 介護休暇、介護休業、有給の柔軟取得 |
| 外部連携 | 社外相談窓口(EAP)、社労士、ケアマネ紹介 |
特に在宅勤務やフレックス制度の活用は、実際に利用された社員の満足度も高く、離職抑制に有効であるという調査結果もあります。
【事例紹介】介護による退職寸前からのV字回復
製造業に勤務する女性社員(50代)は、母親の要介護認定を受けたことを機に、退職を検討していました。しかし会社側が事情を丁寧に聴き取り、在宅勤務を週3日に変更。業務分担も見直され、本人は「支えられている」と実感。半年後には通常勤務に戻り、今も活躍中です。
→ 制度+対話+柔軟な職場調整がそろえば、介護離職は確実に減らせます。
まとめ|「会社に相談してよかった」と言われる職場に
企業が目指すべきは、「介護を理由に辞めざるを得ない社員」を減らすことです。
そのためには、以下のステップをしっかり押さえることが不可欠です。
- 初動対応で状況把握と感情ケア
- 面談で対話と選択肢の共有
- 支援プランで“働き続けられる環境”を具体化
相談のしやすさ=心理的安全性のある職場が、介護離職を防ぐ企業の条件です。
次回予告:「介護に直面する前」に企業ができることとは?
次回の第4回では、「社員が介護に直面する前」に企業ができる備え、予防的な情報提供、教育研修、社内の仕組み整備について詳しく解説します。