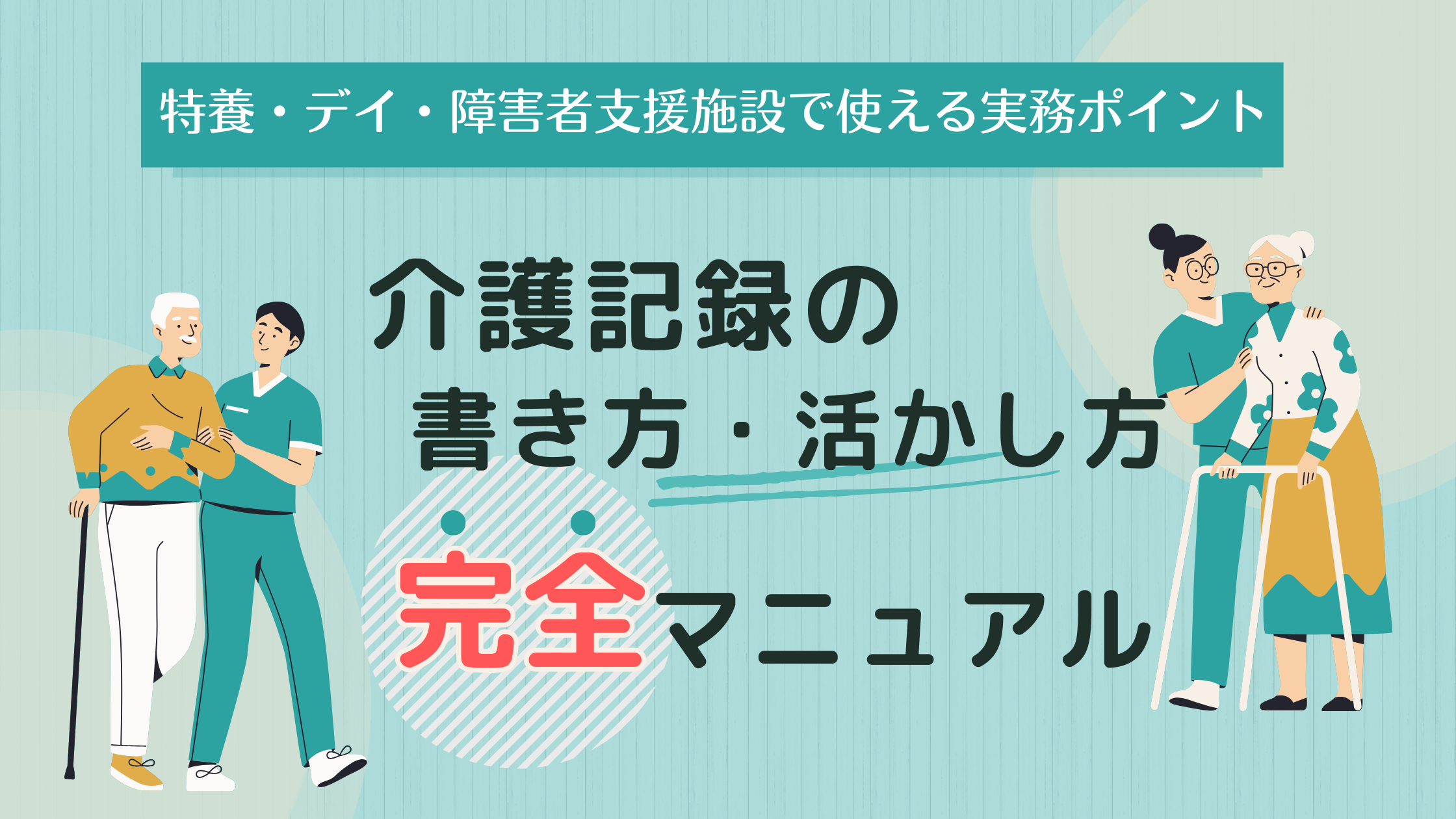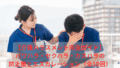1.はじめに ―「加算は取れたのに現場が疲弊」
「せっかく加算を取ったのに、なぜか現場の空気が重い」。
令和6年度介護報酬改定後、とある特養の施設長はそう嘆きました。加算は複数取得し、収益も増えるはずでしたが、蓋を開けると委員会や会議は増え、記録様式は統一されず、監査を前に不安が募るばかり。職員の負担感は高まり、稼働率は横ばい、新人離職率はむしろ上昇しました。
この現象の背景には、「制度要件と日々の業務が一本の線でつながっていない」という共通課題があります。本記事では、改定の政策意図を経営視点で解読し、加算と体制要件の優先順位付け、そして落とし穴を回避するための実務アプローチを示します。
2.R6改定の政策文脈を3分で整理
今回の改定は、単なる加算の追加や要件変更ではありません。国は明確に「人材確保」「科学的介護」「地域包括」という3つの柱を打ち出しました。
人材確保と質向上
処遇改善加算は引き続き重視され、キャリアパスの明確化が要件として強化されました。研修計画や評価制度と結びつけることで、給与だけでなく職員の成長ややりがいにつなげる狙いがあります。
科学的介護(LIFE)とアウトカム志向
LIFEはもはや“提出して終わり”では通用しません。フィードバックを分析し、ケアプランに反映する運用こそが評価の核心となります。アウトカム、すなわち利用者の状態改善や生活の質向上が、今後の加算評価を左右します。
地域包括・連携の強化
医療・リハ・地域包括支援センターとの情報共有や役割分担を明確化し、切れ目ない支援体制を構築することが求められています。ここで重要になるのが、記録様式の標準化と情報共有プロトコルです。
3.経営に効く“実務5領域”総点検
改定対応を収益改善と現場力強化の両立に変えるには、次の5領域の総点検が必須です。
- 加算要件の優先度設計
収益インパクト・実現難易度・監査リスクの3軸で優先順位をつけ、取得すべき加算を選定します。 - 委員会・体制整備
議事録テンプレに目的・KPI・改善提案・次回ToDoを固定欄として組み込み、形式運用を防ぎます。 - 記録・エビデンス運用
監査逆算型の台帳を作成し、証跡の所在・更新頻度・責任者を明確化。 - LIFE/ICT活用
入力動線を短縮し、フィードバックはカンファレンスで必ず議題化。 - 教育・定着
マイクロラーニング+OJTで知識定着を促し、評価制度と連動させます。
4.加算“取りっぱなし”の失敗学
多くの事業所で見られる失敗例は次の通りです。
- 形式運用:委員会や会議は開催しても、改善サイクルが回らない
- 属人化:担当者が不在になると運用が止まる
- 棚卸し不在:取得加算や運用状況を一覧で把握していない
- 様式の乱立:部署ごとに異なるフォーマットで集計不能
- LIFE未活用:提出のみでフィードバックが未読・未反映
これらを防ぐには、″RACI表(責任分担表)”による役割明確化、記録様式の統一、定期的な加算マップの棚卸しが有効です。
RACI表(責任分担表)とは何か
RACI表は、業務やプロジェクトで誰が何をどこまで関わるのかを明確化するためのツールです。
4つの役割の頭文字から成り立っています。
| 項目 | 意味 | 役割の概要 | 実務での例(加算算定業務の場合) |
|---|---|---|---|
| R(Responsible)担当者 | 実際に作業を行う責任者 | 実務を遂行する人 | 加算の必要資料を作成する介護主任 |
| A(Accountable)最終責任者 | 最終的に成果物や結果に責任を持つ人 | 承認・決裁者 | 施設長や管理者 |
| C(Consulted)相談相手 | 専門知識や助言を提供する人 | 双方向のやりとり | 看護師長、事務長 |
| I(Informed)報告先 | 経過や結果を知らされる人 | 一方向の情報共有 | 法人本部、経営会議 |
RACI表の活用ポイント
- 曖昧な責任の押し付け合いを防ぐ
- 欠員や配置替えでも業務継続が可能になる
- 監査時に「誰が説明できるか」が一目でわかる
5.今日からできるミニ改善
5-1.RACIで役割整理
やり方の例
- 対象業務(例:科学的介護推進体制加算の運用)を一つ決める
- 関係者を洗い出す(介護主任、看護師長、事務長、施設長、本部)
- R/A/C/Iの役割を割り当て、表にする
- 職員会議や委員会で共有し、周知する
効果
- 「誰が実務をやるのか」「誰に相談すべきか」が即わかる
- 担当不在時も代行者を決めやすくなる
5-2.会議体のアジェンダ標準化
やり方の例
- すべての委員会や会議で使う共通フォーマットを作成
- 項目例:
- 先月のKPI報告(加算達成率・LIFE提出率)
- 是正計画の進捗確認
- LIFEフィードバック活用報告(改善事例)
- 今月の重点テーマ(虐待防止・感染対策など)
- 次回までのToDoと責任者決定
効果
- 会議のムダが減り、議事録作成も容易になる
- 各委員会の質を横並びで比較・改善できる
5-3.KPIの見える化
やり方の例
- GoogleスプレッドシートやExcelで月次ダッシュボードを作成
- 指標例:加算達成率、LIFE反映率、稼働率、離職率、事故発生率
- 職員が誰でも見られる場所(共有フォルダや掲示板)に設置
効果
数字の変化がすぐわかり、改善活動のモチベーションになるを把握できるようにします。
職員が経営数値に関心を持ちやすくなる
6.まとめ
令和6年度改定は、単なる制度変更ではなく、「現場と経営を同時に動かすための仕組み化」を促す契機です。要件・業務・記録・証跡・KPIを一本の線で結び、現場のやりがいと経営指標を同時に改善できる体制を整えることが、次期改定(令和9年度)に向けた最大の武器になります。
7.次回予告
次回は「加算は“仕組み”で稼ぐ」をテーマに、委員会運用・記録・監査台帳・LIFE活用を一気通貫で設計する具体策をご紹介します。現場の負担を増やさず成果を最大化する導線づくりをお伝えします。