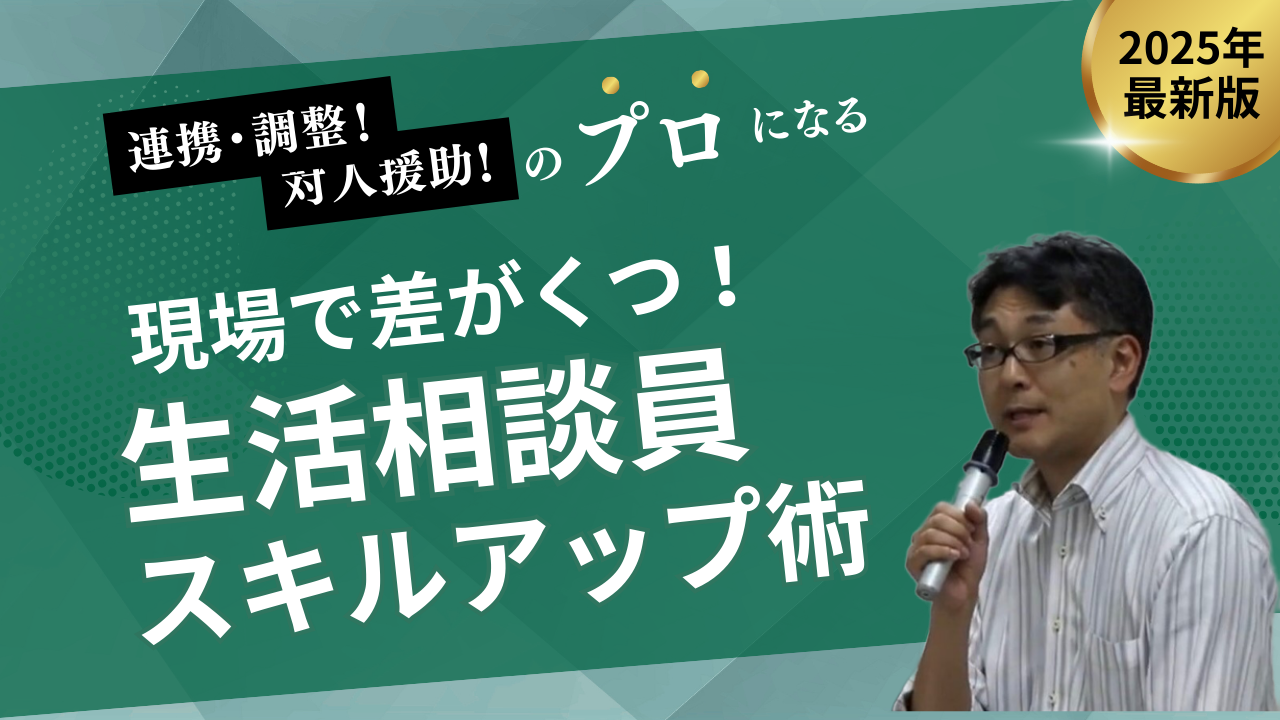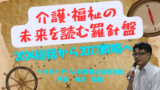→ 家族とのせめぎ合いの中でどう支えるか
介護施設で働く生活相談員が大切にすべき軸は、本人の意向を中心に据えた自己決定支援です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設や有料老人ホームなどの生活施設には、要介護3以上の重度の高齢者が多く入居します。認知症や失語や嚥下障害などにより意思疎通が難しく、本人が自ら選べない場面も少なくありません。しかし「理解できないだろう」と決めつけて支援の手順を省略することは、権利擁護の観点から明確に誤りです。施設は生活の場であるため、医療中心の発想に偏らないよう注意しながら、安全と生活の継続性と生活の質(QOL)を両立させる支援を検討します。
1.「本人の意向を尊重する」とは何を行うことなのか?
本人の意向の尊重とは、言われたことをそのまま実行することではありません。重度であっても、意思を支える工夫を尽くした上で、本人が理解できる範囲で選べる状況を整えることが求められます。相談員はまず、言語情報だけでなく表情や視線や身振りや生活歴に表れるその利用者なりの価値観をていねいに見立てます。その上で、誤解を招きやすい同意と自己決定をきちんと区別します。署名や押印など事務的な対応だけで完結させず、理解の過程と選択の根拠を記録してチームで共有します。
利用者に対しては、要介護(特に重度者等も多く入居されている)であることを前提に支援を組み立てるために、次の4点を基本動作として実践します。
- 情報提供を行い、難しい用語を用いず、短く区切ってゆっくり説明します。写真やピクトグラムや見本などの視覚手がかりを使い、説明の負担を軽減します。
- 理解の確認を行い、うなずきや指差しや「はい」「いいえ」カードなどの代替コミュニケーションで確かめます。時間帯を工夫して、本人が落ち着いて話せる時間に再面接します。
- 選択肢の提示を行い、二択や三択など認知負荷の低い形で提示します。利点と不安点を並べ、どの点なら許容できるかを一緒に検討します。
- 意思の反映を行い、チームの行動計画に落とし込み、見直し日をあらかじめ設定します。記録は事実と憶測を分けて記述し、本人の言葉と反応を明確に残します。
よくある場面として、糖尿病の利用者が「好きなものを食べたい」と希望することがあります。ただ制限してしまうのではなく、生活の質(QOL)向上と健康や安全面の両立を他職種などとも検討します。具体的には、例えばある利用者の誕生会の席で糖尿病の利用者も一緒にケーキを楽しめるよう、事前に一日の総カロリーを調整しておき、気兼ねなく過ごせるように検討するなどです。相談員は、当日の見守り体制や緊急連絡手順なども整えておくことで介護職や他職種が安心して利用者対応に集中できる環境を整えていきます。相談員は、本人・家族・職員の間に立ち、合意形成を図りながら支援が進められるよう働きかけを行う専門職なのです。
本人がどうしても選択できない状況では、本人の推定意思と最善の利益を手がかりに、家族や多職種と協議して方針を固めていきます。その際は、過去の生活歴や好みや大切にしてきた価値観を材料にして、本人ならどう考えるかを丁寧に検討します。結果だけを家族に委ねず、相談員が自己決定を支える過程を大切にして、検討のプロセスを進めていきます。
2.家族とのせめぎ合いを対話に変えるために何を行うのか?
本人の希望と家族の意向が衝突する場面(ズレが生じる場面)では、相談員がどちらかの立場に偏らず、本人を必ず中心に据えながらと家族の意向を傾聴する姿勢を保ちます。以下の5つの手順で話し合いを進めると、対立が協働に変わりやすくなります。
- 傾聴:本人と家族それぞれの気持ちと理由を聴き取ります。家族の負担感や不安感・イライラ・不満など様々な感情を否定せず、ねぎらいの言葉をかけます。
- 事実の可視化:ADL・IADL・既往歴や現病症・本人の主訴・家族関係などさまざな情報をアセスメントします。
- 価値とリスクの並列化:「自己実現したいこと(価値)」と「避けるべきリスク」を検討し、本人にとって大切な時間や活動をケアカンファレンス等で模索します。
- 代替案の検討:できること・できないことの二択ではなく、どれならできる・どこまでできるなど多面的なバリエーションの工夫を凝らしてみます。
- 合意内容の文書化:生活相談員が利用者や家族と向き合い、観察やコミュニケーションから得られた情報は、かならず相談記録に記載し、必要に応じてチームと共有します。施設の指針に沿って本人の生活の方向性が見定まったとしても、時期を見て定期的に意向の変化が無いか把握し直していきます。
小まとめ:重度を前提にしても自己決定支援をあきらめない
生活相談員が行う自己決定支援は、重度化や認知症を理由に縮小してはなりません。意思疎通が困難な利用者にこそ、代替コミュニケーションや選択肢の簡素化(閉じた質問など)や最小制限の原則を用い、権利擁護の視点で「選択できる環境」を整備します。家族との意向の食い違いが生じた場合は、5つの手順に沿い、チームとしての合意形成を継続的に支えます。記録と共有を丁寧に行い、安全と生活の継続性とその利用者なりの生活の質(QOL)の3つを高められる支援を目途とします。
参考リンク:厚生労働省「意思決定支援ガイドライン」
(筆者:ベラガイア17 人材開発総合研究所 梅沢佳裕)