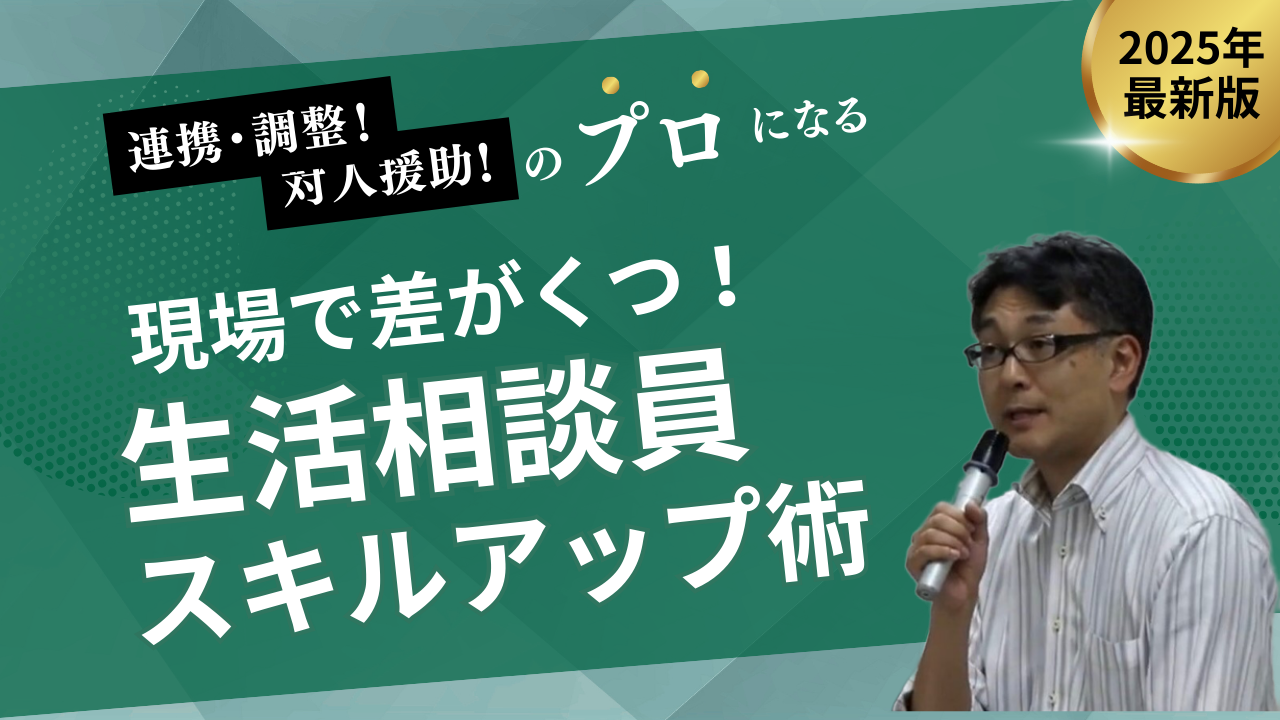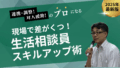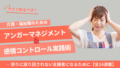―ミクロ・メゾ・マクロを知って、仕事に“軸”をつくる
介護施設における「生活相談員」は、時に“便利屋”のように何でも対応するポジションと思われがちです。しかし本来は、専門職としての役割と機能が明確に存在します。この記事では、**「ソーシャルワークの視点」**を取り入れながら、生活相談員の本質的な仕事の意味と立ち位置を見直します。
1.なぜ「生活相談員=何でも屋」になってしまうのか?
多くの現場で「生活相談員」が担当する業務は多岐にわたります。入退所手続き、家族対応、職員の調整、他職種連携、時には送迎の手伝いや備品購入まで……。
これは、組織内での役割の曖昧さや、制度上の位置づけの弱さが一因です。「生活相談員がやればいいじゃないか」と割り当てられることで、本来担うべき専門性のある支援業務が埋もれてしまうのです。
だからこそ、まずは生活相談員自身が「何をすべきか/すべきでないか」という**職務の軸(スコープ)**を持つことが必要です。
2.「ソーシャルワークの3層構造」で自分の立ち位置を見つける
生活相談員の実務を整理する際、ソーシャルワークの3層構造(ミクロ・メゾ・マクロ)という枠組みが非常に役立ちます。
- ミクロ(個別支援)
→ 利用者一人ひとりの相談対応、生活調整、家族との連携など。 - メゾ(組織内連携)
→ 他職種間の調整、カンファレンスの進行、ケアチームの橋渡しなど。 - マクロ(地域・制度)
→ 行政・他機関との連携、地域資源の開拓、制度情報の発信など。
この3層すべてが「生活相談員の専門性」の一部です。どこに重きを置くかは、施設の機能や個人の経験によって異なりますが、この構造を知ることで仕事の“軸”が定まりやすくなります。
3.“役割の可視化”と“専門性の言語化”が、評価と支援の鍵になる
相談員の仕事は「見えにくい」「成果が測りづらい」と言われがちです。しかし、自らの役割や支援の視点を言語化・構造化できれば、チーム内での理解も深まり、評価や業務改善につながります。
たとえば、以下のように記録や報告の中で、ミクロ・メゾ・マクロの視点を織り交ぜていくことが有効です。
- 「ミクロ視点でAさんの不安に寄り添い、退所後の生活を共に設計した」
- 「メゾの観点から職員間のケア認識のズレを調整した」
- 「マクロ的な視点から、行政との連携を図り在宅支援に橋渡しした」
こうした実践の積み重ねが、**“専門職としての誇り”と“相談員の役割の再評価”**へとつながっていきます。
まとめ:生活相談員に必要なのは「軸」と「言葉」
“何でも屋”から脱却するためには、まず**「自分の専門性はどこにあるのか」を認識すること。そして、その専門性をチームや他職種に言葉で伝える力**を持つことです。
その第一歩として、「ソーシャルワークの3層構造(ミクロ・メゾ・マクロ)」を自分の仕事に当てはめてみてください。見えていなかった支援の価値が浮かび上がってくるはずです。
次回予告
第2回:「本人の意志を尊重するって、どういうこと?―自己決定支援のリアル」
→ 「同意=自己決定」ではない!?現場で起こりがちな“ズレ”と向き合うポイントをお届けします。