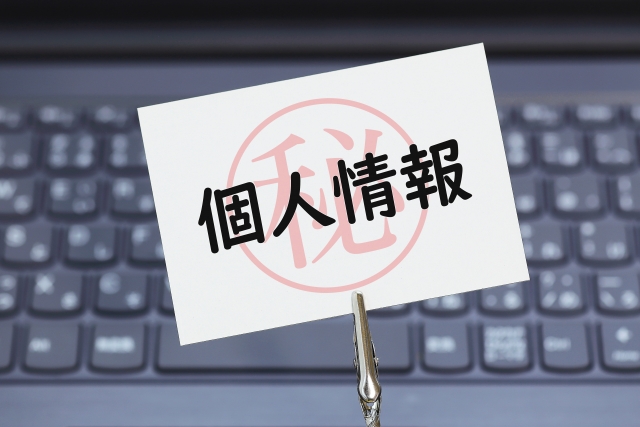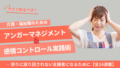皆さま こんにちは ベラガイア17の梅沢佳裕です。
今回の研修は、長崎県社会福祉協議会様から研修のご依頼を頂き、講師を務めさせて頂きました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.研修概要
■テーマ:【法定研修】プライバシー保護と倫理・法令遵守(基礎編)
■開催日時:2025年8月8日(金)13:30~16:30
■研修場所:長崎県社会福祉協議会(オンライン研修)
【研修プログラム】
⦁講義①:個人情報とプライバシーの基礎知識
⦁ワーク①:事例検討(グループワーク)
⦁講義②:守秘義務と倫理的配慮
⦁ワーク②:ヒヤリ体験から学ぶ(個人→共有)
⦁講義③:法令遵守とコンプライアンスの基本
⦁講義④:専門職に求められる倫理観と責任
⦁ワーク③:私たちに求められる行動とは(グループワーク)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.研修の様子
本研修は、福祉現場で働く職員が日常業務の中で必ず直面する「個人情報」「守秘義務」「倫理的配慮」「法令遵守」について、基礎から実践まで体系的に学ぶことを目的としています。
講義①では、個人情報とプライバシーの違いや範囲、取り扱いの基本原則を整理し、実際の現場で注意すべきポイントを解説しました。続くワーク①では、参加者がグループに分かれ、提示された事例をもとに「内部掲示物の機関紙への転載と外部発信」を議論。現場感覚に即した活発な意見交換が行われました。
講義②では、守秘義務の法的根拠や倫理的な背景を確認し、本人同意があっても提供を控えるべきケースなど“グレーゾーン”の判断基準を提示。ワーク②では、受講者が自身のヒヤリ体験を共有し、「なぜ起こったのか」「どう防ぐか」を深掘りしました。
講義③では、法令遵守とコンプライアンスの基礎を押さえ、介護保険法や個人情報保護法などの関連法規を整理。さらに講義④では、専門職に求められる倫理観と責任を、信頼関係の構築という観点から解説しました。
最後のワーク③では、研修全体を振り返り、実際の現場で起こりうる“判断に迷う場面”を題材にして、意見交換を行い、各グループが発表。その後全体共有を行いました。
今回の研修を通じて、法令や倫理の知識を“守るべきルール”として理解するだけでなく、「なぜそれが必要なのか」を自分事として考える重要性を改めて感じていただけたと思います。今後も、現場で活きる研修をお届けしてまいります。
【Q&A補足資料】の解説
研修終了後の質疑応答の際に、私の方から資料を共有し追加説明を行いました。退室された方もおられましたので、こちらにリマインドさせて頂きます。Q&A形式で掲載していきます。
Q1:守秘義務と情報共有は矛盾しませんか?
A:矛盾ではなく、目的と範囲の違いです。
- 守秘義務:第三者に不必要な情報を渡さない義務
→ 利用者・家族の信頼と権利を守るための基本ルール - 情報共有:業務遂行上、必要な関係者に必要最小限の情報を伝えること
→ ケアの質・安全・継続性を確保するための行為
実践のポイント
- 誰に:業務上関わる関係者だけに
- 何を:目的に必要な情報だけに
- どこまで:過剰な詳細は避ける
解説:秘義務は「情報を守る壁」であり、情報共有は「ケアをつなぐ橋」です。橋は必要なところにだけ架け、不要な部分には伸ばさないことが大切です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q2:本人同意を得ても“やめたほうがよい”情報提供はありますか?
A:あります。同意があっても将来的な不利益やトラブルが予測される情報は、専門職として慎重に扱うべきです。
控えるべき高リスク情報の例
- 財産状況(預金額、不動産など)
- 家族関係の詳細(確執、離婚歴、疎遠など)
- 過去の事件・事故や病歴(精神疾患、感染症など)
- 他者への批判や評価
理由
- 公開後に取り消すことは不可能
- 同意時は了承しても、後に撤回を求められる場合がある
- 関係者間の信頼や安全を損なう可能性
安全策
- 提供の必要性を再確認する(代替手段はないか)
- 同意書に範囲・期間・撤回方法を明記する
- 個人が特定されにくい表現に置き換える
解説:同意は「免罪符」ではなく「入口」にすぎません。専門職には“予測してあえて出さない判断”も求められます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q3:災害時や感染症発生時の情報提供はどう扱う?
A:緊急時は、命と安全を守るために必要な範囲での情報提供が優先されます。
1. 災害時(地震・洪水など)
- 行方不明者の捜索や避難誘導のため、氏名・安否・健康状態などを行政や救助機関に提供可
- ただし、報道機関や不特定多数には最低限の情報(安否のみなど)にとどめる
2. 感染症発生時(インフルエンザ、COVID-19等)
- 感染拡大防止のため、必要な関係者(医療機関、保健所、濃厚接触の可能性がある利用者や職員)に情報提供
- 個人名の公表は、感染拡大防止に不可欠な場合に限定し、発表範囲を最小化
3. 共通ポイント
- 「誰に」「何を」「なぜ」伝えるかを明確化
- 緊急性が去った後は情報提供を終了する
- 記録に残し、事後に検証可能な状態にする
解説:平時は守秘義務が優先されますが、緊急時は「生命・安全の確保」という上位目的が優先されます。