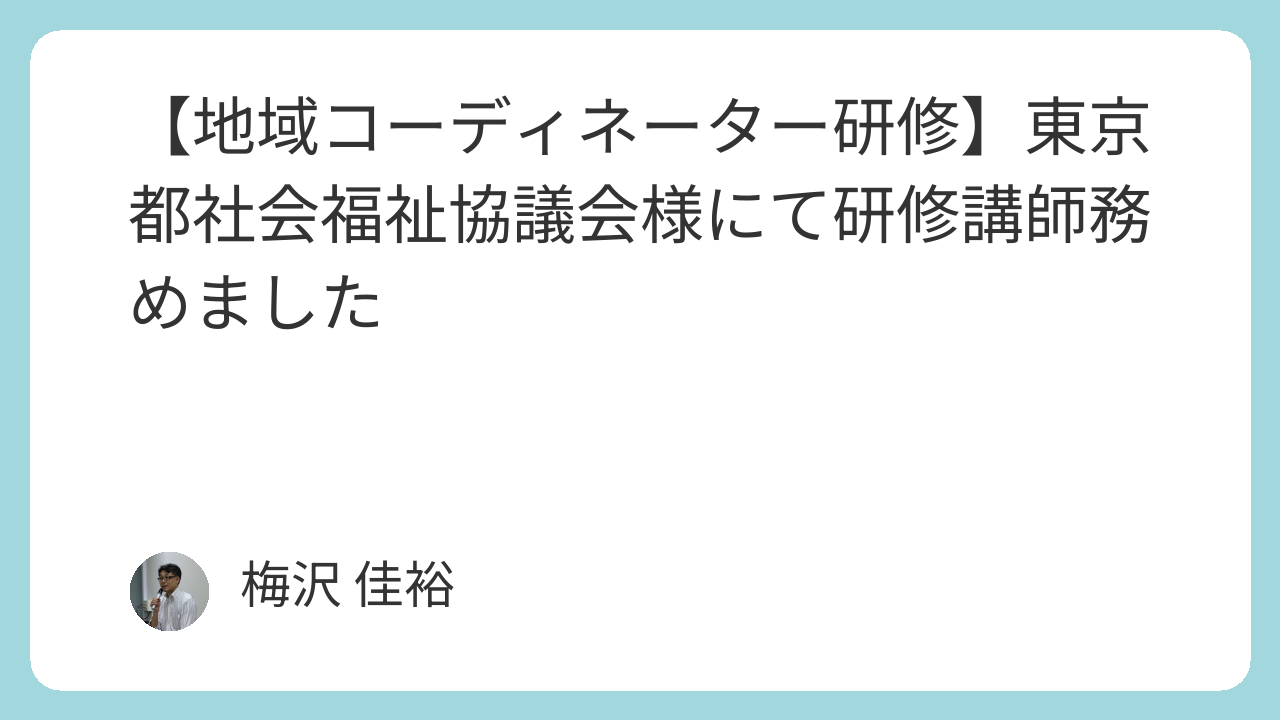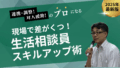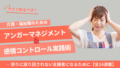皆さま、こんにちは。ベラガイア17の梅沢佳裕です。
今回は、東京都社会福祉協議会様よりご依頼をいただき、
「地域コーディネーターの実践力向上研修」の講師を務めさせていただきました。
この研修は、住民参加型たすけあい活動に携わるコーディネーターの皆さまを対象に、
地域での支援調整やケース会議の進め方を、実践的に学ぶ内容として開催されました。
1.研修概要
- 主催:東京都社会福祉協議会 住民参加型たすけあい活動部会
- テーマ:ケーススタディとケース会議「地域コーディネーターの実践力向上研修」
- 日時:2025年10月 14:00~17:00(集合研修)
- 会場:飯田橋セントラルプラザ12階
- 対象:住民参加型たすけあい活動団体のコーディネーター等
2.研修の様子
冒頭の講義①「住民参加型たすけあい活動におけるケース会議とは」では、制度では対応しきれない暮らしの課題に向き合ううえで、「ケース会議は“正解”を出す場ではなく、“次の一歩”を共有する場である」という視点を提示しました。
特に、独居高齢者や買い物困難者、支援拒否傾向の方など、制度の“はざま”にあるケースこそ、
地域の知恵と柔軟な合意形成が必要であることを強調しました。
続くケーススタディ①では、「買い物が難しい独居高齢者」を題材に、支援者間の温度差や本人のサービス拒否といった“二重の困難さ”を抱えたケースを取り上げました。
グループ討議では、「Aさんの安心な買い物生活を支える」という具体的な目的に絞り、
支援方針を曖昧に広げすぎないこと、意見を交通整理しながら小さな合意を積み重ねることの大切さを考えました。
参加者の皆さんからは、「全員が一度に納得しなくても“できること”から始める勇気が必要だ」との意見も多く挙がりました。
講義②「コーディネーターに求められる視点とスキル」では、支援者同士の意見調整や合意形成を進めるうえで、コーディネーターに欠かせない3つの力――「中立性」「小さな合意形成」「継続的フォロー」――を解説。感情論に流されず、事実と根拠をもとに意見を整理すること、「誰が・いつまでに・何をするか」を明確にして次につなげることが、現場の信頼関係づくりに直結することを共有しました。
そしてケーススタディ②では、制度では支えきれない家庭を題材に、「妻の介護疲労と孤立」を中心テーマとして議論を深めました。
公的支援だけでは限界がある中、地域のつながり(近隣住民・ボランティア・民生委員)を資源としてどう生かすかを考え、「安全・安心」「生活の持続」「本人の尊厳」の3軸で意見を整理しました。
「小さな声かけ」「見守り」「居場所づくり」など、“できることから始める支援”を合意するプロセスが印象的でした。
研修の締めくくりでは、参加者の皆さまが「自分の地域に戻ったらまず取り組みたい一歩」を言葉にし、現場のネットワークづくりに向けた意識を新たにされていました。
今回の学びを通して、地域コーディネーターが“伴走型支援の推進役”として動くための手応えを感じていただけたと思います。
(著者・講師:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕)