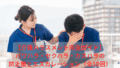~介護離職を防ぐ「見える化」と継続支援の仕組み~
両立支援プランとは?
仕事と介護の両立を可能にするには、制度があるだけでは不十分です。社員一人ひとりの状況に応じて、具体的な支援内容を整理・合意する仕組みが必要になります。
そこで有効なのが、両立支援プラン(個別支援計画)です。これは、介護を抱える社員と企業が一緒に話し合い、勤務調整や制度利用、業務上の配慮などを文書化して共有するツールです。
厚生労働省もこの仕組みを推奨しており、公式にひな型を公開しています。実務担当者はこのテンプレートを活用しつつ、自社の状況に合わせてアレンジするのが効果的です。
➡ 厚生労働省「仕事と介護の両立支援 面談シート 兼 介護支援プラン」
➡ 厚労省「仕事と介護の両立支援 面談シート 兼 介護支援プラン」記入方法と記入例
プラン作成のタイミングと流れ
両立支援プランを作成するタイミングは「介護が始まってから」では遅れがちです。以下のような場面で早めに取り入れることが望ましいでしょう。
- 介護休暇や介護休業を申請したとき
- 勤務時間の変更や在宅勤務の希望が出たとき
- 定期面談で家庭の変化が確認できたとき
- 社員から「両立が難しい」と相談があったとき
実際の流れは以下のとおりです。
- 事前面談:社員から状況を丁寧にヒアリング
- 支援内容の整理:勤務調整や制度利用を検討
- 文書化と合意:プランにまとめ、本人・上司・人事で確認
- 定期見直し:数か月ごとにフォロー面談を行い、更新
記載すべき基本項目
両立支援プランには、次の内容を盛り込むのが基本です。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 社員の基本情報 | 氏名、所属部署、連絡先 |
| 介護の状況 | 続柄、要介護度、介護保険の利用状況 |
| 支援の必要度 | 通院の付き添い、食事介助、見守りの有無 |
| 勤務の希望 | 時短勤務、在宅勤務、残業制限など |
| 利用予定の制度 | 介護休暇、介護休業、有給休暇の活用計画 |
| 業務上の配慮 | 会議参加の調整、業務分担の見直し |
| 今後の見通し | 状況が変化する時期、次回の面談予定 |
これらを表形式で1~2枚に整理し、関係者で共有することで、運用がスムーズになります。
面談の進め方 ― 対話で信頼関係を築く
両立支援プランを作る面談は、単なる手続きではなく、社員が「会社に相談してよかった」と思える機会です。実務者は次の点に留意しましょう。
- 社員が安心して話せる雰囲気をつくる
- 一度で全て決めず、まずできることから始める
- 「制度を使っても不利益はない」と明確に伝える
- 業務調整の現実的な線を上司と共に検討する
また、数か月ごとの中間チェックを設けることで、介護の変化にも柔軟に対応できます。
実務上のメリット
支援の属人化を防ぐ
両立支援プランがあれば、担当上司による対応のばらつきを防ぎ、一貫した支援が可能になります。
業務調整が計画的にできる
事前に業務負担の調整が見える化されることで、チーム全体で協力しやすくなる効果があります。
状況変化に応じて見直せる
介護は時間の経過で変わるもの。プランを軸にすれば、状況変化に応じた柔軟な更新ができます。
まとめ ― 「辞めなくていい」を形にする仕組み
仕事と介護の両立支援プランは、書類ではなく、社員が安心して働き続けるための信頼の証です。
「会社が一緒に考えてくれる」「相談してよかった」という実感が、介護離職を防ぐ最大の力となります。
厚労省のひな型を参考に、まずはシンプルな形から導入し、自社の文化や実情に合わせて育てていきましょう。
(筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕)