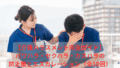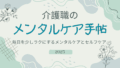~“予防型”両立支援で、介護離職を防ぐ信頼ある職場へ~
介護離職は「突然」ではなく「予兆」に気づけるかが鍵
社員から「介護が必要になって…」と相談を受けることがありますが、実は多くの場合、相談の前に「通院の付き添いが増えた」「親が一人暮らしで心配」などのサインがあったケースが多いです。
だからこそ企業は、介護離職を未然に防ぐために、「介護が始まる前」から備えを整えておくことが大事なのです。今回は、人事労務担当の皆さまに向けて、親しみやすく、かつ制度に正確な表現でお伝えします。
1. 制度を「知ってもらう」工夫で、早めの相談につなげる
周知されていない制度が離職につながることも
多くの企業では、以下のような介護関連制度を整えているはずです:
- 介護休暇(年5日、要介護家族1人につき)
- 介護休業(通算93日、分割取得可能)
- 短時間勤務・残業制限
- フレックスタイムや在宅勤務などの柔軟な働き方
これらは「育児・介護休業法」によって整備が求められており、従業員が希望すれば使える仕組みです。しかし、制度が知られていない・使いづらいことが離職を招く原因になっています。
周知するタイミングの工夫が効果的
- イントラや社内報で制度内容を定期的に案内
- 40代以上のライフステージに応じた啓発パンフレット配布
- 社内研修やメールなどで制度への理解を促す“気づき”の場づくり
こうした工夫が、「自分や家族の状況が変わったときに、使える制度がある」と気づかせる大きなきっかけになります。
2. “自分ごと”として考えてもらう研修・啓発の場づくり
「どこか遠い話」では終わらせない
「うちの親はまだ健康だから…」と思っている社員も、いつか介護が必要になる可能性は誰にでもあります。その前に「介護リスクは身近な話」と感じてもらうことが重要です。
実施したい研修・学びの場の例
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 管理職 | 部下が介護になったときの対応方法、制度の適切な案内の仕方 |
| 中堅社員 | 自分や親の状況を見つめながら、制度を「知って活かす」方法 |
| 全社員 | 介護保険や両立支援の基本知識、相談窓口の案内など |
研修には、事例やストーリーを盛り込むと、「自分のこととして考えやすくなる」という声も多く、実務でも効果が高いです。
3. 相談しやすい仕組みと風土を整える
制度紹介だけでは不十分。“相談できる職場”を整備する
制度があっても、「制度を使うと評価に響くのでは」と思われては意味がありません。制度の存在とともに、相談しやすさを備えた職場づくりが必要です。
具体的な仕組みの例
- 両立支援窓口を明確に設定(人事・社労士・保健職と協働も)
- 定期面談で家庭状況をさりげなく確認(プライバシー配慮をした上で)
- 制度利用の流れ・申請の簡素化
- 先行事例や体験談を匿名で紹介し、利用への心理的ハードルを下げる
こうした仕組みがあることで、「誰かに気兼ねなく相談できる職場」という信頼が生まれます。
過去回もぜひご活用ください
まとめ|「相談しやすさ」が介護離職の防止につながります
介護離職は、制度がないから起きるのではなく、備え不足と相談しにくい環境が重なって発生することが多いものです。
だからこそ企業としては、
- 制度をわかりやすく伝え、
- 学ぶ機会を通じて“自分ごと化”し、
- 相談のしやすさを制度・風土面で整える
という「予防型の両立支援」が求められます。制度だけでなく、情報・研修・相談体制が揃えば、社員が安心して働き続けられる職場になります。
外部リンク|厚生労働省「仕事と介護の両立支援」ポータルサイト
ぜひ以下の公式サイトも参考にしてください。制度の理解だけでなく、実例やマニュアル、動画なども豊富に掲載されています。
- 厚生労働省「仕事と介護の両立支援 ~両立に向けての具体的ツール~」
- 厚生労働省「介護離職ゼロ ポータルサイト」
次回予告|第5回:「両立支援プラン」の設計と実践ポイントを詳しく解説します
第5回では、介護と仕事を両立する社員のための「両立支援プラン」(個別支援計画)の作り方から実務運用まで、わかりやすくご紹介いたします。