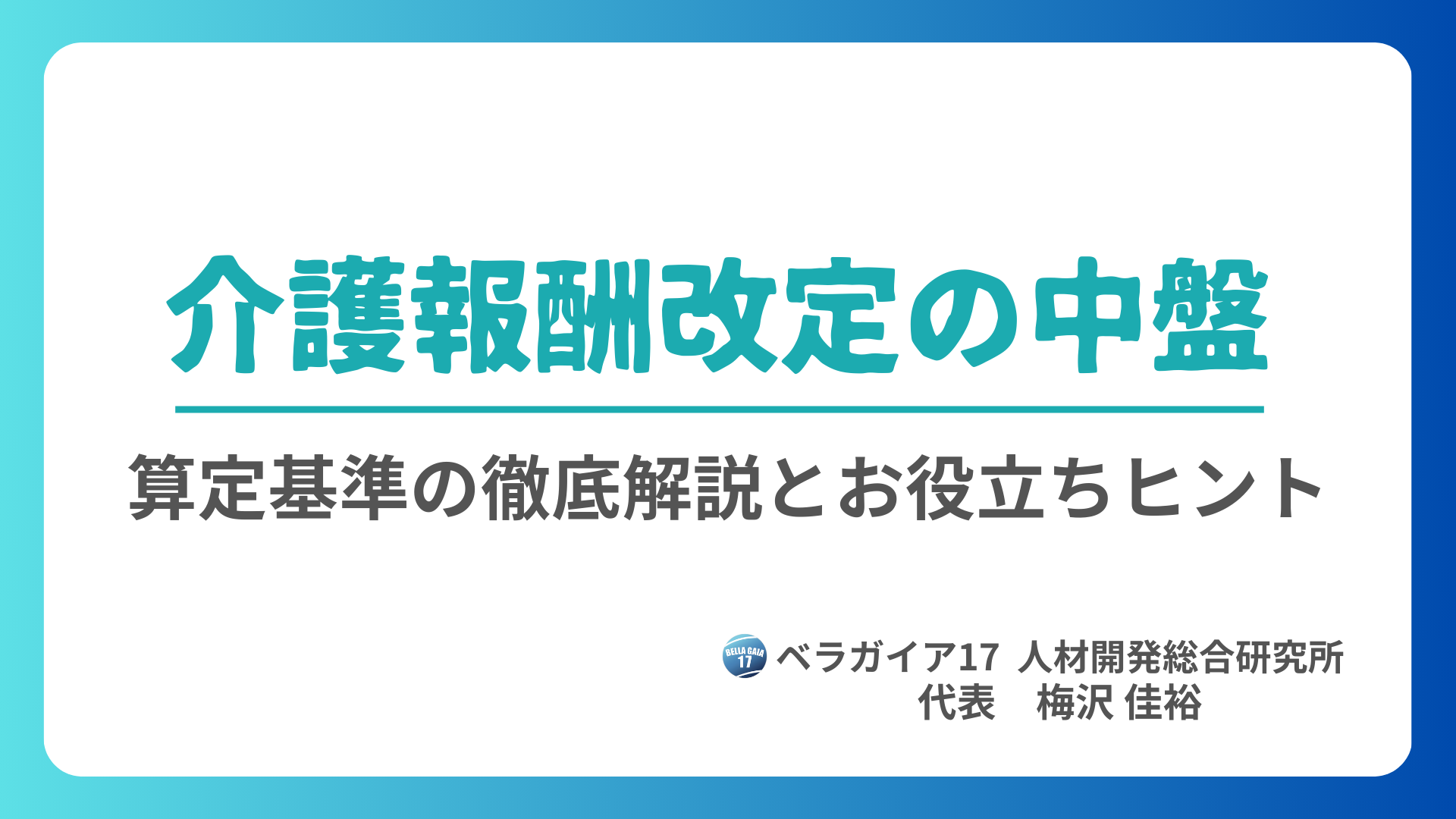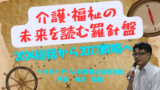介護報酬改定により義務化された介護BCP(業務継続計画)には、自然災害BCPと感染症BCPの両方が含まれています。しかし、この2つは全く性質が異なり、計画の立て方も実践方法も大きく変わってきます。
これまでの連載では自然災害BCPを中心に取り上げましたが、最終回となる今回は「感染症BCP」に焦点をあて、自然災害BCPとの違いや、平時からの備え、そして実務者が現場で取り組める実践的な工夫を紹介します。
1.感染症BCPの基本構成|4つの柱
感染症BCPは、厚労省ガイドラインに基づき以下の4要素で策定します。
- 初動対応:体調不良者の早期発見、隔離対応、感染管理責任者の指示系統
- 感染拡大防止:ゾーニング、防護具の使用、環境清拭と換気の徹底
- 業務継続体制:人員不足時の代替要員手配、優先業務の明確化
- 情報共有:保健所や家族への報告フロー、記録と改善サイクル
これらを「計画書」「行動フロー」「チェックリスト」として整備し、日常的に研修へ組み込むことが必要です。
2.自然災害BCPとの違い|感染症特有の視点
感染症BCPの最大の特徴は「施設は使えるが、人が動けなくなる」ことです。自然災害との違いを整理すると次の通りです。
| 比較項目 | 自然災害BCP | 感染症BCP |
|---|---|---|
| 影響 | 建物破損・停電・断水 | 利用者・職員の感染、隔離、出勤停止 |
| 優先行動 | 避難・安全確保 | 感染防止・人員配置 |
| 初動対応 | 数分〜数時間 | 数日〜数週間の継続 |
| 関係機関 | 消防・避難所 | 保健所・医師会 |
➡ 感染症BCPでは、「施設を閉じずに機能を維持する」ための工夫が求められます。
3.平時から備えるべき感染症BCP対策
✅ ミニシミュレーション訓練
- 「職員が発熱で欠勤、代替はどうする?」を想定。
- 月1回の5分ロールプレイでも効果大。
✅ ゾーニングと物品配置
- マスク・ガウン・手袋の在庫確認を月1回ルーチン化。
- ゾーニング図を掲示し、導線を全員で確認。
✅ 業務優先順位の事前決定
- A:必須(食事・排泄・服薬)
- B:調整(入浴・清掃)
- C:中止可(レクリエーション)
➡ 職員が迷わず動けるよう、平時からルール化しておくことが重要です。
4.介護実務者が自らできる実践アクション
感染症BCPを「管理者だけの計画」にせず、職員一人ひとりが取り組める内容に落とし込みましょう。
日常業務でできること
- 健康観察と記録を徹底し、体調変化をチームで共有
- 標準予防策(マスク・手袋・手指衛生)を徹底し、習慣化
- 5分ロールプレイで隔離や動線確認を繰り返す
- 人員不足を想定し、優先業務を理解しておく
自分自身の「パーソナルBCP」
- 出勤困難時の代替手段(徒歩・自転車)を想定
- 家族との安否確認方法を事前に決めておく
- 「勤務優先の合意」を家族と共有しておく
➡ 職員自身の備えが、施設全体の業務継続を支えます。
5.研修・カンファレンスで浸透させる工夫
感染症BCPは「共有」されてこそ実効性があります。
- 新人研修:感染症時の基本行動マニュアルを学ぶ
- 定期研修:インフルやコロナ流行の事例検討
- リーダー研修:意思決定と責任者の役割を実地訓練
- 掲示物:連絡フロー図、ゾーニング図、日常チェックリスト
➡ 繰り返し触れることで“頭でわかるBCP”が“体で動けるBCP”に変わります。
6.まとめ|感染症BCPは「計画+人+動線」で育てる
感染症BCPは自然災害BCPと違い、長期にわたる人員不足や感染拡大を前提としています。だからこそ、小さな訓練・日常的な備え・職員一人ひとりの意識が不可欠です。
- 計画を整えるだけでなく、
- 人が動ける仕組みを平時からつくり、
- 動線や物品の整備を常に点検する。
これが、介護施設の感染症BCPを“生きた計画”に変える道筋です。
【自然災害BCPと感染症BCPの全4回連載 完結】
今回で全4回のBCP連載は一区切りとなります。
次回からは新連載:
「2024年介護報酬改定の中盤 ― 新設加算の徹底解説と算定のヒント」
を予定しています。加算の要件や算定の工夫を、現場目線でわかりやすく解説します。