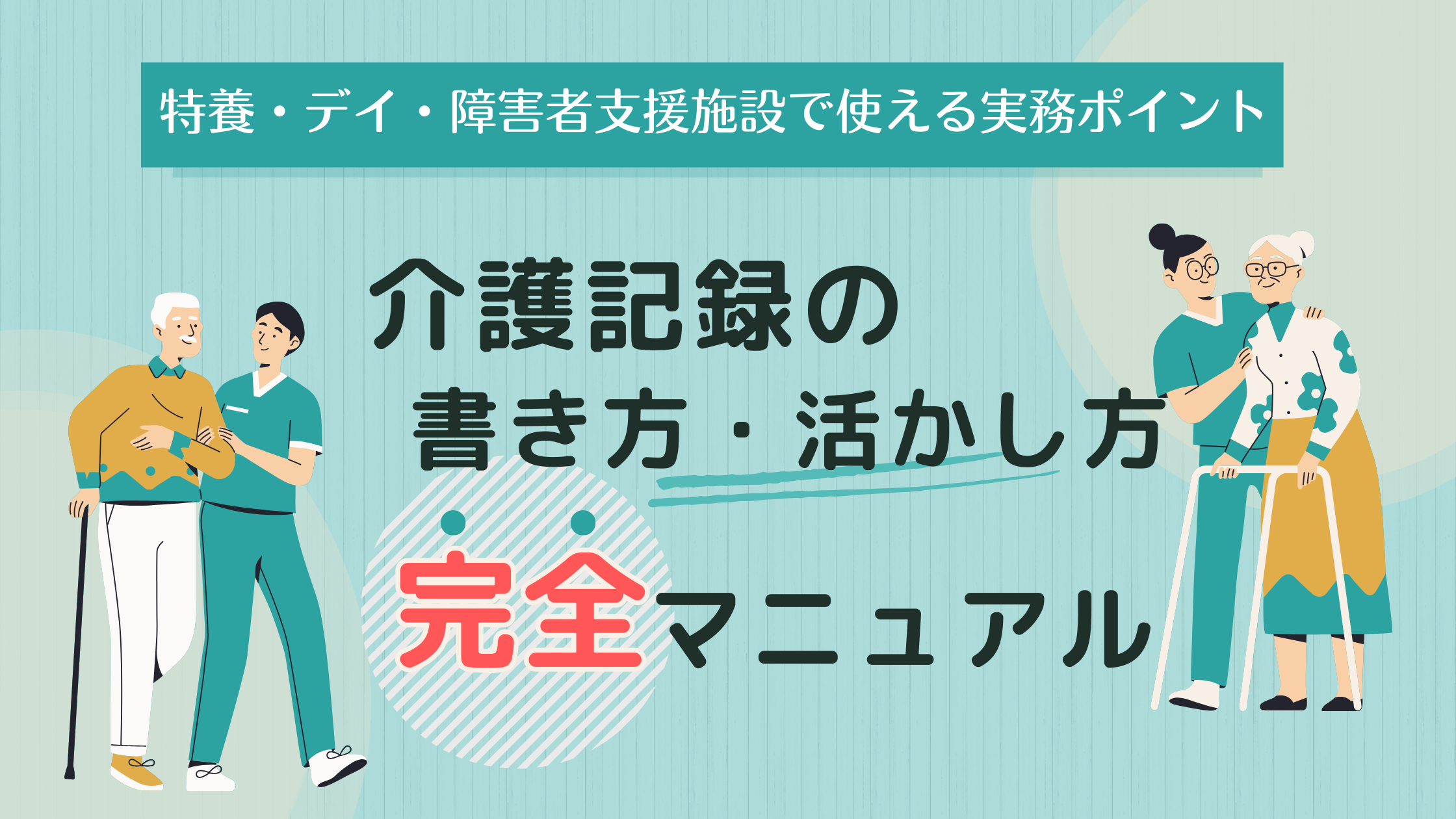介護記録は、未来のケアを導く“道しるべ”です。
特養・デイサービス・障害者支援施設…どの現場でも、記録がしっかりしていれば、後から勤務に入った職員は迷わず利用者に寄り添えます。
逆に「何があったのか分からない」「結局どう対応したの?」という記録では、他の職員を迷わせてしまいます。
今回は、誰が読んでも正確に状況を再現できる、介護記録の基本ルールと書き方のコツを解説します。
1.まずは5W1Hで整理
Who(誰が)/When(いつ)/Where(どこで)/What(何を)/Why(なぜ)/How(どうした)
この6つを押さえると、情報が抜けにくくなります。
例:
10:15(When) 職員A(Who)が居室(Where)で利用者Bさん(Who)に水分提供(What)。嚥下時にむせあり、誤嚥予防のため一時中止(Why)。看護師に連絡し観察(How)。
2.事実と意見を分ける
NG例:「今日は元気そうだった」
OK例:「午前中はレクリエーションに参加し、笑顔で3曲歌った」
→ 意見や感想ではなく、誰が読んでも同じ状況をイメージできる事実を書きましょう。
障害者施設では「落ち着かない様子」など抽象表現は避け、「椅子から立ち上がる動作を5分間に3回行った」など具体的に書くと読み手に誤解を与えることなく伝わる記録になります。
3.具体的な数値・状態を書く
NG例:「たくさん食べた」
OK例:「昼食は全量摂取、咀嚼に時間を要した」
NG例:「尿が多かった」
OK例:「尿量約400ml、淡黄色、異臭なし」
→ 特に排泄やバイタルは定量化することで、健康状態の変化を見逃しにくくなります。
4.時間を正確に記録
記録時間は、発生した時刻を正確に。
「昼食後」より「12:35」の方が、後から読み返すときに有用です。
急変時の対応では、時刻が命を左右することもあります。
5.略語・内部用語は使わない
「普段この事業所で使っているから大丈夫」と思っても、他職員や第三者には伝わらないことがあります。
NG例:「ADL低下」だけ記載
OK例:「起き上がり時に手すりを使うようになり、所要時間が20秒から40秒に延びた」
6.状況+対応+結果をセットで書く
記録は「何が起きたか」だけでなく、「どう対応したか」「その結果どうなったか」までがセット。
例(特養):
14:10 居室で転倒発見。右ひざ打撲痕あり、疼痛訴えなし。看護師がアイシング実施、15分後も疼痛訴えなし、歩行も安定。
例(障害者施設):
作業中に大声で歌い出し、他利用者が集中できない様子。職員が静かな部屋へ誘導し、10分後に落ち着き作業再開。
7.NGワード集
- 「多分」「おそらく」 → 推測は記録に迷いを生むためNG
- 「変わりなし」 → どの状態が続いているのか、変わりないその様子を具体的に書きましょう
- 「元気」「落ち着いている」 → 観察してどのようなことから元気と判断したのか書きましょう
8.“未来への道しるべ”としての心構え
筆者(梅沢)は、介護記録を「ケアチームのメンバーが迷わず利用者を支えられるための道しるべ」だと考えています。
道しるべが曖昧で方向性が定まらないのでは、チームは道を見失います。
だからこそ、
- 読む人が次の行動を取りやすい
- 状況が正確に再現できる
- 必要な情報が過不足なく入っている
そんな記録を目指しましょう。
まとめ
介護記録は「書く作業」ではなく「未来のケアをつくる重要な業務」です。
特養でもデイでも障害者施設でも、5W1H+事実+具体性を意識すれば、質の高い記録が書けます。
次回は、場面別記録のポイント① 食事介助について、誤嚥防止や経管栄養などの具体的書き方を解説します。