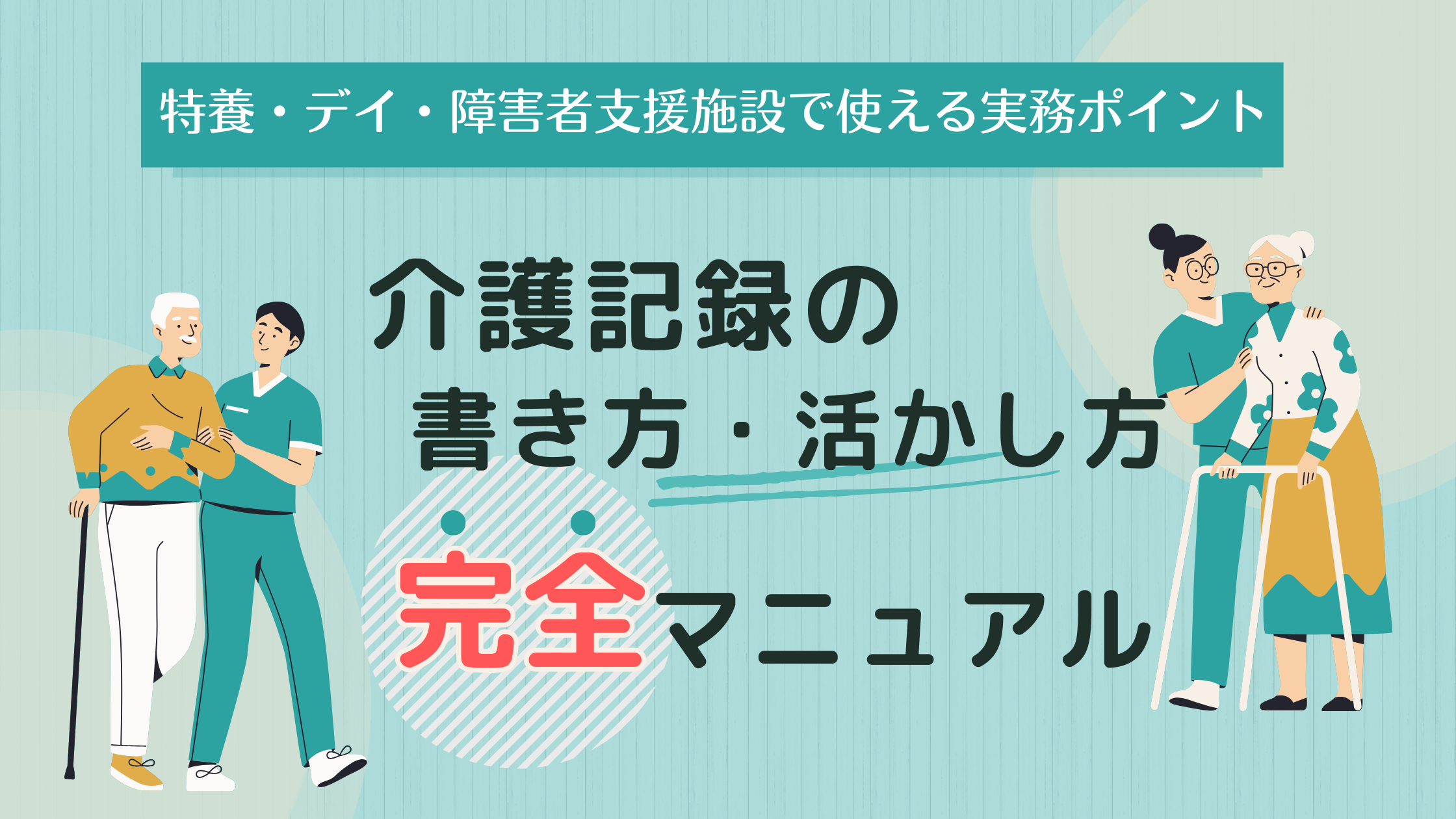「今日もバタバタして、記録は“とりあえず”で…」
こんな日、ありませんか?
でもちょっと待ってください。あなたが書く介護記録は、未来の自分と仲間、そして利用者さんを守る“最強の武器”なんです。
私は全国の介護現場で研修をしていて、「記録って正直面倒」という声をよく耳にします。
でも、もし記録がなかったら…? ケアが抜けたり、誤解が生じたり、最悪の場合は「やっていない」と見なされてしまうことも。
今日は、特養ホーム・デイサービス・障害者支援施設など、どんな現場でも使える介護記録の目的と重要性を、分かりやすく、しっかり解説します。
1.介護記録の3大目的
(1) 利用者の安全を守る
例えばデイサービスで、「昼食後に咳き込みあり、水分摂取は問題なし」と書いてあれば、次の勤務者は嚥下の様子に注意できます。
障害者施設でも、精神状態や行動の変化を早くつかむ手がかりになります。
(2) チームケアを強くする
介護はチーム戦。看護師・相談員・機能訓練指導員…多職種が連携してこそ良いケアができます。
事実に基づいた記録は、「なぜその対応をしたのか」をチーム全員が理解できる共通言語です。
(3) 法的証拠になる
事故や苦情が発生したとき、記録は事業所の盾になります。
「記録なし=やっていない」…そんな誤解を招かないためにも、正しい形で残しておくことが重要です。
2.高齢者施設と障害者施設の“似てるところ・違うところ”
似てるところ
- 状況を正確・客観的に残す
- 誰が読んでも同じイメージが湧くように書く
違うところ
- 高齢者施設:加齢による身体機能低下や病状の経過を中心に
- 障害者施設:行動特性や心理面、支援手順などの細かな記録が重要
3.記録が命を守ったエピソード
ケース1:早期搬送につながった記録
特養で入居者が夜間に発熱。日中の記録に「昼食後から元気がない、歩行ふらつきあり」とあったため、夜勤者はすぐ看護師に連絡。肺炎の重症化を防げました。
ケース2:行動変化をつかんだ記録
障害者施設で、利用者が「作業所に行きたくない」と数日続けて訴え。職員が毎回記録していたおかげで、軽いうつ状態が早期に発見され、医療につなげられました。
4.記録をサボるとどうなる?
- 大事な対応が抜ける
- 勘違いや誤解でトラブル発生
- 事故や苦情対応で不利になる
現場では「書かなくても覚えてるから大丈夫!」という声も聞きますが、人の記憶はあいまい。記録は“忘れないための保険”です。
5.初任者がまず覚えるべき4つのルール
- 事実と意見を分ける
例:×「元気そう」 → 〇「午前中はラジオを聴き、笑顔で手を振った」 - 数値や状態を具体的に
例:摂取量は「半分」「全量」など - 時間を正確に
例:「10:15 トイレ誘導、尿量約300ml」 - 略語は使わない
例:「バス」ではなく「浴槽入浴」など
6.梅沢流「良い記録」の条件
- 後から読んで状況が再現できる
- 誰が読んでも同じ意味にとれる
- 次の行動に役立つ情報がある
私は研修でこう話します。
「記録は未来のケアへの″道しるべ”です」
未来の自分や仲間が迷わないように、責任とケアチームのメンバーへ想いを込めて書く。読みやすいように、理解しやすいように、これが介護記録の本質です。
まとめ
介護記録は、特養・デイ・障害者施設のどこでも命と生活を守る最初の一歩です。
忙しい日こそ「必要な情報を、簡潔に、誰でも分かる形で」残す。
それが利用者の安心と、自分たちの安全を守るカギになります。
次回は、「介護記録の基本ルールと書き方のコツ」を、もっと具体的な事例と“やってはいけない表現”を交えてお伝えします。