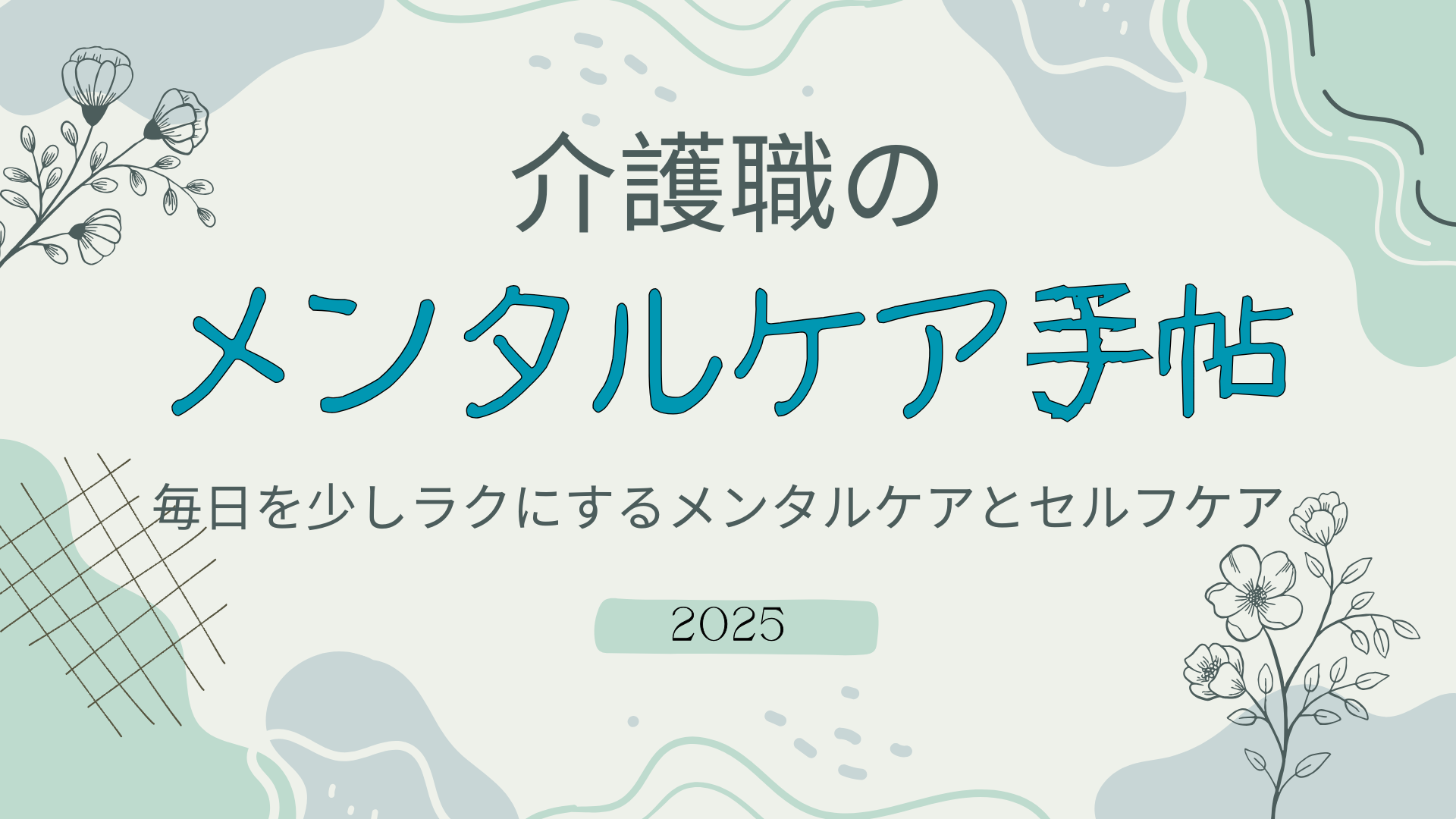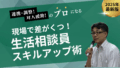「最近イライラしやすくなった」
「夜中に何度も目が覚める」
「なぜか食欲が落ちた」
こうした小さな変化を「疲れているだけ」と放置していませんか?
介護職にとって、ストレスは“日常的に付き合う相棒”のような存在です。しかし、そのサインを見逃すと、ある日突然、心と体が動かなくなることもあります。
介護の仕事を長く続けるために大切なのは、ストレスのサインを早めにキャッチすること。本記事では、介護職が日々の中で気づきにくいサインを整理し、実際のエピソードを交えながら解説します。
1.「心」に現れるサイン
介護の現場は常に感情のやり取りが伴います。利用者や家族に対して笑顔で対応しつつ、自分の感情を抑え込む場面が多くあります。その結果、心の疲労は思っている以上に溜まりやすいのです。
代表的なサイン
- 仕事に行く前から気分が沈む
- 利用者や同僚の言葉に過敏に反応してしまう
- 今まで楽しめていたことに関心が持てなくなる
- ちょっとしたことで涙が出る
あるデイサービス職員のBさんは「利用者さんの何気ないひと言が胸に刺さり、家に帰っても頭から離れなかった」と振り返ります。以前なら笑って受け流せたことが、心の余裕を失ったことで深刻に感じられるようになっていたのです。
心のサインは一見「性格の問題」に思えますが、実際にはストレスが限界に近づいている証拠です。
2.「体」に現れるサイン
心の不調は必ず体にも影響します。介護職は体力勝負の仕事でもあり、体調の変化を「ただの疲れ」と誤解しやすいのが特徴です。
代表的なサイン
- 睡眠障害(寝つけない・夜中に目が覚める・朝早く起きてしまう)
- 頭痛、肩こり、腰痛の悪化
- 食欲の変化(減退・過食)
- 動悸や息苦しさ
特養ホームで働くCさんは、夜勤明けに眠れず、昼間も熟睡できない状態が続きました。そのうち食欲も落ち、3カ月で5キロ痩せてしまったのです。本人は「シフトのせい」と思っていましたが、実際には慢性的なストレスによる自律神経の乱れが原因でした。
介護職の体調不良は「仕事柄仕方ない」と思われがちですが、繰り返す不調は心のSOS。早めにケアすることが重要です。
3.「行動」に現れるサイン
心と体の疲労は、最終的に行動にも表れます。職場での小さな変化が周囲にも伝わりやすく、仕事のパフォーマンスや人間関係に影響します。
代表的なサイン
- 遅刻や欠勤が増える
- 同僚や利用者との会話を避ける
- ケアの記録や業務のミスが増える
- 必要以上に攻撃的、または無気力になる
訪問介護員のDさんは、以前は利用者や家族との会話を楽しんでいました。しかし、ストレスが積み重なると「訪問先で必要なことしか話さない」ようになり、やがて記録の誤りも目立つようになりました。上司から声をかけられた時、初めて「自分が追い詰められていた」と気づいたそうです。
行動の変化は、本人よりも周囲の方が気づきやすいことがあります。そのため、同僚同士で声をかけ合うこともストレスケアの大切な一歩です。
まとめ
介護職のストレスサインは、心・体・行動のあらゆる面に現れます。
「気分が沈む」「眠れない」「会話を避ける」──そのどれもが、心の余裕が減っているサインです。
大切なのは、サインを軽視せず、早めにセルフケアや相談を行うこと。
深呼吸や小休憩、一行日記といった簡単な方法を組み合わせながら、日常的にストレスをケアしていきましょう。
今日の小さな気づきが、明日の「大きな不調」を防ぎます。介護の仕事を長く続けるために、ぜひご自身のストレスサインに耳を傾けてみてください。