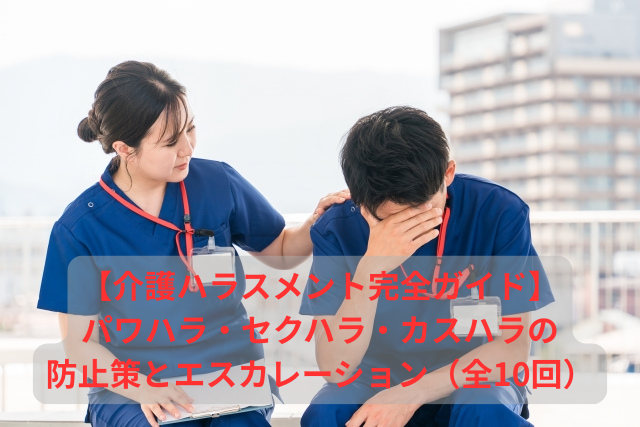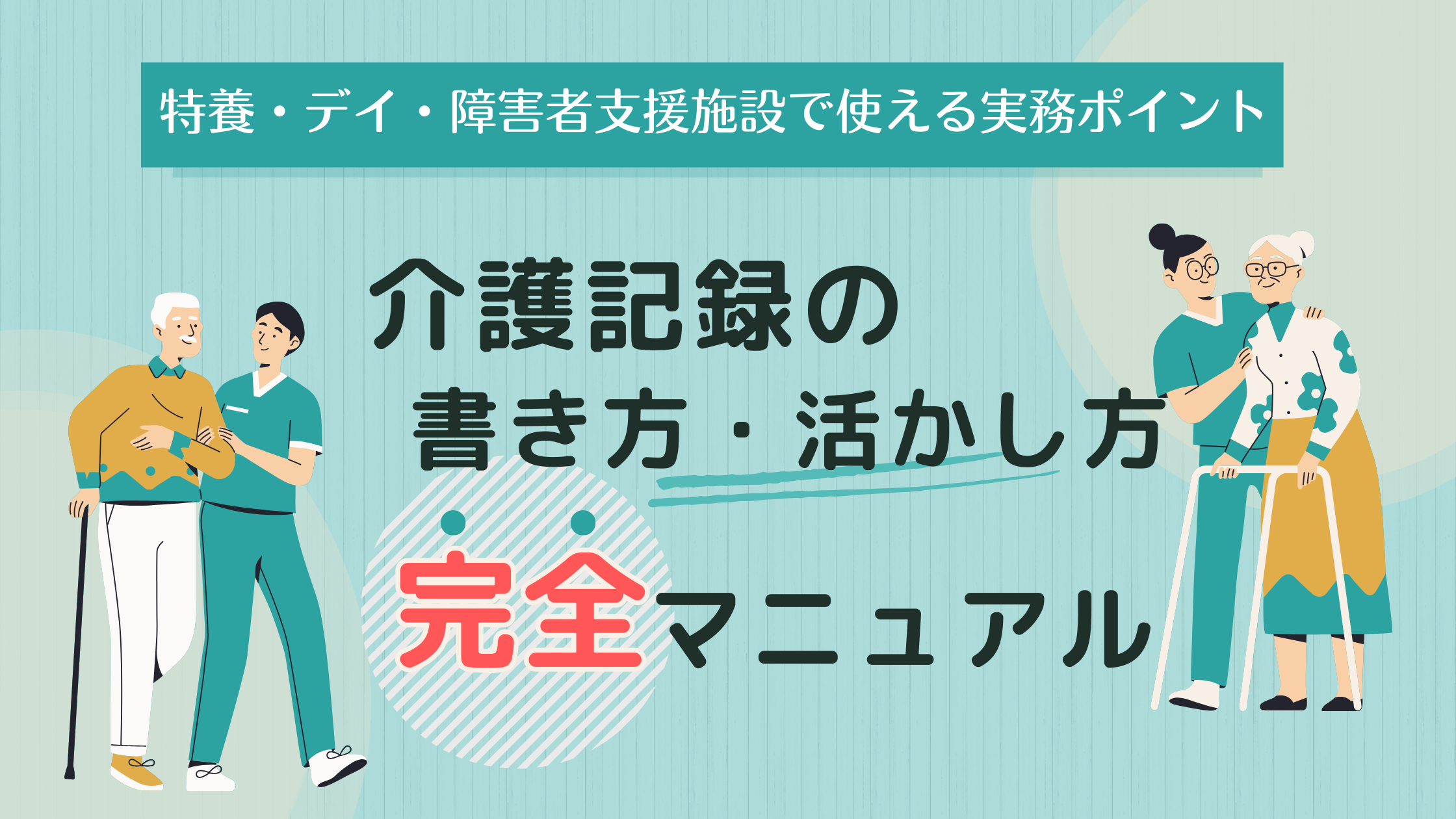特養ホームの朝。新人職員が入浴介助の段取りを間違え、先輩が思わず大声で言いました。
「何度も言ったよね!しっかりして!」
本人は“安全確保のための注意”のつもり。
しかし新人は「皆の前で恥をかかされた」と感じ、以降発言をためらうようになりました。
介護現場での注意・指導は必要不可欠です。しかし、言い方や場面の選び方を誤ると、すぐにパワハラと受け止められるリスクがあります。第3回では、ありがちな場面の整理、言い方の置き換え方、記録と相談の実務を解説します。
1|ありがちなパワハラに発展する場面
介護現場で多いのは、以下の3つのケースです。
- 大声で注意する
→ 安全確保のために声を荒げても、受け手には「怒鳴られた」と映りやすい。 - 公開の場で叱責する
→ 他の職員や利用者の前で「何やってるの!」と注意。屈辱感が強く残り、パワハラ認定されやすい。 - 過大・過小な仕事の割り振り
→ 「新人だから何でもやらせる」「逆に仕事を与えない」なども不適切な指導とされる。
➡ 共通するのは、“意図”ではなく“影響”で判断されること。
「安全のため」「育成のため」と考えていても、相手が萎縮し職場環境が悪化すればパワハラに当たります。
2|言い方の置き換え ― 事実→期待→支援
「叱る」のではなく、「伝える」ために有効なのがこの順序です。
- 事実:起きたことを具体的に
- ×「また間違えたの?」
- ○「入浴前にバイタルチェックが抜けていました」
- 期待:どうしてほしいかを明確に
- ×「ちゃんとしてよ」
- ○「次からは必ずバイタルを測ってから浴室へお願いします」
- 支援:困っていないか、どうフォローするか
- ×(なし)
- ○「手順を一緒に確認しましょう。私も横についてサポートします」
➡ “怒りの表現”ではなく、“改善の方向性+支援”に変換することで、相手は「自分を否定された」のではなく「仕事のやり方を改善すればいいんだ」と受け止めやすくなります。
3|指導の「場」を工夫する
- 人前で叱責しない:公開の場は萎縮を生む。短く安全指示だけ伝え、詳細は個別で。
- 時間帯を選ぶ:繁忙時は指摘が強くなりがち。落ち着いた時間に振り返りを。
- 1on1の定例を設ける:日常的なフィードバックの場があれば、叱責の必要性が減る。
➡ 上司・リーダー層は「注意をどの場で行うか」がハラスメント防止の分かれ道です。
4|記録と相談で「改善」に繋げる
もし注意・指導の場でトラブルになった場合は、必ず記録します。
- 日時・場所
- 発言の原文
- 対応した内容
- 相手の反応
例)
「2025/09/01 10:30 食堂。新人職員へ“食事介助前に嚥下確認が抜けていた”と指摘。大声になったと感じたため、その場で“あとで個別に確認しよう”と伝え直した。午後に1on1を設定。」
さらに、上司や相談窓口に共有することで、次の改善策や研修テーマにつながります。
まとめ:パワハラにしない指導の3ステップ
- ありがちな場面を避ける(大声・公開叱責・不適切な業務割り振り)
- 言い方を置き換える(事実→期待→支援)
- 記録と相談で残す(日時・原文・反応を整理)
介護現場のハラスメント防止は、厳しさをなくすことではなく、「伝え方」を工夫することで実現します。
職員が安心して成長できる環境づくりこそ、リーダーの大切な役割です。